ソーシャル・ジャスティス基金
助成発表フォーラム第13回 報告
ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)は、公募により審査決定した第13回助成先の方々(NPO法人アクセプト・インターナショナル 代表・永井陽右さん、きりしまにほんごきょうしつ代表 本田佐也佳さん、 NPO法人原子力資料情報室研究員兼活動家 高野聡さん、trunkアーティスト 中島伽耶子さん、NPO法人リカバリー代表・大嶋栄子さん)を迎えた助成発表フォーラムを2025年1月25日に開催しました。
各助成先がプレゼンと共に他の助成先とのクロストークも行い理解を深め合い、それらを基に全体での対話を行いました。この5つの助成事業は、「分断を超えた共生」というSJF助成公募の特設テーマに応募されたものでした。
「分断」が本当に分断なのか、見せかけの分断なのか、誰かが意図してつくった分断なのかを考えることの重要性がSJF運営委員長の上村英明から提言されました。世界の紛争地の現場で活動してきた永井陽右さんは、前提として、良い・悪いではなく、人の差異を受け止める、その存在を許す、そこから立ち上げなければ何も生まれないと経験を語りました。原発の核ごみ処分の受け入れをめぐって分断した地域で活動してきた高野さんは、賛成派も反対派もお互いが希望のある将来を共有できることが非常に重要だとの考えを示し、分断を生み出す大きな社会構造があることを皆に知ってもらって改善していきたいと語りました。
分断を生む一つとして、SNSが多方面から挙げられました。「当事者」と呼ばれる人に会う前にイメージが多くの人に作られてしまうからこそ意図的に分断が作られているという状況があると、取りこぼされがちな声をアート等で発信共有してきた中島伽耶子さんは指摘しました。霧島市で地域住民の外国人との共生に取り組んできた本田佐也佳さんは、SNSで持っていたイメージを払拭するためには本人との会話を通してしか変えられないものがあると、実際に接せられる場づくりの必要性を強調しました。そして、自分の中できちんと参照する軸をどれだけ作れるかが重要だと高野さんは述べました。
人数が少なかったり不可視化されたりしているために会話できる可能性が乏しくても、想像力などイメージを変えていく他の力も使って、連帯はできるはずだと中島さんは提言しました。ひどい暴力を受けるなど尊厳を奪われ薬物に依存せざるを得なかった女性を支援してきた大嶋栄子さんは、言葉にならない人とも多く接してきた経験を基に、一緒に農園で自分たちが食べるものを自分たちで作ってカフェもやっていると語りました。
困難をインターセクショナルな視点で解きほぐしていく姿勢がこれらの助成事業には通底していると大嶋さんは感想を述べ、現場は非常にシビアだけどポジティブであることが大事だと提言しました。テロリストと言われるような人であっても、そもそも人間であって、いろんな可能性がきっとあるはずで、自分にとって圧倒的他者と思えるような人との間に何を見いだせるか、より能動的な姿勢で何を生み出せるか、一緒に取り組む方が前向きだと思っていると、永井さんは活動姿勢を語りました。
詳細は以下をご覧ください。 ※総合司会、土屋真美子(SJF運営委員)

(写真=上左から時計回りで、大嶋栄子さん、高野聡さん、中島伽耶子さん、土屋真美子さん、本田佐也佳さん、永井陽右さん)
目次
- 1 ――開会挨拶――
- 2 ――第13回助成事業の発表とクロストーク――
- 2.1 ◆NPO法人アクセプト・インターナショナル代表・永井陽右さん 『パレスチナの若者リーダーたちによる分断を乗り越えるための対話と東京宣言の作成』
- 2.2 ◆きりしまにほんごきょうしつ代表・本田佐也佳さん 『外国籍住民への日本語教育等支援を通したエンパワーメント・地域の受け入れ体制の基盤作り事業』
- 2.3 ◆NPO法人原子力資料情報室研究員兼活動家・高野聡さん 『核ごみ調査に揺れる地域の声をすくい上げ、政策変更を促すアドボカシー活動』
- 2.4 ◆trunkアーティスト・中島伽耶子さん 『例えば「天気の話をするように痛みについて話せれば」2025』
- 2.5 ◆NPO法人リカバリー代表・大嶋栄子さん 『薬物依存女性を取り巻くスティグマの解消ならびに日本の薬物政策の見直しに向けたアドボカシー事業』
- 3 ――全体対話――
――開会挨拶――
上村英明・SJF運営委員長) 2011年に始まったソーシャル・ジャスティス基金の第13回目の助成発表フォーラムを迎えることになりました。今年はいろんな意味で市民社会を考える年になると思います。21世紀も四半世紀、25年目に入りました。それから今年は第二次大戦が終わって80周年という年にも当たります。
今回の助成公募では特別テーマで「分断を超えた共生」を掲げさせていただいたのですけれども、「分断」という言葉がこの社会をかなり覆い尽くすような流れが見える時代であり、これをどう乗り越えるかだけではなく、「分断」が本当に分断なのか、そこにある「分断」と言われるものが見せかけの分断なのか、あるいは誰かが意図して作った分断なのかということを考えながら、社会のあり方を見ていかなければいけないと思っています。
抽象的なので一例だけ挙げますと、韓国の尹大統領が12月3日に戒厳令を敷き、今は弾劾にかかっていますけれども、彼がそういうことをやった背景は何かというと、去年の選挙で野党が多数を取ってしまったということにあります。大統領が政権運営をしようとしても、国会で否決されることが多くなってしまった。これは別に韓国の問題だけではなくて、今の日本も同じで、少数与党なのです。そういう時に、大統領が自分の思いで政治を動かせなくなったために戒厳令を敷き、軍隊を使って国会を閉鎖し、反対派の国会議員を逮捕しようとしたので今回の問題が起きてしまったわけです。
これは「分断」という話ではなくて、単に民主主義の原則を大統領自身が否定したということを、社会が認めるか・認めないかという根本的な問題であり、「分断」が社会にあるという捉え方を決して軽々しくしてはいけないとは思います。
そう言った状況がこの社会にあり、20日に就任したトランプ大統領は早速、アメリカには「男性と女性しかいない」といった言葉で分断を煽るようなことを言っています。一方で、ガザの――これはどこまでどう続くかは後でお話を聞きたいと思いますけれども――停戦協定が実現するということもあります。
そういう意味で、私たちがこの社会の中における「共生」というものを改めてどう考えるかという、とても大事な時に、この第13回の助成発表フォーラムを開催できたことを大変うれしく思いますし、これをきちんと活かさないといけないと考えています。幸いなことに今回の助成公募にも58件の応募がございました。今回選ばれた5団体と共に、「分断を超える共生」という課題をどういうふうに前進させるのか、ご参加の皆さんと一緒に考えさせていただく会にできればと思います。

――第13回助成事業の発表とクロストーク――
◆NPO法人アクセプト・インターナショナル代表・永井陽右さん
『パレスチナの若者リーダーたちによる分断を乗り越えるための対話と東京宣言の作成』
私たちは日本生まれの組織で、「アクセプト(accept)」――「受け止める」という英単語ですけれども――、そんな思いを一つ大切にしながら、憎しみの連鎖を解いていくというミッションを持って、主にアフリカのソマリアや中東のイエメン、最近はパレスチナもやっています。そうした紛争地のようなところで、若者たちが暴力に加担することを予防する。そして、暴力に加担してしまった若者たち、例えば武装勢力で戦闘員をやっている若者たちが武器を置いてユニークな平和の担い手として社会に戻っていくための包括的なリハビリテーションのプログラムや社会復帰の取り組みを刑務所や捕虜収容所、特別リハビリ施設などでやっている変わった組織です。
同時に、そうしたことを軸に、この被害者や犠牲者への取り組みや、和解に向けた取り組みも行っていて、特にソマリアとイエメンでの取り組みが大きいです。今回、これまでのこうした経験や知見を踏まえて、パレスチナの問題に対して我々は何ができるのかと、去年から実は動き始めていて、今もガザの南部や中部で人道支援もやっているのですが、同時に、やはり和平に向けてもっとやるべきことがあるのではないかと取り組んでいます。
パレスチナ内やイスラエルとの交渉など色々あるのですけれども、一つ問題としてこれまでかなりあったのが、とかく男性のリーダーたちだけによって行われてきたという事実です。ですので、我々が目指す新たな対話と和平プロセスの構築においては、女性を含むパレスチナの各政党や社会組織の若手リーダーたちをどうにか中心として新たな場を作っていこうということで、実はいろいろ動いていました。
これまで3回、人知れず中東でハマスを含めた若手リーダーたちとの対話会合を開催してきています。特にネックとなるハマスに関しても、ハマスのシニアリーダー級からもかなり賛同や応援をされていて、ここから本当にパレスチナの若手リーダーたちで真にインクルーシブな、ずばりハマスを入れた新たな和平プロセス、対話会合を作ろうということで、今、必死に盛り上げて整えているところです。
今年もさらに2回ほど、カタールやレバノンなど中東の場所でこうした対話会合を続けると共に、どうにか8月頃に日本に招致をして日本で新たな和平の対話をできないかと考えています。まさに戦後80年の節目でもあり、パレスチナの方々も日本の復興や考え・経験を学びたいと言っているので、一つこの日本というポジショナリティを活かして、そうした場を作れないかと今回チャレンジしていきたいと思っています。東京か京都か広島か、まだ調整は必要ですが、最後には何かしら宣言をリーダーのみんなから出してもらって、機運を高めていきたいと思っております。
安全な対話の場――まずは受け止め、聴き、否定しない――
trunk 中島伽耶子さん) 個人的に『交差するパレスチナ』という本を最近読んでいて、その中で金城美幸さんが、植民地主義と家父長制は切っても切れない関係にあるし相互関係にあるということを語られていました。まさにその対話の場で男性の年長者たちが選ばれるという話も永井さんがなさっていたので、なるほどと思いながら聞いておりました。
対話の場を、参加者も聴いている人も安全なように作っていくとために何か工夫されていることはありますか。

永井さん) テクニカルには色々あると思うけれども、政治家でもないし、軍や情報機関の人間でもなく、本当に日本のNGO、「市民社会」という言葉を借りるならば正に「市民社会」のプレイヤーなので、そうしたポジションのアピール。あくまで我々は第三者であって、独立していて――実際独立していて、財源もご寄付や民間からの支援が一つ軸になっているので、こんな仕事もやれている――、そこを大切に前面に出して、巻き込んでいき、信頼を勝ち取っていくのが大事だと思います。
今回で言うと、やはりハマスのリーダーはかなり命が狙われていますので、一般的には会えないのです。かつ、テロリストだから会ってはいけないという見方も一般的に強いので、そんな中で我々が、紆余曲折ありましたけれども、こうした形でかなり巻き込めている。それで本当に新たな、ハマスを含めた和平プロセスのスタート地点を作り上げられているというのは、我々のこれまでの市民社会組織として独立した中での一貫性や、そこを大事にしているということが上手く伝わっている気はします。
あとは、否定しない。議論するためにやっているものではないので、まずは受け止める、まずは聴くというのをグランドルールにして、ちょっと優しい場にする工夫をしています。
中島さん) 活動団体名を地でやっている感じなのだと思います。
日本での対話会合に若者を7、8人ぐらいと話されていたのですけど、難しいということも話されていて、どういうふうに関係づくりを進めていくのか教えていただけますか。
永井さん) パレスチナ内の問題としては、パレスチナの中でまとまれないという問題がずっとあり続けているのです。いわゆるパレスチナ政府と言った時に、ファタハという大きい政党がメインなのですけど、一方でハマスという政党もあって、選挙が行われないだとか国際社会はハマスを認めないだとかという意味でファタハとハマスは結構仲が悪いわけです。なので、和解したパレスチナの政府をどう作るか、真にハマスを統合した暫定統合政府を作れるかというのが実はものすごく鍵になっていて、これまでずっと失敗してきたわけです。
なので、ハマス、ファタハよろしく他のパレスチナの政党の若手リーダーを巻き込んで、もう若手たちで新たな統合政府への道を別トラックで作っていこう、ということで取り組んでいます。そういう意味ではハマスはハマスでかなり一歩を踏み出していく勇気が必要ですし、ファタハはファタハで選挙をやったら多分ハマスが勝ちますので政権を取られてしまいますから怖いわけで、そういうジレンマを一緒に踏み出していきましょうと、みんなでエンカレッジしながらワイワイやるという感じです。
そこに第三者の価値があって、ハマスとファタハだけポンポンと置いていても何も進まないので、日本かつ日本の市民社会のピュアな組織がうまいこと間に入って別トラックを作っていくのは和平仲介の王道なので、日本の組織や日本人が持つユニークな可能性に賭けていきたいところです。今のところ、みんな日本のことをそんなに悪く言わないので、それがいい感じに作用しています。
中島さん) 活動が日本の印象になっているとも感じます。
活動概要のお話に「武器を置きユニークな平和の担い手として社会に戻っていくための支援」とありました。ここで「ユニークな」という言葉が使われているのも、すごく希望を感じると個人的に思いました。私は美術の世界で活動しているけど、活動や創作の場でも「ユニーク」が、何か話を始めたり、人に何かを伝えたりする時に大事になることがあると感じるので、希望を感じると思いました。
永井さん) その点もお目が高い。すごく大変で、我々の仕事は、無邪気な視座から見ると、更生支援や矯正の分野とか言われるけど、我々の意識としては全くそんなことがない。「矯正」は歯の矯正と同じ単語ですから意味がなくて、マイナスをゼロに近づける営みでしかないわけです。そんなことをやったって、いい芽が出ない。
なので、我々はもっとエンパワーメントの側面が強い。彼らの社会的・法的な悪い点にフォーカスするより、あくまで彼ら彼女らが持っているユニークな可能性――バックグラウンドや経験から生まれてくる学びとか色々あるので――にフォーカスして、むしろマイナスをプラスに変えていく。レトリックではなく、本当にユニークなプラスになれる。多くが若者なので、だったらお前が世界を変えろよという話なので、「矯正」とは自分は言いたくなくて、リハビリテーションとエンパワーメントという視座がある。
パレスチナにおいても、ハマスを脅威として捉えていかに彼らを潰すかより、むしろ彼らをどう統合して新たなパレスチナをパレスチナの方々が作れるかと考えています。実際、オスロ合意が失敗した理由は正にハマスを入れなかったことが一つなので、だったら今回は入れてこうよと。そこにある種アレルギーがなく、そこを本当に前向きに捉えて実現もできるのが我々の強みであり、バックグラウンドもあるので。
中島さん) 国際的な大きな流れをどうにかしようという活動でありながらも、その若者たち個人にもきちんと目を向けている。個人を大事にしようとする目線が伝わってきます。どちらかだけで話を進めることは無理だと思っているので、本当に素晴らしいなと思いました。
◆きりしまにほんごきょうしつ代表・本田佐也佳さん
『外国籍住民への日本語教育等支援を通したエンパワーメント・地域の受け入れ体制の基盤作り事業』
私は普段は日本語教師として外国人に日本語を教えています。
霧島市は鹿児島県で二番目に大きな市です。飛行機で来られた際に降り立つ鹿児島空港があるところです。農業が盛んで、自然豊かな小さい町です。霧島市の人口は12万人ですけれども、ずっと減り続けています。その一方で外国人の人口は増え続け、その変化がとても急激なので、対応が全く追いついていないのが現状です。それにより、様々な場所で不満やクレームが上がる状況になっています。
しかし、「外国人だから」が本当にその根底にある理由なのか、また彼らを責めることでその問題は解決するのかということを訴えたいのです。このような急激な変化が訪れると、彼らを排除することで問題がすべて解決すると誤解しがちですけれども、全くそのようなことはなく、かえって分断や対立を見ます。そして、この分断が深刻化すると、修正することは非常に難しくなります。
外国人の置かれた状況は、言葉や文化、習慣の違いなどの高い崖を必死に登らざるを得ないものになっています。一方、市民は高く安全な場所からただ彼らに努力を促し、それが上手くいかないと彼らに責任を押し付けています。私たちは、この高い崖を小さなステップを重ねて登れるようにし、両者が歩み寄りやすい状況を作る基盤を築かなければいけないと日々活動しています。
私たちが目指すのは、誰かに責任や負担を強いる社会ではなく、お互いに歩み寄る多文化共生社会です。私たちは外国人が参加しやすく、地域の方々と交流を持つための企画を日々考えて実行しています。そういった活動だけではなく、行政の変化が必要だと訴えるために市議との対談や男女共同参画審議員になるなど動き続けてきたけれども、壁の高さに気付かされるばかりでした。
そこで出会ったのが、ソーシャル・ジャスティス基金の理念でした。任意団体の私たちに挑戦の機会を与えてくださいましたことを心より感謝申し上げます。公募テーマである「分断を超えた共生」、「見逃されがちだが、大切な問題」が私たちの活動と重なるものが多く、挑戦してみようと決心いたしました。
助成を受けて私たちは三つの事業を行います。まず一つ目は、日本や霧島市での生活をよく知らないまま転入して生活トラブルになることを回避するために、外国籍転入者向けの生活オリエンテーションを定期的に開催します。またその場に、さまざまな言語ができる地域住民や留学生などのボランティアに参加してもらって、つながるような機会を設け、そこから彼らの孤立を防いだり、困った時にすぐ相談できるようなベースを作ったりします。
二つ目に、日本語ができずに就学が難しい子どもたちや、先生や周囲との意思疎通ができない保護者への日本語教育支援を行います。これは日本語教師の有資格者による専門的な授業です。ボランティアに参加したいという地域の方々の人材を発掘するためにも、学校や公民館を積極的に活用しようと思っています。
三つ目に、多文化共生をテーマにした地域の発信イベントを行います。これは外国人の置かれた背景や状況への無関心や無理解から受ける差別や偏見を減らしたいからです。国際交流に関心がある人以外にも興味を持ってもらえるようなイベントを、地域のNPOや留学生たちと関わって作りたいと思っています。
これらの活動を続ける中で、政策提言を行ったり、活動場所を市街地だけでなく山間部など複数の地域に広げたりしていきたいと考えています。 私たちはこのように地道な活動を2年ほど続けてきたけれども、アドボカイシー活動に関しては本当に初心者です。ソーシャル・ジャスティス基金の皆様にご助言をいただいたり、登壇されている皆様のご活動を参考にさせていただいたりしながら、一つずつ課題を達成できるように努めてまいりたいと思います。
リカバリー 大嶋栄子さん) まず初歩的な質問ですが、ボランティアによって構成されている団体ということなので、団体の規模感を教えていただけますでしょうか?

本田さん) 私が代表を務めているのですけれども、スタッフは全員で10名です。ほとんどがシニアの方で、退官や退職された方々が自分たちの力を何か社会に活かしたいということで、強い意志を持って活動されている方がたくさんいらっしゃいます。
大嶋さん) なるほど。先ほど、霧島市の人口が減っているのに対して外国籍の方たち増えている状況があるというお話があり、この増加の背景には具体的にどんなことがあるのでしょうか。
本田さん) 人口が減っているのは、高齢者はたくさんいらっしゃるけれども、若者世代がやはり都会に出たいということでごっそり抜けていって、新しく子どもが生まれないので真ん中の層の人口が減っていて、労働者人口が減るということで、技能実習生がたくさん来たのです。日本人の労働力不足を補うために技能実習生や特定技能の人たちが増えているというのが背景にあります。
大嶋さん)そうすると、これは本田さんたちが取り組んでいらっしゃる活動の理念とも関係してくることになるけれども、労働人口が減っている霧島市の近隣でその技能実習生の方となんらかのコミュニティを共にする方たちにはおそらく高齢者の方が結構いらっしゃって、その方たちにはこの技能実習生の方たちは、自分たちと同じコミュニティの一員だと見えていらっしゃるのでしょうか。
本田さん) これが本当に大きな問題です。技能実習生を受け入れる企業さんや自治会の会長さんは彼らが地域に入り込むことに対して好意的で、ルールを教えていたり、受け入れの支援をしている場所ではお祭りに招待したり、そういう雰囲気が生まれています。一方で、ゴミの分別ができてないとか騒音がひどいということで実際にアパートから追い出したり、苦情を会社や自治会、市役所、警察に言ったりして、方々に手を尽くして追い出そうとするところもあります。
だからこそ、私はこの活動をしなければ。霧島市の住民には、外国人が増えていることに恐怖心を覚えている人たちもたくさんいるのです。でも、その外国人の方たちは、私たちが補えなかった日本の政策や、霧島市の政策でどうすることもできなかったことのために来てくれていて、労働力として必死に頑張っているのに、それに対して追い出そうというムーブがあることが私はすごく嫌です。お互いが、どうして実習生がここにいるのか、どうして実習生がゴミの分別ができないのかという理由を知らないまま、外国人は嫌だからという単純な偏見や差別で排除するシチュエーションをどうにかして変えていきたい。そのために何かできることがないかと考えております。
大嶋さん) それが正に、これから日本の社会において、特に地方の人口の流出が激しいと言われる地域では大きな問題となってくるだろうというのはよくわかります。
実は私、日本における女性リーダーたちがお互いに自分たちの経験や知恵を分かち合うというグループに入っており、そのグループの一人で、いま北海道で同じような活動をしていらっしゃる方がいます。技能実習生の方たちに日本語――彼女は「優しい日本語」というコンセプトでやっていて――をお伝えしながら、同時にその方たちを受け入れる環境を整えていくことにアプローチしている。彼女のやっていることを、先ほど本田さんもおっしゃっていたように、行政や一般市民の方に理解をより深めていただくことは苦戦していると聞いています。なので、今日のご発表は、私が彼女から聞いていたことと重なる部分が多かったと思います。
最後の質問ですが、これはミッションもクリアで方法もはっきりと方向性がある一方で、いくつもの大きな壁があるのもよくわかります。ここを超えていくための本田さんたちの組織のあり方や、今後こうしていきたいというのがおありでしたら教えてください。
本田さん) 私たちも最初はNPO法人化したいと思ったのですけど、私たちの中心メンバーがシニアであったり、メンバーの数が一桁に減ったり増えたりということがあったり、会計が難しかったりということで任意団体になっています。この任意団体という形は、間口が広くなるという意味でも魅力的だと思っていると同時に、ボランティアでもここまでできるというモデルケースになれれば、と思っています。なぜなら、留学生も4年経ったらいなくなって短いスパンでしか関わることができないけれども、何かしたいという人たちが同じように行動を起こす地域で「きりしまにほんごきょうしつのみんなボランティアだよ」とやりやすいようなモデルケースになれればと思っています。
私たちは人数が少ないので、できることも少ないのですけど、他の団体さんや大学、今度できる日本語学校と連携していって、競合ではなく住み分けをして、お互いにできることで協力し合えるようにしていきたいと思っております。
大嶋さん) ボランティアという立ち位置だからできることや、どうやって広げていけるかということを検討していきたいのですね。
本田さん) そうですね。
土屋真美子さん) ありがとうございました。地域の地道な活動でありつつも、先ほどのパレスチナの話と共通点もあると思って聴いていました。植民地主義と家父長制はオーバーラップしているという話があったけれど、この地域にも家父長制があったり、技能実習生は基本的に植民地主義のようなものだったりしますよね。
本田さん) 強制されていますから。
土屋さん) そういう点でも共通点があるお話だったと思います。
先ほど大嶋さんもおっしゃっていたように、これから行政と連携していく時に壁があるだろうと思うのですが、ユニークな形でユニークな可能性を探りたいというお話がありましたが、これも本田さんがおっしゃったようにボランティアならではで乗り越えていけるかもしれないと思いました。
本田さん) ありがとうございます。頑張ります。今、いろんな議員さんからも興味を持って連絡が来たり、企業さんから「技能実習生に教えてほしい」というお話があったり、受け入れる側の意識が少しずつ変わってきているのだなと感じているので、このムーブを止めずに私ができる関わり方をしていきたいと思っております。
◆NPO法人原子力資料情報室研究員兼活動家・高野聡さん
『核ごみ調査に揺れる地域の声をすくい上げ、政策変更を促すアドボカシー活動』
まず当室の簡単な紹介から始めたいと思います。設立は1975年で、今年50周年迎える古くからの団体です。脱原発を目指す研究活動や市民運動を日々行っている非営利団体で、専従は7名、東京の中野に在籍しております。特長としては、ほとんど市民からの会費と寄付で成り立っているために政府や企業におもねらない独立した研究や市民活動ができることであり、誇りであると思っております。
この事業は、原発を運転することによって生まれる高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの処分政策に対して政策変更を求めるアドボカシー活動です。核のゴミには処分場が必要ですけれども、その処分場を建設するための調査があるのです。その調査の第一段階を「文献調査」と言うのですけれども、文献調査に応募した北海道の寿都町では町全体に地域の分断が広がってしまいました。あと、応募はしなかったけれども応募推進の動きがあった対馬市でも一部で地域の分断があり、また去年の6月に文献調査が始まった佐賀県の玄海町でも市民の間で不満が渦巻いています。
分断には例えばどういうことがあるのかというと、これは寿都町で顕著ですけれども、核のゴミの話題を避けて日常会話が減少してしまったり、友人と会う回数が減ってしまったり、賛成派・反対派がお互いわかっていればそのお店には行かないとか、地域の団体が調査推進派で固められてしまうとか。そのようにコミュニティの結束や日常生活に打撃が与えられて、将来のまちづくりでも支障が生まれているという状態です。
これ以上、地域の分断を繰り返さないための、政策変更が必要になっていると感じております。
そういう地域の分断を招いてしまう構造があるのが、この問題の背景かと思います。それを簡単に二つにまとめますと、まず、交付金が下りることです。調査だけで最大20億円の交付金が交付される。そして、その応募の権限は首長のみで、地域住民の合意や、透明な議論の仕組みがないので、交付金目当ての首長など一部の地域有力者が秘密裏に応募を推進して、全く知らされていない地域住民の反発が起こるという形になっています。
そういう政策を変えることもなく、政府は調査を実施する地域の拡大を進めているところで、非常に大きな問題が現在も起きているし、これからも起こり得ると考えております。
では何をやっていくのか。まだ核ゴミの文献調査実施地域の実情が知られていないので、シンポジウムを開催したいと思っております。文献調査の当該地域がある広域自治体あるいは東京あたりでの開催を検討しております。
それ以外にも、いま言った3つの地域の住民が現状報告をしながら意見交換を行うようなオンラインミーティングを数回重ねる中で、その地域の声が反映された政策提言集も作成したいと思っております。それが完成した暁にはプレスリリースと記者会見、国会議員への配布などのロービング活動、経産省との政府交渉にもつなげていきたいと考えております。
この事業は当室だけでは実現が難しいので、当該地域や東京の団体との協力が不可欠だと思っています。私は既に当該地域に何度も足を運んでいるので信頼関係が構築されており、事業はスムーズに進めることができるのではないかと感じております。
期待される効果は、まずは問題への関心が向上し、支援の増大により、阻害された地域住民へのエンパワーメントにつながるだろうと思っております。もう一つ重要なのは、私は核ゴミの問題を議論する政府の審議会、特定放射性廃棄物小委員会の委員を務めておりますので、そこでの政策提言や意見書に活かしていくことです。また、これから本格的に調査が進む玄海町での公正で透明な住民対話を実現したいです。そして、地域分断への対処。中長期的には、最終処分法の問題を改正する機運をつくっていきたいですし、その法による交付金等の制度変更も目指していきたいと思っております。
分断を生み出す大きな構造があることを賛成派も反対派も共有することが重要
アクセプト・インターナショナル 永井陽右さん) 専門的な視座からのお話ですごく勉強になりました。聴いていて難しい問題だなと思いましたが、何か日本よろしく世界でもうまくいっている例はありますか。この原子力の話は大きいお金が絡むと思うので、特にこうしたことにはなりやすいと思いますが、他にもこうした町を二分してしまうような分断を生んで、さらに分断を深めてしまうようなトピックはあるように思うので、そういう際に成功例とはどんなものなのか聞いてみたいです。
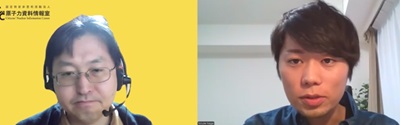
高野さん) この核ゴミの処分場政策に関して言うと、原発のあるほとんどの地域で悩んでいる状況です。フィンランドが一応、唯一、最終処分場を既に建設中です。その成功の秘訣というのは、日本よりはるかに透明性のある情報提供をしていることです。反対側の専門家の意見もきちんと聞けるような保障をしています。また、もう少し幅広い住民参加の形となっています。ステークホルダーの参加を意思決定の早い段階からしているので、そういうところは参考になるのかもしれないと思っております。
しかし日本においては一つ問題なのは、処分方法が地層処分という地下奥深くに核のゴミを埋めて捨てるという方法です。それが世界共通の方法にはなっているけれども、安全性の観点から言うと、フィンランドや最終処分場が決まっているスウェーデンの地盤は40億年ぐらいずっと安定しているのです。それに対して日本は4つのプレートがぶつかり合うような唯一の国と言っていいところでの地層処分となるので、市民の認識も差があると思いますし、専門家の意見も分かれているところです。
でも、地層処分ができると言うような専門家ばかりを審議会に集めて、そういう専門家の意見をどんどん住民に聴かせることによって一方的に説得――向こうの言葉で言うと、理解促進活動――をするという、そもそもそのチームがまずいのではないのかと思っています。日本においては、まずはもっと幅広く地層処分に対する賛成と反対の専門家の意見をもっと戦わせないといけないと思っています。
永井さん) パブリック・エンゲージメントも含めて我々はさらに議論や対話が必要だとか、市民社会側も政策決定にもっと参画をというのは分かるのですけど、実際は多くの人々、特に若い世代は「公民館とかに行って、ベテランの方がこんなの止めろとか言っていることに参加して、議論は成っているの?」みたいな感覚もある気がしています。もう少しオンライン上でカジュアルに参加できるのも必要だろうなと話を聴いていて思いました。
実際の議論や対話をさらに促進していく難しさのリアルはあるのですか。
高野さん) この核ゴミ問題自体がとっつきにくく、何か複雑な技術的な議論ではないかというイメージがあるので。もちろん技術的な問題もありますが。まずは、いま地域の分断が生まれてしまっているという問題点を、理論的・理性的なところだけでなく、感性的なところや、不公正で不当に抑圧された人たちがいるというところで共感を広げていきたいと思います。そこからの対話があるというのが一つ。
もう一つは、こういう問題の背景には、貧しい自治体を交付金で狙い撃ちするところがあります。国の補助金に今まで頼っているような地域社会が応募してしまうので、そうではなく、きちんとした住民自治をしましょうというアプローチで、核ゴミ問題に関しても対話を促すことができるのではないかと考えています。そういう住民主体のまちづくりの切り口であれば、もう少し幅広い層の、しかも堅苦しいイメージではなく対話を促すことができるのではないかと考えています。
この事業でシンポジウムの企画作りをする上では、堅苦しい政策だけでなく、とっつきやすい形でのアジェンダ設定を工夫したいと思っております。
永井さん) 「the市民社会」に、市民社会の役割や価値に改めてもっと光が当たってほしいと、自分も市民社会のプレイヤーとして思うので、本当にその一つのいい例だなと、素晴らしい活動だなと思いました。
高野さん) 地域の分断というと、住民同士がいがみ合ってしまうけど、それは本当に悲しくて、問題はそこではなく、地域の分断を生み出すような政策があって、それを国が押し付けているというところにあると思うのです。そういう大きな構造として地域の人たちにも問題を捉えてもらって、どうしても「応募した町長が…」みたいな形になってしまうけれども、そういう感情は持っていながらも、大きな問題として一つ分断を生み出す構造があることを、調査の賛成派も反対派も共有してもらうことは重要になると考えております。
◆trunkアーティスト・中島伽耶子さん
『例えば「天気の話をするように痛みについて話せれば」2025』
私たちの団体、trunkとは、秋田を拠点に、既存のメディアでは取りこぼしてしまわれがちな声を様々な形で発信、共有し、すべての人が生きやすい関係を目指して、ゆるく連帯しながら活動するコレクティブです。
様々な形というのは、例えば、トランスジェンダーの人たちを取り巻く差別に反対を表明する現代美術の展覧会を開催したり、性とジェンダーについて安心して話ができる対話の場所を対面や匿名参加ができるオンライン上で開催したり、秋田県の内外からゲストを招いてトークイベントを開催したり。また、trunkのメンバーは専門家ではないので、みんなで勉強するための本を読む会を開催したり、政治や映画の話を楽しく聞けるラジオ配信をしたり。自分で食べる野菜を自分で作るために畑を去年から始めました。こういうふうにいろんなことをしています。
なぜこんなにまとまりがないかというと、trunkというのは、みんなで一つの目標を目指すのではなく、個人が得意なことや関心があることをみんなで勉強して、生きやすさや人権について様々な角度で生活の中から考えていける団体を目指しているからです。
今年行う展覧会、「例えば『天気の話をするように痛みについて話せれば』」というプロジェクトをご紹介します。この展覧会は、トランスジェンダーの人々を取り巻く差別を出発点に2022年から始めたプロジェクトです。
近年はトランスジェンダーの人々に対する差別がSNSを中心に激化していて、多くの人が生きていけないと思わされるような現状があります。悪質なデマや誤った情報が故意に作られて、イメージが作られていって、あたかもトランスの人たちに問題があるような、トランスの人たちが問題を作り出しているように語られています。トランスジェンダーの人々に対する差別を考えることは、私たちの人権について考えることだと思っています。
今年は、差別に反対する気持ちを誰もが表明できるような、意思表示としての展覧会を東京で開催します。例年通り11月20日の「国際トランスジェンダー追悼の日」に合わせて開催することを考えています。
誰もが自由に好きな方法で安全に参加できるアンデパンダン形式の展示です。展示と聞くとなんだか堅苦しいイメージがあるかもしれないけれども、歌を歌ってもいいし、イラストを描いてもいい。文章を提出してもいいし、何か作らなくてもお気に入りのぬいぐるみを並べたり、好きな本を一冊選んだりすることでもいいかもしれません。何かを作る経験を持つ人に参加してもらえるのはもちろんですけど、作ったことが無い人にも気軽に参加してもらえるような工夫を考えています。
アートや表現というのは、単純な正しさではなく、複雑で混沌とした状況をそのまま形にして鑑賞者に伝えることを可能にすると思っています。想像もできない他人の経験や気持の一部を垣間見るのに、年齢や言語の制約なしに受け取れるのがアートの強みです。
「差別に反対する」、それだけが一緒であれば、他はバラバラでいいと思っています。一緒に行動しなくていいと思っているし、仲良くなくてもいいし、同じ方を向かなくてもいい。それが連帯だと思います。複雑な経験や気持ちを無理に揃えるのではなく、「差別に反対する」ことだけを唯一の共通の部分として集まって、「差別に反対する」ことが可視化される。そんな展覧会にしたいと思っています。
私は普段、秋田に住んでいて、交通費が高くて東京のパレードになかなか参加できていません。そもそもパレードが嫌いな人もいるし、人前に立つのにリスクを感じる人もいます。この展覧会は、その人自身の体が表に出るのではなく作品が前に出る、しかも名前を出さなくても参加できるという強みがあります。こういう差別に反対する方法もあっていいと思うし、これからもっといろんな方法が出てくるといいなと思っています。
きりしまにほんごきょうしつ 本田佐也佳さん) すごく面白い努力をされていると思いました。私があまりアートに詳しくなかったので、出てきた言葉の意味を教えてほしいと思っていて、アンデパンダン形式というのはどういうものですか。
中島さん) 美術展には審査員がいて出品できる人を選ぶ形式があって、希望する人みんなが出せるわけではないことが多いけど、アンデパンダン形式は、出したいと言った人がみんな無審査で出せる形式です。
本田さん) では、子どももシニアも出したいと思えば出せるし、どんな言語で書いたものであっても展示していただけるということですか。
中島さん) そういうことです。
本田さん) すごくいい取り組みですね。
最初にtrunkさんのこの助成事業の名前を聴いた時に、「天気の話をするように痛みについて話せれば」ってキャッチーで、どんなことをするのだろうと想像力をかきたてられるフレーズだと思いました。「悩み」や「苦しみ」でなくて「痛み」という言葉を選ばれた理由や背景があれば教えていただけますか。

中島さん) タイトルはみんなですごく話し合って、本当に長いタイトルになってしまいました。「痛み」を選んだ理由は、単純に比べられないはずなのに、痛みは対比されることもあるし、それを気にしてしまって上手くしゃべれなかったり、自分の痛みを感じているはずなのに痛みだと思わないように無理にしてしまうような状況、そうでないと耐えられない状況も出てきたりするので、いろんな状況を含められるといいなと思い、「痛み」を選びました。
また、安全な場でないとそういった状況を絶対に言葉にしたり、他人に何か表示したりすることは難しいと思うので、それがセットで読み取れるようなだといいなと思って名付けております。
本田さん) すごく惹き込まれるフレーズだなと思いました。日本人は「会話の一点目は天気の話をしろ」と言われるし、私たちも外国人のみんなに「日本人とおしゃべりする時、どうしたらいいですか」と聞かれる時は、「『暑いね』とか『雨降っていますね』から始まるんだよ」と言うぐらい、文化的なものがあります。
天気は誰も言う話なのに、痛みは私たちが接する外国人もそうで、病院に行った時に痛みを表現することができない。彼らは「ズキズキ」や「ガンガン」と言われてもわからない。「どれくらい痛いですか?」というのは人それぞれだし、表現の仕方も違うし、言いたいのに言葉や形にできないモヤモヤがある。
私は言葉が専門なので言葉に頼ってしまうけれど、アートという形にするのは、本当に子どもからおじいちゃん・おばあちゃんまでできるし、それこそ国籍も越えられるというのはすごくあると思って、素敵な取り組みだと思っています。こういう新しい活動に私が出会えたことは本当にうれしいご縁だと思いました。ありがとうございます。
中島さん) なんて温かい言葉、ありがとうございます。
立場が弱い人というのは、痛みを訴えても、それを信じてもらえない状況が実際に起きていて、ウィシュマさんの件もそうですし、トランスの人たちが医療に関わる時もそうです。立場が弱いと言っても、きちんと言葉で伝えても、それが権力のある方から拒否されることが往々にして起こってしまうこともあって、いろんな分野から痛みの話ができるようにと思います。
土屋真美子さん) 立場の弱い人は言っても伝わらないというのが、本当にそうだろうなと思ったのと、もう一つ、それを言葉にするには、安全な場である必要があるって、これもすごく大事なことですよね。
中島さん) そうです。いろんな種類の安全な場があると思っていて、多種多様なのを試していきたいと思っています。
土屋さん) そういう安全な場としては、きりしまにほんごきょうしつは、どうですかね?
本田さん) 私も中島さんの活動にすごく共感しています。私もとにかく数を打とうと思って、いろんなイベントをするので。そこにヒットしてくれる人が一人でもいたら、一人でもそこを居場所として感じてくれる人がいれば、それでいいと私は思っています。そこからまた惹かれる仲間がいるはずなので。そこで私が中心になる必要はないし、彼らは彼らで新しい活動を生み出していってくれたらいいなと思っているので、中島さんのように、分野は違っても、思いがつながるところがある人たちがたくさんいらっしゃるというのが励みになりました。
土屋さん) 場所が鹿児島と秋田で離れていて、多分ここじゃないと会えなかったかもしれないので、よかったです。また後でよろしくお願いします。
◆NPO法人リカバリー代表・大嶋栄子さん
『薬物依存女性を取り巻くスティグマの解消ならびに日本の薬物政策の見直しに向けたアドボカシー事業』
まず私たちの団体についてお伝えしたいと思います。任意団体としてスタートしたのが2002年の9月ですから、今から23年前になります。そして、2004年1月にNPOとして認証されました。
私たちのホームページを開きますと、なぜか赤い古いトラクターの写真が出てくるけれども、「嵐の後を生き延びてきた女性たちをソーシャルビジネスでサポート」というコピーがついています。もともと私たちの団体は 様々な暴力の被害を生き延びてきた女性たちを支援のターゲットとしてスタートしました。
そこからいろんな事業をやってきたけれども、現在は障害者総合支援法という法律に基づく事業をやっています。グループホームという住む場所、就労の練習をする場所、相談支援事業、自立生活を営んでいる人のところを訪ねてサポートする自立生活援助事業をやっています。
「リカバリー」というのが法人名ですが、施設にはいずれも「それいゆ」という名前が付けられていて、フランス語で「太陽」の意味です。私たちは、いろいろな困難をきっかけに精神的な不調や社会的な引きこもり状態などいろんな不具合を抱えている人たちがゆっくりと回復をしていくことをイメージして、その心の中にある回復の種が芽を出してしっかりと葉を出していく時にどうしても必要な「太陽」のような役割を果たせたらいいなということで、「それいゆ」という名前を各施設につけています。
最初は女性だけを支援の対象としていたのですが、2017年からグループホームだけ除いて男性も対象としています。
どんな人たちが使っているかというと、登録している人たちの8割には何らかのアディクション、何かに依存してコントロールができなくなる疾患があります。ただ、特に女性はアディクションの問題だけ抱えているわけではなくて、このアディクションを必要とする背景として、重たい暴力被害やそれによる複雑性PTSD、発達障害、軽度な知的障害――今は境界知能などとも言われていますが――、そういったいくつもの困難性が重複している方が約8割なのです。利用されている方は、相談室を含めますと、だいたい50名から55名ぐらいです。
法人は4つのミッションを掲げて活動してきました。まず、暴力の被害を受けている方たちが多いのでセーフティであることで、安全で安心を感じられる場を提供すること。それから、自分の抱える困難を人に知らせていくための言葉を獲得すること。さらに、社会の中で排除されがちな人たちなので、居場所を獲得できること。そして、今回の助成事業にも関わるのですが、私たちがサポートしている人たちの困難さを広く社会に知らせることです。
さて、今回の薬物依存を抱える女性のアドボカシーについてです。この事業は東京を拠点に行いたいと思っています。
私たちは2019年から24年までの5年間、女子刑務所の中でプログラムを矯正局から事業を受託して実施してきたのですが、違法薬物に対する国のスタンスは「ダメ、ゼッタイ。」政策で、出所後は就労すれば社会に包摂されて再犯を防止できると言われてきたわけですが、実際はそうは行かない。彼女たちが違法薬物を使った背景には、それを使わざるを得ないような環境的な要因がたくさんあって、そこにアプローチすることなく、ただ仕事をすることだけでは負のサイクルをブレークスルーすることができないという現実があります。
だから、罰を与えることなのではなく、必要なサポートを受けられるような受刑生活に変えていくことや、実際に出所後に塀の外が塀の中からの支援とつながるようなシステムを作っていくのが私たちの最終的に目指すところです。
なぜそれを東京でやるのかというと、札幌の女子刑務所の中でこのモデル事業を5年間やったのですけれども、薬物事犯で受刑している女性たちの半分は東京近郊の人たちだからです。全国に全部で10庁の女子刑務所がありますけれども、地元の方が地元の刑務所に入ったというよりは、むしろ東京や大阪に帰っていく人たちが圧倒的に多いので、東京で女性の出所者の食と住の支援を提供して、社会復帰の完遂を目指していくというのが今回の事業です。
まずは安全に住める場所。私たちは札幌で障害福祉サービスという形の支援をしているのですが、この5年間、刑務所の中で事業をやってみて、刑務所の中に収監されている薬物の問題を抱えた女性たちは見過ごされてきた障害があるのだけれども、彼女たち自身は自分たちが障害を持っているとはなかなか認識しません。そういった現実を踏まえて、今回の事業はビジネスモデルのスタイルでやっていきたいと考えています。当初は様々な助成金を獲得してランニングコストを出していきたいと思いますが、いずれはシェアハウスと就労機会という二つの事業で得られる収益で回していくのが私たちの目指すところです。
今申し上げたような事業をなぜやっていきたいのかということについて、この5年間の女子刑務所モデル事業を振り返るイベントを2月8日、成城大学をお借りして行う予定です。市民の方たちに、問題の存在と、私たちの事業のユニークさと目指すところをお伝えしていけたらいいなと思っています。
原子力資料情報室 高野聡さん) まだまだ薬物依存に対する偏見が強い中で、それを丁寧に解きほぐしていって、適切な支援を行うという非常に貴重で不可欠な事業だと感じました。基礎的なところでいくつか質問をしたいのですけれども、まず「ダメ、ゼッタイ。」というアプローチが間違っているというのは本当にそうだと思いますし、そういうアプローチでは効果がないというのは学術的にも証明されているところがあると思いますが、なぜ国はそういう問題のフレームに未だ固執しているのか。
あと、それと関連して、本来こういう事業は国や自治体と協力しながらやることも必要だと思うけれども、今のような問題のフレームだと協働していくことが難しい部分もあるのか、お聞かせください。
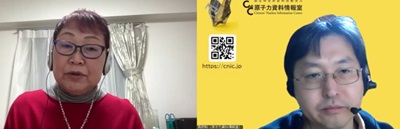
大嶋さん)「ダメ、ゼッタイ。」という政策を日本がやってきて、あまり上手くいっていないことは国もだんだん分かってはきている。世界の趨勢も、薬物政策に関して国際的に知見を集める機関があり、そこからも厳罰政策は決して上手くいっていないことはエビデンスとしても出ているところです。私も本当に、日本はなぜここまで「ダメ」に固執するのかというのはあると思います。
私は実は精神科医療で働いていた期間があり、そこで依存症の問題と出会ったのです。でも私は、依存症の専門病棟に配属されるまでは、これは個人の責任だと思っていた節があるのです。というのは、違法薬物の代表である覚醒剤という薬は精神的にかなり本人にダメージを与えますし、注射器を複数で使うことによってC型肝炎に罹患するリスクは確かにあるので、できるだけそういう薬物から離れていくことが望ましいというのは、私も理解できるからです。
「どうして『ダメ』と言われているものを使ってしまうのか」ということに、私はこの依存症病棟に配属された時に特に関心を持ったのです。 その背景をよく聞いていたみたところ、特に女性の薬物使用の背景にこれだけひどい暴力があることが分かった時に、私はものすごく誤解していたことが分かるわけです。それで、こういったことを国が知らないのかというと、国も全然わかっていないわけではない。そのことを一番よく知っているのは刑務所の職員だと思います。
一方、たくさんの薬物の問題を抱える海の向こう側の国の現状があります。日本の政府や国が恐れているのはそれと同じような状況になりはしないかというところだと思います。実際、アメリカでは違法薬物ではなく、合法薬物への依存が抜き差しならないところまで悪化してきています。合法薬物のオーバードーズ(過量服薬)によって、新型コロナウイルスの感染が拡大した時に亡くなった人数を超える死者が出ていることが大きな社会問題になっている。だから、日本政府や国は、女性が違法薬物を使う背景にたくさんの暴力があることを分かってきていて、厳罰政策が上手くいかないことに薄々気がついていながら大きな政策変更に今一歩踏み切れないのは、そういった先進国における深刻な薬物のオーバードーズの現状が少なからずあるのではないかと思っています。
今回の事業は違法薬物にフォーカスをしていますが、実は日本において違法薬物の使用者はだんだん減ってきています。刑務所に収監される女性の数は、私が刑務所の中で仕事を始めたのはちょうど10年前の2015年ですが、その時の数に比べると6割程度に下がってきています。では、今回の助成事業がだんだん必要なくなってくるのかと思いきや、一方で増えているのは合法薬物、具体的には若年女性の市販薬・処方薬のオーバードーズなのです。だから今回の事業はまず基本は強い偏見に晒されている違法薬物の女性をターゲットにしていくのですが、このアプローチは合法薬物の女性たちにも十分な効果があると私たちは思っています。
高野さん) この事業の特長は、支援の対象者を女性に絞っているところにあると思いました。女性なので、薬物依存だけでなく、何か複合的な差別も重なっていると思いました。男性の薬物依存の人とはまた違う特有の困難が女性にはあるのか。あったとしたら、それに対するどのような問題克服のアプローチをしようとしているのか、お聞かせください。
大嶋さん) これも重要な質問です。「ダメ、ゼッタイ。」政策と対になっているのが、「就労自立=リカバリー」という捉え方です。これが一定程度、男性の受刑体験のある方には効果があったというのですが、私たちがこれまでのフィールドワークや研究をフォローアップしていく中では、女性に関してはあまり上手くいってないと思います。なぜかと言うと、就労以前の問題がまずとても大きいということなのです。刑務所に入ると大体の方は仮出所という形で何ヶ月か早く刑務所から出るということで、その時に身元引受人が必要なのです。
ところが、この身元引受人が少なからず薬物つながりの方であることが多い。配偶者が薬物依存者であるとか、収監されている女性にとっては暴力の加害者であることが少なくないのです。だからその人を身元引受人にすることは、またそこで暴力が再現されることになる。彼女たちが覚せい剤のような強い作用の薬物を使用する時には、殴られたりする痛みを消してくれる効果が覚せい剤にあったり、恐怖に体がすくんでしまうような状況を乗り越えさせてくれる、怖くなくなる効果が覚せい剤にあると言われているのです。ですから、安全な帰住先をなかなか彼女たちが選べない、選ばない現実がある。
私たちが「そこは安全じゃないように見える」というふうに言葉を駆使して伝えても、「私にはそこしか帰るところがないんです」というような語りに出会うことも少なくない。あるいは「今は大丈夫」と言う。でも、私たちは実際に塀の外でも支援してみて、やはり大丈夫ではないのです。その時に、障害福祉サービスという枠組みだと手続きで行政窓口に行かないといけないとか、住民票はどこに設定してあるとか、いくつものハードルを越えないといけない。
今回の事業では、「今日行きたい」と言った時に今日泊まる場所がある。そこには安全に彼女がいられるようにスタッフがいて、専門的な知識を持った援助職の人や、同じ薬物依存をくぐり抜けてきて今は薬物を使っていないピアスタッフと呼ばれる人たちの配置を考えています。
女性の支援は男性の支援に比べて、背景にある暴力被害が多く、そのトラウマ体験をどう乗り越えていけるのかという問題や、就労したとしてもご承知のように非正規雇用の割合が多いという問題がある。これは女性の薬物依存に限ったことではなくて、シングル女性の非正規雇用による貧困の問題は今の日本における大きな問題でもあるのです。
加えて、小さな町のご出身でそこに帰る場合、先ほどの高野さんのご発表にもありましたけれども、地域が彼女に向ける眼差しが非常に厳しいですから、どうしても都会に流入してくる。それが東京や大阪であったりするので、私たちの活動拠点はこれまで札幌だったのですが、今回の刑務所のモデル事業を引き受けたことで、東京にオフィスを構えたのです。これをテコにして、東京をベースとした働く場所と安全に泊まれる場所、暮らせる場所、そこから定住地を設定していくというようなスポット的な場所をやっていきたいというのが今回のポイントだと思っています。
高野さん) シェアハウスで住宅を確保して、就労支援で働いて、そのサイクルがうまく回れば本当にいいと思いますし、そう願っています。一方で、その人たちは地域のコミュニティの中でも生きることが必要だと思いますが、私が聞いたところでは、やはりまだ、例えば自助グループで有名なダルクが地域のコミュニティの中で受け入れられないだとか、出ていけみたいな張り紙がまだあるという事例もありました。そういうコミュニティの中での共生という形でのアプローチは何か考えていらっしゃるでしょうか。
大嶋さん) そうです。それがスティグマの解消にまさにつながるのですが、正直難しいところはあります。合法薬物であっても、例えば代表的な合法薬物であるアルコールであっても、まだまだスティグマがあって、男性のアルコホリックは嫌がられますけど、女性のアルコホリックはさらに嫌がられる。
でも、若年層のオーバードーズに関しては、なぜ彼女たちがそんなふうに市販薬をオーバードーズしなくてはいけないのか、ここら辺が突破口となっていく可能性はあるかもしれません。安全を保ちながら例えばマスメディアに露出していくようなアプローチも必要なのですが、その時にダルクのように狙い撃ちされるという難しさは確かにあります。 そのリスクとどういうふうにバランス取っていくのかが、私たちのこれからのチャレンジかなと思っています。
――全体対話――
大嶋栄子さん) 先ほどからの高野さんのご発表を、私も北海道なので非常に関心を持って伺っています。地域の分断が相当ひどいところまで行っていることが本当によくわかって、そういうふうに仕掛けられてしまうということに対して、そのことを知る機会が少ないということもあるのですが、高野さんはどのあたりが突破口になるとお考えですか。
高野聡さん) 国による問題の提示の仕方は、「私たちが原発を使ってきたので、そのゴミを私たちの世代で解決して、後の世代に引き継がせない」というような形で、「それが私たちの責任だ」というように言っていて、なんとなくまともに聞こえてしまう。だけれども実際やっていることは、お金で地域を釣るというような非常に不公正なやり方でアプローチしています。
もう少し生々しい話で言うと、事業者のNUMOという電力会社に似たような組織があって、そこが地域住民に密かにアプローチをかけて、視察見学のように称して住民をいろんな所に連れていくのです。そういうやり口の汚さをみんなにも知ってもらって、仮に核のゴミの処分地となることが必要だというような人に対しても、今のような進め方の問題を提起する形でアプローチしたい。
もう一つは、地域の分断。地域の中でも、もう少し視野を広げてもらえればと思っています。政策の構造そのものがおかしいから賛成・反対で今いがみ合っているけど、どちらも政策の被害者であり、もう今は当事者も地域社会で生きづらくなっていと感じているところなので、本来あるべき地域のまちづくりの在り方から対話の切り口を見出せないかと思っています。既に分断が起こっているところにどうやってアプローチするかは本当に悩ましいところではあります。
分断を超えた共生
土屋真美子さん) 今回の助成公募の特別テーマとして、「分断を超えた共生」いうのがあって、言葉で言うのは簡単ですけど、どう共生していくのかが本当に難しいということで、最初の上村英明運営委員長の話にも、いろんな形で分断が仕掛けられているとあったので、どう突破口を開いていくのかに関して、ご意見があればぜひどうぞ。
中島伽耶子さん) 地震のあった石川県の端にある珠洲市で芸術祭をやっていたというご縁もあって、最近ずっと1ヶ月に1回ぐらい訪問して、知り合いに挨拶に行ったりしています。この珠洲市は小さな地域ですけど、かつて原発誘致の問題でまちが二分してしまいました。結局、設置はされなかったけれど、その分断だけが残ってしまって、未だにちょっとした言葉の端々に賛成派だったとかいう話が出てきて、分断してしまった後のイメージがすごく強いので、分断が一度起こってしまうと長いスパンで続いてしまうということを身にしみて感じています。
狭いコミュニティだからこそ、そこに居られなくなってしまって都会に行ってしまう。トランスジェンダーの問題で言っても、SNS上で本当ではないことで悪意のあるデマによってイメージが先に作られてしまっていて、「当事者」と呼ばれる人に会う前にイメージが多くの人に作られてしまうからこそ、意図的に分断が作られているという状況があるので、悩みながらもいろいろな方法を試していきたいとは思っております。
高野さん) 永井さんへの質問です。「分断」と言ったら、イスラエルとパレスチナは歴史的にも価値観の違いやお互いの憎悪が見られて、すごい分断なのかなと思うけれども、イスラエルの人とパレスチナの人の和解のプログラムやプロジェクトはあったのか、何かグッドプラクティスがあれば教えていただきたいと思います。
永井陽右さん) 我々の活動はパレスチナでは去年からですが、他の紛争地、ソマリアでもイエメンでもコロンビアでも、いろんなところで仕事をしています。離脱した戦闘員、投降兵や捕虜、受刑者も社会に出た後に紛争が終わっていないケースだと学術的にも理論的にも社会復帰や和解は難しいのですが、なかなか和平合意を結べない難しい紛争地もある中で試行錯誤はしてきました。
例えばAとBとCが分断して対立しているとしたら、各々あまり他の人のことを分かっていないですし、自分自身のグループのこともあまり分かっていなかったりするけれども、前提として、良い・悪いではなく、人の差異を受け止める、その存在を許す、そこから立ち上げなければ何も生まれないというのは、この仕事を現場でやってきて思うことです。
我々はこの社会に起きている分断を語る時、わかりやすいトピックが前面に出てくるわけです。原発だったら、原発いいねと思う人と微妙だねと思う人たち、という構図はわかりやすい。でも、そこだけではないところに目を当てていって、とかく自分にとって頓珍漢な意見や悪魔と思える人の意見であっても、その存在を許す、認める。そういうのは一つ大事だと思います。そこが意外とそもそも無いのが、対立や紛争や分断の話ではすごく多いのです。
特に、日本も含めてですけど、SNSの空間は本当に過激で、「SNSは人類にまだ早かったな」と自分はいろんなところで言っています。やはり操られて、心が揺れ動いてしまうので、自覚的に向き合わないといけないと思います。なので、分断がすごくあるからこそ分断だけに目を向けない。分断が本当にない世界なんて本当にあるのかなと若干思ってもいるので、分断との向き合い方もまた一つ大事だと思います。
土屋さん) どう向き合うかですね。
永井さん) 自分は、いわゆるテロリストと呼ばれる人や、安保理的に国際法的にテロ組織に指定されているような方々がメインで、彼ら彼女らは一般的には社会・国際平和・安全の脅威という理解ですので、その脅威をどうコントロールしてゼロに近づけるかという発想なのですが、自分からするとすごくもったいないと思うのです。社会科学的な問題解決としてあまり上手くいかないというのもあるけれども、そもそも人間であって、結構若い奴がいるのだったら、そこに可能性はきっとあるはずだと思うわけです。自分にとって圧倒的他者と思えるような人との間に何を見いだせるか、より前向きな能動的な姿勢で何を生み出せるか、答えはないけど、ここに可能性があるのではないかと一緒に見る方が前向きだなと思います。
高野さん) 本当にその通りですし、寿都町の問題にもつながる部分があると思ったのは、お互い希望のある将来を共有できるところがすごく重要なのかなと感じています。今の寿都は核ごみで賛成・反対で別れてしまっている部分もあと思うけれども、お互い明るくて希望のある将来に向かっていきたいというのは絶対に共有できると思うので。
私が寿都の人たちで印象的だったのは、こういう問題が起こることによって「今まで町長に任せっきりだった」、「もっと私たちが主体的にまちづくり関わっていかないといけなかった」と後悔していたことです。
最近は「未来世代法」という概念があって、政策の立案段階でそれが地域社会の未来世代にどれだけ影響を与えるのかを多角的に検証して、経済だけでなく環境面、地域のアイデンティティを健全に強化するかという文化的な面、不平等を解消するか等の社会的公正の部分など、多角的に見ながら政策立案をするという考えです。その専門家を寿都の人たちが知って、「今必要なのは、これだと気づいた」と言っていたのです。
「より幅広い価値で、経済だけではないいろんな物差しで見ながら、どういう形で寿都の将来を共有できるかといったところからアプローチして、話し合っていく中で、核ゴミに頼る形ではない方がいいと共有できるのではないか」というようなことを寿都の人から聞いたことがあるのです。まだ具体的なプロジェクトにはなっていないけれども。
そういう将来を共有するところからアプローチを探せるのではないかと、永井さんのお話を聞いて感じました。
土屋さん)希望のある将来をどうやって共有するかが大事だと気がついた方たちがいるというのは、とても希望が持てる話だと思います。一方で、先ほどの中島さんの話でショックだったのが、原発は結局建設されなかったのに分断だけが残されたという話で、そういう話も結構あるのだろうと思います。本当は分断は無いほうが絶対いいわけですけれども、そういうふうに作られてしまう部分もあるとは思いました。
きりしまにほんごきょうしつは、その辺の狭間にいる感じがしますが、いかがでしょうか?
本田佐也佳さん) 私が本当に恐れているのは、分断が起きてからではどうしようもないということです。「どうしてケアが前もってできたのに、なぜしなかったんだ」と後悔する。私はもうそのビジョンが見えているからこそ行政にも地域にも働きかけるのですけど、どこも他人事になっていて、「あそこで起きたことが、うちで起きるとは限らない」とか、「こんなに小さい街だから現場が頑張れる」とか言う。その現場に押し付けている事実を棚上げして、先送りにする姿勢が随所に見られる。
私は一生懸命ボトムアップを図ろうとしたけど、田舎独特のことなのか、トップダウンだとものすごい勢いで進むのにボトムアップしようとするとすごく遅くて、誰も交渉のテーブルについてくれない。でも両方が必要だと私は思っていて、この2年間ずっと地域の人たちや市役所に日参して話していたら、「外国人向けに優しい日本語の職員研修をお願いします」と、やっと実現に漕ぎ着けて1回目を開催できたということもありました。
でも分断があると思うのは、「外国人ばっかり、ずるい」が絶対にあるのです。その「ずるい」とか「不公平」という気持ちが根底に生まれるのは自分に余裕がない時だから、外国人がいることが原因ではないということにまで目が向けられない社会全体の構造があるだろうと思います。「どうして外国人の子どもに日本語を学校の後で塾のように教える予算を取るのか」とクレームが入るわけです。「その分、日本人に教える予算を割けばいいじゃないか」というけれども、今、教員の成り手が本当にいなくて、発達障害の子も職員が足りないから先生が一人で見ている中に、日本語さえも通じない、習慣も全然違うところから来た子も一緒に見てねとなれば、教員になりたい人はさらに減っていく。そこでも、「あんな子が来たから」というふうな職員内の分断が生まれる。
外国人たちは日本語ができないだけで、母国語が話せる地域では自分の力をきちんと発揮していたわけだから、日本語という道具を手に入れられれば、もっと力を発揮できて、新しくその国々から来た人たちのサポートもリーダーとしてできるし、先生も職員の方もPTAのみんなも楽になるのだから、もっとみんなWin-Winになる方法を考えようと働きかけています。でも、「いや、まだいいです」とか言われて、「今やっておかないと、いざ来たら、間に合わないですよ」と言っても、「いや、来た時でいいです」と言う。この危機感のズレを感じています。
無理解や無知は恐怖心を増すので、啓発やアドボカシーが必要になってくると思っているところです。
分断を煽るSNSに対して自覚的に理性的に
永井さん) SNSのところは、やっぱりあるなと、今、話を聞いていても思いました。その分断を煽る人がいるわけです。いくつか研究もやりましたけれど、なぜ煽るかというと、最近見ていて思うのは、金になるわけです。ヘイトをやったり、分断を煽ったりするのは、社会心理学的にもアドレナリンが出がちなので気持ちいいわけです。悪を暴くみたいな。そしてそれは金にもなるのでみんなやるわけですね。SNSもTikTokも YouTubeも。
そうしたところに乗っからない。究極、オートマティックに出てしまう我々の情動的なところをいかに理性的にコントロールできるか。決して金儲けさせないというのは、社会全体としてもっと意識していかなければいけないとすごく思います。
本田さんがおっしゃっていたWin-Winになったほうがいいというのも、他人が良くなるぐらいなら自分も他人も良くならないほうがいいと思う人は意外とたくさんいる。この病んだ日本社会には。それはなぜかと考えると、例えば中高生が整形したいというのとつながるとも思うわけで、つまり比較対象がありすぎるわけです。SNSにみんないい面しか出さないじゃないですか。加工して。それと常に自分を比較してしまって、「他人のほうがいい思いしてる」とか「他人のほうが可愛い」とかで「そんな自分はダメだ」と。
やはりSNSは人類に早かったのですよね。なので、SNSに対して自覚的に理性的に、というのは大事な気がします。
高野さん) ここまでSNSが普及してしまって、アルゴリズムによって私たちの感情がある程度操られてしまう中で、大きな解決策はなかなか難しいとなると絶望的な気持ちにもなってしまうので。僕は韓国に10年ぐらい住んでいたのです。そうすると友達もたくさんいるし、韓国社会のいい面と悪い面もいろいろ見られたりして、 それが面白いのです。いろんな人たちと会う経験をすると、今のマスコミに流れている韓国社会のイメージは明らかに偏っているのがよく分かるのですが、SNSだけだとそこら辺がどうしても分からない人が多くなってしまうと思うのです。
なので、どうやってもっといろんな友達をたくさん作って、自分の中できちんと参照する軸をどれだけ作れるかが重要なのかなと思うのです。いろいろSNSで流布されている情報の薄っぺらさに気づけるように、個人が免疫を上げるのが必要だと思うし、そういう場をどれだけ提供できるかも鍵かなと思いました。
先程、中島さんもアートでいろんな場を作るという話があり、そういう場をもっとたくさん作って、出会えて、 自分がきちんと知っている人から物事を判断するということが広がっていけばいいなと思いました。
本田さん) 今、高野さんがおっしゃったことが私の活動の中で起きました。まさにTikTokやYouTubeのショート動画でヘイト動画ばかり見ていた人がいて、中国に対して「そういう人たちなんだ」と思っていたと。私たちは月に1回、地域の外国人と住民の方が日本語で交流する「カンバセーションナイト」を開いていて、その人がそこに来てくれるようになって、日本に長く住んでいて日本語も中国語も堪能な方と会話をすることで、自分の凝り固まっていたイメージが一掃されたそうです。
対話を通してしか変えられないものがある。SNSでずっと見ていたものを信じたいというのがあると思うけれど、それを払拭するためには、本人と会話ができるという衝撃がないとこんなに難しいのかと思いました。でも、その変わってくれた方はうちのスタッフになってくれたぐらい、この活動には可能性がある。SNSから受けて自分が持っていたイメージと一人ひとりは違うということを他の人にもっと分かってほしいという繋がりになったので。高野さんがおっしゃったようにいろんな場を設けて、彼らと地域の方々が接して、それまでイメージしていたのと違うというのが分かるような場が日本全体に広がっていけばいいなと思います。
中島さん) そこにすごく希望があると思うし、他の団体の方も対話の重要性については度々お話しされていたと思います。
でも同時に、対話しなければ本当に私たちは連帯や協力ができないの? と思ってしまうのです。トランスジェンダーの問題で言えば、数が少ないことによって、実際に会話できる可能性や頻度が少なくなってしまうことが起こる。じゃあ単純に、対話の数が相対的に少ないから連帯ができないというのはあまりにも貧しい。私たちは、対話だけではないはずだと思うのです。想像力や、イメージを変えていく力は対話だけではなく他の力も信じたいと思っています。なので、確かにSNSは人類には早すぎましたけど、同時に、地域にいられなかったけどSNSがあったからこそ生きていけたという人も確かにいるわけで、両方を見ていきたいと思います。
あと、性的マイノリティの人たちの貧困率は、女性の貧困率もそうですけど、同じように本当に深刻な問題で、しかも性的マイノリティであり、外国籍ルーツの人はさらに困難な状況に置かれてしまう。そういう状況の人は、何かしらの依存症になりやすいし、ホームレスの状態にもなりやすい。重層的なものがあって、何か一つだけに目を向けることが難しい。どれもつながってくるなと、リカバリーの大島さんのお話を聞きながら頷いていました。大島さんのお話を聞きたいです。
大嶋さん) 北海道札幌市でCloudyというコンソーシアム、10個ぐらいのNPOが集まって困難を抱える女性に月に1回、相談と食事を届けるという活動を2020年から始めています。そこでは、女性はシス女性が圧倒的に多いですけど、マイノリティの人も結構いらっしゃいます。
インターセクショナリティという言葉がありますけど、ジェンダーの問題だけでなく民族や思想などいくつもの視点によって組み込まれていくような形で起こってくる困難があって、その絡まったものをどうやってほどいていくかというところは、今日の皆さんの話に共通していたと思います。助成事業の内容はバリエーションがありますし、非常に国際的なものから非常にローカルなものまで幅広いと思ったけど、通底しているものがあるとお話を聞いていて思いました。
参加者) 大嶋栄子さんにお聞きしたいです。人と人の分断、個人中での分裂、分割に対して、「食と自然」をひとつのテーマに置いて工夫されている実践から、その意義や変化をおきかせください。
現場はものすごくシビアだけどポジティブである
大嶋さん) 私もけっこうシビアな領域で長いことやっていて、どうしてシビアな領域で続けてこられたのかって自分で自分に問い返した時に、現場はものすごくシビアだけど、私自身はどこか楽観的なのです。それを今日、永井さんの話に確認できて、永井さんもすごくシビアだけど、永井さん自身はどこか楽観的だなと思います。
どうして楽観的かというと、やるしかないからです。気がついてしまったから、やるしかないというのと、やるからには自分を下手に追い込まないほうが長く続けられていいからです。じゃあどういうふうに自分を楽観的に切り替えていくかっていう時に、すごく大きな力になったのが食べることだったのです。その食べることは、心のバランスを崩した時に真っ先にどうでもよくなることだし、貧困な状態に置かれるとエッセンシャルなのに真っ先に保てなくなる部分なのです。
だから、人間の尊厳を守るときに食べ物から入っていくのは大事だし、非常に緊張状態にある関係で、のるか反るかという交渉を相手とする時に、もし共に食べることができると、そこが突破口になることが結構あるのです。それで私たちは6、7年前から農園をやっていて、自分たちで食べるものを自分たちで作りました。
それは、中島さんが言っていたように、言葉にならない人がいっぱいいるからなのです。私たちの団体はアートにも力を入れているけど、同時にアートという表現方法がフィットしない人もいて、そういう場合にいくつかの方法として農業に携わることをやっています。そこで確実に収穫されていったり、収穫直前で大雨が来て何だよということもあったり、地球温暖化をモロに感じて北海道でサツマイモが採れる体験もしたりしています。そういう中で確かな手応えと、私たちの星がだんだんヤバくなっていると日常的に感じることを共有しながら乗り切っていくところがあります。
だからカフェもやっていて、せっかく作ったもので美味しいご飯を作って、みんなで食べる。そのご飯は最初からみんな美味しいと食べるわけではなく、心を病んだりひどい暴力の中で生きてきた人は、人がつくったご飯を信じないでファストフードのほうを信じたり、ポテトチップスの方が絶対だったりするのです。彼女たちがポテトチップスやコカコーラやジャンクフードを手放して、人が手をかけたご飯を食べて、そこに何かを感じられる瞬間が来た時に、私たちは一緒にやっていて良かったなと思うのです。
使えるものは何でも使うというのと、現場はものすごくシビアだけどポジティブであるというのが、私たちは大事かなと今日改めて思いました。
土屋さん)最後にまとめのようなお話、ありがとうございます。そろそろ時間ですので、最後に一人一言ずつ、できれば今の大島さんの「ポジティブで」という話に引っ掛けていただければいいなと思っています。
高野さん) 「楽観的になる」というのは心の持ちようだけでなく、長くやっていると楽観的になれるような、希望を感じるような瞬間が、皆さんにも多分あると思うのです。本当に地域の分断が起こってしまったけれども、未来世代法という先端的なまちづくりの考え方に触れて、すぐにその人たちは反応できるのです。2千7百人ぐらいの町ですけれども、そういう反応が見られると、民主主義の可能性も感じました。
なので、活動をしていて何か苦しい中でも楽観的に感じられるエピソードを横断的に共有できる場があるといいのかなと思いましたし、今日はそういう場でもあるかなと思います。ソーシャル・ジャスティス基金さんにも頑張ってそういう場を用意していただければありがたいなと思いました。
中島さん) 今日皆さんの話が聞けてすごく勉強になったし希望が感じられていい気持ちになりました。やはり前々から思っていたけど、問題はつながっていくし、芋づる式になっていくと改めて実感できました。
最後の大島さんのお話にもありましたけど、trunkは6人ぐらいでしかやってないのですが、みんなが楽しめる方法を探している。楽しめないのであれば続かないので、最初から無理はしないというようなことをモットーにやっているので、楽観的であることや楽しむことがシビアであればあるほど大切だと改めて思いました。
永井さん) 私も大変勉強になり、よかったなあと思っています。
紛争地のプロの現場でも「悲観的に準備して、楽観的に実行せよ」なんてよく言うので、ワースト・シナリオでいろいろ準備していますけど、やるときはもう楽観的にやって、そのメンタリティーは普遍的に通じるのだなと思いました。
いわゆるテロリストと指定されたりレッテルを貼られたりしている方々とメインにやり取りをしていると、みなさんテロリストは怖いとか悪魔だとかヤバい奴だとなるけど、本当にエイリアンだったら話は別ですけど、「どこまでいっても高々人間だな」と自分は思っていて、人間である限り、いろんな可能性があって、いろんなやり方があるというのは事実だし、かつ楽観的に考えていて、「せいぜい人間だし」ぐらいの感覚も懐に入れておくと、もっといろんなことを試せる気もすると思いました。
先程中島さんがおっしゃっていた「人間というのは対話しなきゃ、できないんですか」というのは、その通りだなと思って。人間だからこそもっとできることはあると思うのです。会ったこともない地球の裏側にいる人間に想起できるかとか。そういう人間の可能性にもっと光を当てて、前向きに捉えていきたいですね。何事も問題は解決できると思いますので、そんな形で市民社会からグッとやっていければいいのかなといます。ありがとうございました。
本田さん) 私も勉強させていただいて、同時に勇気をもらって、頑張っていこうという気持ちになることができました。
分断が起きる前に、もう少しずつ起きているけれども、それから目をそらさずにいろんな方法で関わっていきたいなと思っています。一方で、私も自分が代表を務める中で、必ず皆さんに「自分のプライベートを一番にしてください」とお伝えしています。私も子育てをしているので、自分自身が子どもと家族との時間を大切にしながら、そしてそのことの幸せがみんなに平等に渡ったらいいなという思いがあります。出稼ぎに来ている人たちがたくさんいますので、そういう彼らの気持ちを分かり、みんなとシェアできる居場所となれるようにと考えています。
私もネガティブにばかりを見ているわけでは決してなくて、必ず解決できるはずという希望を持って活動をしているので、ここで皆さんとそういう思いを共有できたことが本当に嬉しいです。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
――閉会挨拶――
佐々木貴子さん・SJF運営委員) 皆さんが本当に希望を感じられながら、次の活動に向かいたいとおっしゃっていて、ここに参加された方たちがお互いに対話交流ができたこと、すごく嬉しいです。

どなたもおっしゃっていたけれども、市民自身の自治や自発、市民社会にもっと希望を持ち続けることの大切さ。そういう場も提供していきたい。皆さんが今活動されていることには通底するものがあるということだと思うのです。社会の深いところにある課題は共通するものが多い。でも、そこに市民ならではの希望を持ちながら対処していきたいと私も強く思うことができました。本当にありがとうございました。これからの活動をすごく楽しみにしております。 ■
●次回のSJFアドボカシーカフェご案内★参加者募集★
『摂食障害に影響をうける人がしなやかに生きられる社会とは―当事者の声から考える―』
【日時】2025年3月8日(土)13:30~16:00
【会場】オンライン開催
【詳細・お申込み】こちらから
*** 今回2025年1月25日の企画ご案内はこちら(ご参考)***

