ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第94回開催報告
パレスチナの和平構築
―紛争当事者の若者が主導する対話から―
2025年9月27日、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)は、永井陽右さん(NPO法人アクセプト・インターナショナル代表理事)、Batoolさん(東エルサレムを拠点に教育イノベーションプログラムを展開するパレスチナ人市民社会リーダー。パレスチナの若者が課題解決に主体的に関わることを後押ししている)、Asselさん(ヨルダン川西岸地区でコンピューター工学を学ぶパレスチナ人学生。若者やパレスチナ問題に関する活動を行っている)をゲストに迎えてSJFアドボカシーカフェを開催しました。
分断され戦争が続くパレスチナで、市民が政治に関われない状況を変え、和平への新たなプロセスを構築するために若者主導の対話が続いています。なぜ、大量殺戮が起きている今まさに対話をすべきなのか、と永井さんは発題しました。Batoolさんは、パレスチナの人々自身が結束しなければパレスチナの未来はないと今回の事態によって突き付けられ、政治的な主体者として若者同士が対話で信頼を築き、市民の信頼を得られる政府に変えていくことが重要だとの考えを示しました。Asselさんは、機能不全となっている政府を、市民の声に応えられる政府、説明責任を果たせる政府に変えていく意味でも対話する必要性があると指摘しました。
NPO法人アクセプト・インターナショナルは、パレスチナの若きリーダーたちの可能性を信じ、パレスチナの人たち自身が新たな和平構築プロセスを見出すことを支えています。オスロ合意の失敗を繰り返さないよう、新しい和平プロセスを構築するために、パレスチナの主要政党・組織や市民社会を代表する若者・女性たちを中心とした包括的な対話によって、パレスチナの人々の結束に向けた取り組みを進めています。戦後80年の節目となった今年8月にはパレスチナの多様な若者を第三国である日本の広島・東京に招いて対話会合を持ち、「東京宣言」と具体的な「アクションプラン」を作成しました。
その日本での対話会合で、パレスチナでは出会い得なかった国内外で暮らすパレスチナの若者が集え、強い連携が生まれ、団結して困難を乗り越えていくビジョンと希望が共有できたとAsselさんとBatoolさんは語りました。パレスチナの未来をつくる主体は、党派を超えて連携した若者たちであることを世界に示していく責任を自覚したといいます。
新しい和平プロセスを構築するために私たちは何をすべきか、との永井さんの問いかけに対して、パレスチナが占領されている実態や若者の声を記録して共有し、メディアを活用したアドボカシーによって団結に向けた変革を起こしたいとAsselさん。正当な選挙によって適切な政府をつくることがパレスチナの未来をつくる鍵だとBatoolさん。そうした団結や選挙が成功するために国際社会が協力して保障することを永井さんは展望しました。
詳しくは以下をご覧ください。 ※コーディネーターは寺中誠さん(SJF企画委員)。
 (写真=上左から時計回りで、Asselさん、永井陽右さん、寺中誠さん、Batoolさん)
(写真=上左から時計回りで、Asselさん、永井陽右さん、寺中誠さん、Batoolさん)
目次
——永井陽右さんのお話:「パレスチナにおける私たちの取り組み~新たな和平プロセスの構築~」——
私たちアクセプト・インターナショナルは、日本生まれのNPO法人です。元々は、2011年頃、私が大学1年の時に立ち上げた団体で、ちょうど昨日(9月26日)に14周年を迎えました。
ソマリアやイエメンなどの紛争地域で長らく活動しており、最近はパレスチナやコロンビアでも仕事をしています。人道支援に加えて、いわゆるテロ組織と指定されるような組織も含め非政府武装勢力の戦闘員を受け入れて――これが「アクセプト」という英単語ですけれども――、彼ら彼女らの社会復帰支援などの取り組みを軸に、和解や和平の支援も行っている非常に珍しい組織です。
近年は、そうした現場の仕事に加えて、国際法の制定に向けても尽力をしております。そのため、最近は紛争地の最前線に加えて、ニューヨークやジュネーブなど国際政治・国際法の最前線でも仕事をしています。
パーパスは、「誰しもが、平和の担い手となり、憎しみの連鎖をほどいていく」です。我々の仕事は紛争解決やテロの解決などの分野ですが、本質的に貫かれていることは「憎しみの連鎖をほどく」取り組みです。まずは若者や子どもたちが過激化するのを防ぐこと。さらに力を入れていることは、テロ組織を含む武装勢力に今いる若者たちが武器を置いて投降や離脱ができるような取り組みです。必要があれば、武装勢力側と交渉して、どうにか離脱できるようにすることもやっています。さらにワンストップで脱過激化や社会復帰の取り組みも行なっています。
「憎しみの連鎖をほどく」という視座から考えるのであれば、被害者や犠牲者の方々への支援もなおざりにできません。そこで緊急人道支援や、和解・和平に向けた取り組みという形で支援をしています。
こうした、加害者とされるような方々への取り組みや、被害者とされるような方々への取り組み、そして地域への取り組みをさらに強化し高めていくための国際政策やアカデミアへの還元、ひいては国際規範の制定まで包括して行うことで、日本から、憎しみの連鎖を少しずつほどいていく仕事を皆様と共にさせていただいております。
なぜ我々がこうした非常に珍しい仕事に並み並みならぬ情熱を注いでいるかといいますと、皆様と同じように、少しでもこの世界が良くなればと願っているからです。日本にも世界にも様々な問題が存在していて、それらをつぶさに分析していくと、武力紛争やテロリズムが非常に多くの問題の原因になっているし、結果にもなっている。そうした問題群が連鎖していくことによって、紛争やテロは増加するし、それに伴いさらなる問題も発生しています。
例えば、現在世界には難民が1億人以上いると言われており、今なお増え続けています。この難民問題に取り組んでいる組織や人はたくさんいて素晴らしいことです。ただ、難民の発生原因は何かと考えると、武力紛争が圧倒的に多いのが現状です。したがって、武力紛争を解決していくようなアプローチをとらなければ難民はさらに増えていくでしょう。
しかし、こうした問題の解決は確かなニーズがある一方で、やり手がいません。なぜならお金がかかるし、危険も伴うし、問題のセンシティブさゆえに寄付が集まりにくいからです。また、武力紛争の性質上、政府開発援助(ODA)やソーシャル・ビジネスのようなアプローチも有効とは言えず、日本からの物理的・心理的距離もあり、正解が書かれた教科書もありません。
だから、我々が日本から前例をつくる。これが私たちの存在意義であり、一番大きな根幹をなしています。
我々の仕事は日本から生まれた新たな紛争解決のアプローチとして最近は世界的にも非常に評価を受け始めています。
分断されたパレスチナ 政治に関われない市民
我々がパレスチナ問題に取り組み始めてもう1年強が経ちます。きっかけは2023年10月7日でした。ハマスやイスラム聖戦などによるイスラエルに対する奇襲攻撃があったということで、それを受けてジェノサイドと言われるものがずっと起きています。これまでに6.5万人が命を落とし、瓦礫の下ではさらに1万人ぐらい亡くなっているのではないかという話ですから、まごうことなきジェノサイドです。ちょうど今、国連総会ハイレベルウィークがニューヨークで開催されていて、米国のトランプ大統領やイスラエルのネタニヤフ首相が物議をかもす発言をしています。
こうした非常に深刻な国際情勢の中で、我々として何をするべきかというのをずっと考え、かつ行動してきました。我々は人道支援に特化した団体ではなく、紛争解決と平和構築を専門とする組織です。もちろん人道支援は必要で、現在もガザで行っていますが、同時に長期的なパレスチナ和平に向けた取り組みを行っています。それは、我々は誰にアプローチするか、私たちだからこそできることは何かということがポイントでした。
国際社会では「パレスチナ国家承認」という波が来ており、承認するかわりに「ハマスは国家の統治に関与しないこと」という条件を出す国もかなり多く、パレスチナ自治政府も言っていますが、ハマスはハマスで理解できることはあるわけです。ハマスをテロ組織と指定している国がありますが、広範なパレスチナ市民から一定の支持を集めていて、以前に選挙を行った時は勝っていた組織でもあるのです。すなわち、いわゆるイスラム国やアル・カイーダといった現代的な過激主義組織とは異なっているわけです。彼らは抵抗運動であり、軍事部門だけではなく政治部門や社会福祉部門があり、後者はまさにガザの行政を一手に担ってきました。ですので、ハマスはテロリストだというのは、果たしてどこまで正しいのか、その先に何があるのだろうかと我々は考えるわけです。
そのようにパレスチナはずっと分断しています。ヨルダン川西岸地区にパレスチナ自治政府があり、そこから離れたところにガザ地区があります。そもそも、この地理的に無理があるというのも指摘されてきた歴史があります。ガザ地区とヨルダン川西岸地区は行き来できないのです。
このヨルダン川西岸地区は与党のファタハが統治していて、非常に腐敗しているという国際的な批判が長らくあります。一方でガザの方はハマスが実効支配していますが、元々2006年にハマスがパレスチナの選挙に勝って入閣していましたし、首相の座にも就いていました。ところが、国際社会、特に欧米諸国からイスラム組織に対する疑問符がついて退陣していき、それ以降分断が激しくなってしまいました。その後今日まで選挙は行われておりません。今のパレスチナ自治政府から発令されるのは全て大統領令です。
そうした状況ですので、民主主義とは何だったのか、市民の声はどこへいったのか、といったことが非常に問題になってきたわけです。アッバス議長は、昨日・一昨日と国連総会でビデオメッセージを発表していましたが、おそらく死ぬまで議長で、死ぬまでパレスチナ自治政府大統領でしょうと、パレスチナ人の方々も言っているぐらいで、そうした難しさがあるわけです。このように、パレスチナ自体が政治的にも非常に深く分断されている、かつ、市民レベルで見れば、市民は政治に関わることができないことにより極めて難しい状態が続いていました。
ちなみに、ハマスについて23年10月7日以降、定期的にアンケートが行われていますが、ハマスに対する支持は今もあることがわかります。ヨルダン川西岸地区でこのアンケートをとってもハマスの影響力はなかなか強いのです。それは、これまで批判され続けていた与党ファタハへの反発の裏返しみたいなところもあるでしょうが、各国が「ハマスは認めない」と言っても、ハマスはそこにいるわけですし、ハマスを支持する方々もたくさんいます。
長期的な和平プロセスのために 排除されてきたような人も組み込んだ包括的な対話で団結へ
パレスチナの若きリーダーたちの可能性を信じて 現地の人自身が見出す解決策を支える
では、どのようにして正当な選挙を行うか。長年「選挙を行う」と言われてきましたが、実際には行われてきませんでした。和平を考えると、それをどう実現していくかが課題になってきます。
我々は北部ガザで給水活動をしています。海水を淡水化して毎日とにかく届けるこの活動は、全てご寄付によって賄われています。助成金や補助金はありません。しかし、できる人がやるというところで、ガザの人々に清潔な飲み水を届けています。
これに加えて、パレスチナの団結のために包括的な対話のプロセスをつくり、長期的な和平に向けたプロセスを作っていくために様々動いております。今回、日本における対話会合を開催するにあたり、一部はソーシャル・ジャスティス基金から温かな助成を受け、今年の8月に広島と東京で実際に14名のパレスチナ人若手リーダーたちを招いて、ハイレベルな方々も交えて一日中続く議論と対話を経て最終的にパレスチナ和平に向けた「東京宣言」と「アクションプラン」を採択することができました。若手リーダーたちは、パレスチナの主要政党や組織、市民社会から参加をしました。本日これからお話しするBatoolさんとAsselさんも参加してくれました。
我々だからこそ、そうした政党や組織、市民や国との交渉もして、日本発で困難なミッションを実現し、「東京宣言」と「アクションプラン」を採択して、オスロ合意が失敗したからこそ新たなプロセスを作っていくというところで、さらに動き出しています。
パレスチナ問題において即時的な解決策というものは、残念ながら存在しません。どうしても中長期的なものになります。そして、その解決策は、大国でも我々のような外国の人でもなく、あくまでもパレスチナとイスラエルの人自身が生み出すしかないと思っています。私はパレスチナの若きリーダーたちの可能性を信じています。私は紛争解決のプロとして色々な案はありますが、それが答えだとは思っていません。彼ら彼女らの可能性を信じているユニークな第三者として、和平プロセスを共に創る、支える。特に排除されるような人々を組み込み続けて、この東京宣言とアクションプランの実現を最後まで支えていきたいと思う次第です。
——Batoolさんのお話 ~パレスチナの未来を創っていく政治的な主体者として~——
皆さん、おはようございます。アクセプトさん、ありがとうございます。パレスチナ人の代表として、パレスチナの首都であるエルサレムから参加しています。この街は、私のリーダーシップやアイデンティティー、責任の基になっています。私は教育や起業などを行っているプロジェクト・コーディネーターで、この社会のリーダーとしてシステマティックな解決を求めて活動をしています。
私は今日、紛争の犠牲者としてではなく、これから未来を創っていく一人の主体として、お話をしたいと思っています。

パレスチナの未来を築く結束 政治・経済においても基礎的
2023年10月7日、これはとても大きなターニングポイントでした。地域的なダイナミクスだけではなくて、パレスチナの若者としてどういった役割があり責任を持つのかというところです。パレスチナの国家プロジェクトはどこへ向かっていくのか、どのような私たちの未来を築くべきなのか、そして、どんな世代をつくっていけばいいのか、といったことを突きつけられました。
そこで私は、結束がなければ、そこに未来はないと考えました。これまで政治的な分裂や、制度的な崩壊がありました。しかし明確になったのは、パレスチナの団結というのは政治においても、今後の経済開発においても基盤になるということです。
日本だからこそ集えたパレスチナの多様な若者 生まれた強い連帯 未来を築く行動計画を創出
そこで、私は、若者として平和構築の重要性に対して何か効果的なことができるのではないかと信じてアクセプト・インターナショナルの対話に参加をしました。私たち自身の可能性というものを、私自身も信じています。こうした国境を超えた対話に参加するというのは、何か象徴的なものだけではなく、むしろ現実的な戦略であり、今後を見据えてネットワークなど何を築いていくのかというところで、とても重要なポイントでした。
他の若手リーダーたちも実に様々な政党や市民社会から参加をしていました。こうした対話はパレスチナの中では実施が難しいので、日本だからこそ実現できたと思います。これから、団結のためにできる具体的な行動として若者である私たちに何ができるのか、そして、どのような制度的な信頼を私たちの間で築くことができるのかについて話してきました。
結果としては、ただの対話だけではなくて、本当に強い連帯を築くことができたと思っています。最終的には、政治的な公式宣言やアクションプランを作ることになりましたが、それらは包摂的に様々な立場の人たちをつなげた議論に基づいています。結束というのは、リーダー層からだけではなくて、次の世代である私たちから始まるものだと強く感じました。
広島への訪問ではとても多くの学びを得ることができました。歴史的な背景は違いますが、インフラを再建することだけではなく、教育や、平和に向けた地道な取り組みが行われてきたことに気づかされました。パレスチナは今でも構造的な暴力に耐え続けていますが、苦難の先に復興が本当に可能だと思わせてくれました。
対話を通じて、参加した若者の間に共通するものがあると感じました。それは、世界の政治状況の中で何かしらのフラストレーションをお互いに抱えているという点であったり、そして軍事的手段に依らずに新たなリーダーシップを築くことへの願いであったり、過去に囚われることなく未来を築いていくことへの投資の必要性です。
こうした学びを通じて私たちは具体的なアクションを実行しうるための行動規範や行動計画を考えてきました。占領や制限により見通しが立たないからといって、パレスチナの若者たちは状況が好転するのをただ待ったりはしません。私たちは世界的なデジタル部門のプロジェクトや文化的プロジェクトを積極的に進めています。技術者、研究者、文筆家、芸術家たちを通じて、様々な分野において築き上げてきました。それは、抵抗の物語ではなく、私たちの能力(キャパシティ)を広く表明する機会だと捉えています。政治的な場、制度的な支援、国際的な承認における私たちの価値を位置づけていると考えます。
国際的なパートナーの皆様へ、パレスチナの若者は同情を求めているわけではありません。私たちは、対等な関係性に基づいて共に行動することを求めています。私たち若者をぜひ公式な対話に参加させてください。そして、パレスチナが主導するプロジェクトを支援してください。単なる人道支援の受け手ではなく、政治的な主体者として私たちを認識していただきたいのです。そして、平和に向けた前提条件として正義が実現されることもまた必要であるとご理解いただければと思います。
私たちの正当性が多くの方々に認められてこそ、リーダーシップが発揮できると考えています。共感だけではパレスチナの状況を改善することはできません。その平和は、公正さや連携、そして戦略的な計画と行動に基づいたものであるべきです。
——Asselさんのお話 ~パレスチナの団結と平和のための活動~——
皆さん、こんにちは。本日はこうした機会をいただき、ありがとうございます。
まず、私の紹介をさせてください。私は22歳で、ヨルダン川西岸地区でコンピューター工学を学んでいます。特に、同時に、若手の活動家としてワシール青少年育成センターを拠点として、パレスチナの団結や平和のために若者に対して様々な活動を行っています。
私がアクセプト・インターナショナルと一緒に活動している理由は、どうにかパレスチナの人々の間での結束を強めていきたいと思っているからです。「パレスチナの団結に向けた若者の実行委員会」から現実的なアイディアを生み出して、団結を強め、積極的に参加していきたいです。私たちの前には様々な困難が立ちふさがっていますが、意味のあるアクションを起こしたいと思っています。

パレスチナの国家承認は象徴的なものにとどまるのか 占領軍によって人権が奪われている日常
2023年10月7日以降、パレスチナの若者たちの状況は本当に変わってしまいました。絶え間ない恐怖やセキュリティ上の不安の中で暮らしています。そうした中でも勉学や社会活動への参加を続けています。なぜなら、そうした活動を経て生まれる団結だけが、分裂や分断を乗り越えていく手段だと思っているからです。
昨今、多くの国々がパレスチナを国家として承認し、パレスチナを支援しようとしています。ただ、そうしたものが多分に象徴的なもので終わってしまっているとも感じます。実際にはイスラエルの占領は変わっておらず、むしろ助長してしまっている状況があると考えています。
(ここで、現地でどう占領が起きているかを3つの短いビデオを通じて見せました。)
私が通う大学では、占領軍の兵士が銃を持って歩いています。催涙ガスが建物内に投げ込まれて、学生たちは息をすることもできず、次々と病院へ搬送されていきました。私たちが学ぶためにあるはずの教室は、緊張感のある場所に変わってしまいました。こうした状況の中で勉強するのが日常です。私たちは満足に勉強することもままなりません。
ガザにおいて占領軍によるパレスチナの人たちへの行為に対して、パレスチナの女性たちが平和の声を上げました。私たちは多くの場合、声をあげることも許されません。その女性たちは、占領軍によって暴力を加えられました。
私の出身地のトゥルカレムでは、数週間前に占領軍が多くの人たちを何の理由もなく逮捕しました。こうした状況で街自体がロックダウンされてしまいました。人々は自由に移動することができず、病院に行くこともできません。
パレスチナでは出会えなかったガザの若者とヨルダン川西岸地区の若者 日本で集い、団結して困難を乗り越えていくビジョンと希望を共有 パレスチナの若者たちが未来をつくる主体であることを示す責任を自覚
今年の8月、私は日本での対話に参加する機会を得ました。若者代表として、私たちが直面している難しさ、苦しみをしっかりと伝えたうえで、団結の大切さについて話すという大きな責任の伴う経験でした。広島で起きたことは本当に大きな悲劇でした。ただ、そんな苦境を乗り越えて、経済的にも日本が再建したというのは大きな気づきでした。私たちも、深く傷ついた国であっても、そういった経験に基づいて立ち直ることができると信じています。
私が印象に残ったことは、エルサレム、ガザなど様々な地域から多くの若者たちが団結のために集まったことです。困難から立ち直る力を高めるためにも私たちは集まりました。私たちの共通の祈りと希望は、明日の若者たちとしてどうにかこの厳しい状況を一緒に乗り越えていくことでした。
東京滞在中に、モスクで日本の方々と交流する機会があり、その時にマリアムという若手リーダーの一人が、2023年10月7日以降も戦争の渦中にあるガザ地区で100日以上も暮らしていた苦しい経験を語ってくれました。この話を聞いて、私は涙が止まりませんでした。私が住んでいる場所からガザは数時間しか離れていないのに、日本に来るまで彼女を含めガザで苦しんでいる人たちに出会うことすらできませんでした。その苦しみを日本で共有していることができました。彼女の話を聞くことで、私たちの義務として、祖国のために立ち上がり、パレスチナの団結を実現していくことが重要であると改めて深く感じました。
短い日本での滞在でしたが、本当に多くのことを学びました。日本の人たちは高度な教育を受けていて、とても優しく、さまざまな意見交換を行いました。広島で歴史を学ぶ中で様々な人の話を聞いた時、私たち全員が破壊されたパレスチナの都市やガザを思い浮かべました。日本の人たちは、多くの時間をかけ、色々な人が関わる中で再興できるということを教えてくれました。私自身はパレスチナで生きる一人の若者であり、教育こそが苦難を乗り越えていく際の武器になると考えています。
重要な気づきとしては、私がこの場にいることは贅沢ではなく、パレスチナの人々の声をしっかりと伝えていくという大きな責任があると感じたことです。私たちパレスチナの若者が“失われた世代”ではなくて、これから“未来を創っていく世代”であるということを示していく必要があります。
こうした団結に向けた実行委員会の活動やアクセプトとの協働を通じて、私は具体的なビジョンや希望を得ることができました。それがパレスチナのために動き続けるモチベーションにもなっています。ありがとうございました。
—パネル対話(永井陽右さん・Batoolさん・Asselさん・寺中誠さん)—
パレスチナの国家承認をめぐって
永井陽右さん) 率直に今のパレスチナの状況をどう見ますか? 今、フランスやオーストラリアなどがパレスチナを国家として承認している一方で、先日、日本政府が、現時点では日本はパレスチナの国家承認を見送ることを発表しました。日本として二国家解決を支持しているものの、適切な時期を探しているとのことです。国家承認をめぐっては、広島や東京での対話会合でも議論しましたが、一部の専門家も指摘するよう、パレスチナ内部が分断している今日の状況で国として認めることは危険ではないかと私自身も懸念しています。それについてどう思いますか?
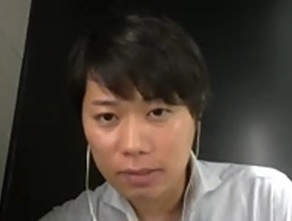
Batoolさん) 私たちは今、多くのショックを感じています。多くの国々がパレスチナを国として認めていますが、実際にはイスラエルの占領が強化されています。パレスチナが国として認められたとしても何も状況が変わっていないことに、大きなショックを抱えています。
また、多くのパレスチナの人々が逮捕されている状況もあります。境界を通過するのにも長い時間がかかります。国家承認をただスローガン的に行うのではなく、承認が何を意味するのか、そして現地の状況を見てほしいと伝えたいです。私たちは本当に苦しんでいます。多くの国々がやっていることだけが正しいとは思いません。
Asselさん) 私の意見としては、二国家解決がガザの抵抗を止めるものであると認識されているように感じます。国家承認は単に象徴的なものであって、いまだにイスラエルは占領を続けています。やはり具体的な行動が伴わない限り状況は膠着したままです。
寺中誠さん) いくつの国がパレスチナを国として認めたのか、マップを共有しようと思います。
永井さんが話したように、日本の政府は認めていません。韓国、ミャンマー、ニュージーランド、デンマーク等も認めていません。もっとも権力があるアメリカも認めていないですね。ただ逆に、他の国々はほぼ全てがパレスチナを国家として認めている状況があります。
これは政治的なものも示しています。私たちとしては、その政治的なディスカッションに参加をするということではないですけれども、こうした現実も同時に見つめていく必要があると考えます。私たちは国家承認自体に100%賛成するわけではないですけれども、新しいディスカッションの段階にあるということを示していると感じます。
新しい和平プロセスをつくるために私たちは何をすべきか
永井さん) 寺中さんがおっしゃるように、国際社会の大多数がパレスチナを国家承認しようとしています。ただ、同時に、BatoolさんとAsselさんからのパレスチナの実情に即した現実的なアイディアを含め、状況がかなり悪化していることを踏まえて考える必要があります。イスラエル側も最近はますます原理的で暴力的な手段に出てきています。
これに対して、日本も含めて国際社会はサポートしようとしています。かつてのオスロプロセスが失敗に終わり、我々がすべきことはオスロに変わる新しいプロセスをつくることです。それが、パレスチナの平和につながると、私たちは常々考えています。
ちょっと意見を伺いたいのですが、私たちは今、どのような行動を取るべきでしょうか。多くの国々がパレスチナを承認している中で、状況は、ガザはもちろんヨルダン川西岸でも好転していない。多くの植民者が押し寄せ、域外を自由に行き来するためのアクセスもありません。そうした中で、我々は今何をすべきでしょうか?
正当な選挙によって適切な政府をつくることがパレスチナの未来をつくる鍵 国際社会は選挙成功のための保障を
Batoolさん) 必要なアクションプランを考えるにあたって、状況を変えられる行動を検討すること、かつ、多くのパレスチナの人たちの声を集めることが本当に必要だと感じます。
政策を変革できる人が足りていない今こそ、選挙を行い、適切な政府をつくっていくことが必要だと感じます。それによって、国際的に国々に働きかけることができると考えています。これがパレスチナの未来をつくるための鍵になると思っています。
選挙ができない原因は、もちろん占領が続いていることです。なぜ占領が続いていることで選挙ができないのか? パレスチナの人々が結束してしまうと、イスラエルが占領を続けられないので、彼らは選挙ひいては団結を妨害しているのだと思います。
だからこそ、国際社会には、パレスチナの人々が安全に正当性のある選挙を実施できるようなサポートや保障をしていただきたいです。選挙によって、真に必要な新しい政治家たちを擁立することができるでしょう。これまで何度も選挙をしようとしてきましたし、実際に2006年には選挙が実現しました。ただ、その時も国際社会では支援しきれなかった点もあり、パレスチナの人々の声が広く反映されたものではありませんでした。
皆様には国際社会の一員として、ぜひパレスチナの現実をその目で一度見ていただきたいと思っています。ただ、現在の状況では誰も現地に来ることは難しいところですが、私たちは未来を築いていきたいので、占領を止めるようなアイディアと行動が本当に必要とされていると感じています。
永井さん) Batoolさんの考えに賛成です。パレスチナ自治政府は選挙が大事だと強調していますが、それは多くの困難が伴うものであり、同時にある種の言い訳のようになっていて、現実ではパレスチナ自治政府はイスラエルに対抗する力を全く持っていません。
だからこそ、若手リーダーたちが日本に集まり、国際社会と協力して選挙を成功裏に実施するための保障が必要だと発信していこうとしています。カンボジアやコソボなどでは、国際社会が軍を伴わない公正な形で選挙監視団を派遣しました。私たち日本もこれまでの経験を活かして、国際社会との間で選挙分野に関する協力を強めていき、選挙監視ミッションを行う必要があると考え、私たちの革新的な行動計画の中に盛り込みました。
パレスチナで何度も選挙をしようとしていますが、イスラエルの占領によって実現には至っていない状況が続いている中で、どのように状況を良くしていくかがポイントだと思います。そういう意味では、具体的な選挙計画が若者たちから出てくることを期待しています。
パレスチナの占領実態や若者の声を記録し共有することで起こす団結への変革
Asselさん) 日本での対話会合に参加した後、私たちは行動をとろうと努力してきました。私自身も、メディアを通じたアドボカシーをしようと奔走しています。パレスチナの若者たちの苦しみや、占領によって何が実際に起きているのかを記録することを続けてきています。こうした声に基づいて、色々な人たちの物語を伝えていくことで、変化をもたらすことができると信じています。団結するために、こうした記録を共有していくことが、実は非常に重要ではないかと感じています。
なぜ、大量殺戮が起きている今まさに対話をすべきか
永井さん) 日本での対話会合後、我々は既にいくつかのアクションを実行に移してきました。今回来日した若手リーダーの一人は、レバノンで小規模ながら類似の対話イベントを行いました。とても興味深く、またポジティブなものです。また、ガザ地区で活動する若者リーダーの一人は、残念ながら今回の日本会合には参加できませんでしたが、今は現地のNGOで働いていて、ガザの中心部でユース対話集会をやろうとしています。そうした対話イベントをさまざまな若者のリーダー、政治・市民社会を含めた形で、ガザだけでなく、レバノンやヨルダン川西岸地区やヨルダン等さまざまなところで実施できないかと考えています。
選挙に関連して、国際社会に認められたパレスチナの代表機関であるPLO(パレスチナ解放機構)がその機能を果たせるようにどうしていくか、また、パレスチナ人が世界各地にいる中で、PLOの選挙を行うかといったところが非常に重要になってきます。
Asselさんの話にもありましたが、ガザやヨルダン川西岸だけでなく、トルコ、レバノン、エジプトなどさまざまな国から、今年8月に広島・東京に集まりました。同じパレスチナ人であっても一堂に会することが非常に難しい状況の中で、この日本会合を実施できたことは重要でした。私たちは、選挙に向けた具体的な行動を考える必要があることと、そうした対話会合を世界のさまざまな国に拡大していくことが重要だと考えています。こういったことについてどう考えますか?
一方で、ガザでは現在進行形で大量虐殺が起きていて、対話のための時間もエネルギーもないため、まずは大量殺戮を止めることが先決で対話は二の次と考える人もいます。しかし、私から言えば、大量殺戮が起きている今まさに対話をしていくことが重要だと考えています。なぜ今、対話をすべきだと思いますか?
社会課題へ対応できない機能不全の政府 若者同士が対話で信頼を築き、市民の信頼を得られる政府に変える
Batoolさん) 私は、対話が信頼を得るために必要だと思っています。私たちはPLOやパレスチナ政府に対する信頼を失っています。私たち同士がお互いに信頼し、新たな関係を築くことができれば、今まで苦しい過去があったとしても、未来を変えることができると信じています。
私たちは、本日のイベントのように国際社会に自分たちの声を届けることはできているかもしれませんが、パレスチナ内部ではそれができていない状況があります。パレスチナ政府も人々の声を聞き、アクションプランを策定するべきです。パレスチナの独立宣言においてエルサレムがパレスチナの首都であると定められましたが、実際にはイスラエルの占領下にあり実現に至っていないのは、適切なアクションプランがないからです。継続的に実現までの道筋とそれを実行することができていない状況にあります。パレスチナの人々と政府との間のギャップを解消していくための行動を取らなければなりません。
私たちは、本当に普通の生活を送りたいだけなのです。そして、私たちの声を表明していきたいのです。例えば、大学に行ったら理解できないことがあったり、社会の中でうまく機能していないことがあったりしますが、政府がそういった課題に対応ができていないということが問題です。もちろん占領も問題ですけれども。そのため、エルサレムやヨルダン川西岸地区など各地から代表者を招いて、これまで何を成し遂げてきたのか、何が課題だったのか、そしてどんな責任を政府として担っていくべきなのか話し合う必要があります。
それぞれの地域で代表者がいない、あるいは誰が代表者なのかもわからないというような、政府が機能していない状況にあります。そして、大統領自体も実際に何が起きているのかを理解していないという問題もあると思うので、私たちはしっかり声をまとめて、やってほしいことや考えてほしいことを伝えていく義務があります。国のリーダー自身も何をしているのか理解していないし、人々も理解していない。それは本当に大きな問題です。私たちとしては、代表者の義務・責任を明確にして、それを要求していくことが重要だと考えます。
永井さん) そうですね、Batoolさんが指摘したように、何のための対話なのかというのは、まさに信頼を築くという点にあります。特にガザでは10月7日の攻撃以降ハマスに対する支持が低下しており、誰がハマスに代わるプレゼンスを発揮できるのか、市民社会の人たちがどのように考えているのかという点は指導者層に全く聞かれていません。そういったところで、不信感が高まっていると考えられます。だからこそ、対話によって信頼を築くことでは非常に重要なのです。
市民のニーズや声に応えられる、説明責任を果たせられる政府に変える
Asselさん) 現在、特にヨルダン川西岸地区ではパレスチナ自治政府に関して多くの問題が生じています。彼らは公務員に給与を支払わないし、なすべきことをなさずにずっと静観しています。若者たちが市民としてまとまり、政府に対して説明責任を求めていくことが重要だと思います。同時に私たちも、様々な市民たちの話をしっかり聞いていくことが大切です。実際、今は、政府がこうした人々のニーズや声に基づいて組織されているとは思えません。パレスチナ政府の変革が必要です。そのためにもやはり選挙を実現することが鍵になると思います。
永井さん) そうした気運をパレスチナ内部でも国際社会でもつくっていくところが非常に重要になってきますよね。政府と市民が信頼を築くために、政府が選挙に向けた行動を起こし、具体的に説明責任を果たすことは私も肝要だと思います。
寺中さん) ありがとうございました。1つ印象的なことは、今のパネル対話が全部英語で行われたということです。当然、BatoolさんもAsselさんも英語は母語ではありません。普段はアラビア語で話されています。そういう意味では、私たちは現地の人たちの生の声を母語のまま聞くことができていない。そして、その時に必ず介在される英語という言語は、イスラエルやパレスチナの地域においては支配者の言語です。これを私たちが使っているというのは、我々がよく直面する運命的な問題です。結局、征服者の言葉を使っているということを私たちは十分に理解し、その暴力性というものを意識した上で、対話を進めていかないといけない。これは、AsselさんもBatoulさんもかなり強調されていたと、今のお話の中で私は感じました。
――グループ対話とグループ発表を経て、ゲストからのコメント――
※グループにゲストも加わり、グループの方々に感想や意見、ご質問を話し合っていただいた後、会場全体で共有するために印象に残ったことを各グループから発表いただき、出演者からコメントをいただきました。
Asselさん) 皆さま、本日はお時間をいただいて、私たちのお話を聞いてくださり、ありがとうございました。アクセプト・インターナショナルとソーシャル・ジャスティス基金の皆様には、こうした機会をいただいて、大変感謝をしております。皆様、ありがとうございました。
Batoolさん) 本当にありがとうございました。対話だけではなく、私たちの話を聞いていただいて一緒に行動していくことが、皆さんと私たちの義務・責任だと感じています。これは1回きりの対話ではなくて、私やAssel、他の若者たちと一緒に状況を改善していくための1つのプロジェクトだと思っています。教育やアドボカシー、さまざまな分野があると思いますので、パレスチナの若者たちと一緒にアクションを拡大していけたらと思っています。皆様のお話には本当に鼓舞されましたので、これからも一緒にアクションを続けていけたらと願っております。本当にありがとうございました。
永井陽右さん) パレスチナの問題を解決していく、パレスチナをよくしていくところにおいて、よき第三者の存在が不可欠であるということは、今日のお二人の話を聞いていて改めて感じました。私たち自身、よき第三者としてさまざまやっていく中で、そのことを感じています。ですので、私たちは日本の民間の組織であるからこそできることは明確にありますので、そうしたところを日本からしっかりと支えていければと思います。
BatoolさんとAsselさんは、信頼をつくっていかないといけないだとか、今のような状況でも対話が大事だとか熱く話してくれました。こうしたパレスチナの若きリーダーたちが本当に鍵で、可能性なのだろうと常に思っています。
私たちアクセプト・インターナショナルによるパレスチナでの取り組みは特設サイト(こちらから)でも紹介しておりますので、もしよろしければご覧ください。私たちは、ガザ地区での人道支援もパレスチナの新たな和平プロセスに向けた対話にしても、基本的に皆さまのご寄付を基に運営していますので、ぜひご寄付もご検討いただけましたら幸いです。
本日はありがとうございました。
- 次回SJF企画のご案内★参加者募集★
『ソーシャル・ジャスティス 連携ダイアローグ2025』
【日時】2025年12月13日(土)13:30~16:00
【詳細・お申込み】 こちらから
※今回25年9月27日のアドボカシーカフェのご案内チラシはこちらから(ご参考)

