ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第93回開催報告
トランスジェンダー差別から考える社会課題
~アート作品を見ながら語り合う~
2025年8月30日、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)は、trunk等から岩瀬海さん、中島伽耶子さん、櫻井莉菜さん、山もといとみさん、美馬摩耶さんをゲストにお迎えしてSJFアドボカシーカフェを開催しました。
全体セッションで岩瀬さんと中島さんにお話いただいた後、櫻井さん・山もとさん・美馬さんも加わって参加者のみなさまとグループ対話を3セッション行いました。各セッションでは、異なるゲストがアート作品を携えて交替でグループを訪れ、作品の背景にある問題等をお話した後、それをきっかけに対話が行われました。
trunkは「すべての人が生きやすい環境というものは一体どういうものなのか」というのを考え続けるために、連帯しながら活動している市民団体です。多様な人が意思表明の一つの手段として多様な方法で出品等ができるひらかれた展覧会がtrunkにより25年の11月26日から12月2日まで東京藝術大学上野キャンパスで開催される予定です。普段は交わらない人がつながる場ともなりえ、いま個人が抱える複雑な感情や状況をそのまま伝えられるアートが持つ可能性、また、アートを通して当事者性を体験できる可能性への期待が寄せられています。
詳しくは以下をご覧ください。 ※コーディネーターは明戸隆浩さん(SJF元審査委員)。
 (写真=上左から時計回りで、山もといとみさん、櫻井莉菜さん、美馬摩耶さん、明戸隆浩さん、中島伽耶子さん、岩瀬海さん)
(写真=上左から時計回りで、山もといとみさん、櫻井莉菜さん、美馬摩耶さん、明戸隆浩さん、中島伽耶子さん、岩瀬海さん)
目次
——岩瀬海さんと中島伽耶子さんのお話(全体セッション)——
中島伽耶子さん) まず、“trunk”という団体について、「一体何?」と思う方がほとんどだと思いますので、少し紹介させていただきます。trunkは秋田に拠点を置いています。テレビや新聞といった既存のメディアでは取り上げられないような声を、読書会や映画の上映会などのイベントを開催したり、展覧会を企画したり、いろんな形で発信しています。それをさまざまな人と共有して、「すべての人が生きやすい環境というものは一体どういうものなのか」というのを考え続けるために、連帯しながら活動している市民団体です。今は6人しかいない小規模な団体です。2021年に結成し、メンバーの好きなことから出発して動いています。
今回ソーシャル・ジャスティス基金に採択されたプロジェクトは『例えば「天気の話をするように痛みについて話せれば」』という長いタイトルなのですが、これについてご紹介していきたいと思います。
trunkのメンバー6人のうち3人が主に中心メンバーとなって、このプロジェクトを動かしています。 その一人が岩瀬海さん。アーティストで彫刻を作っています。身体をモチーフにした彫刻、ジェンダーやセクシュアリティといったことを記憶と結びつけて彫刻にするアーティストです。もう一人が私、中島伽耶子です。同じくアーティストとして活動していて、空間全体を作っていくようなインスタレーションという部類の大規模な作品をつくっています。そして、もう1人が櫻井莉菜さんで、今回のゲストの1人です。アートマネージャーで、作品を直接作るわけではないのですが、展覧会を作家自身にとっても見る人にとっても安全な場にすることを、展覧会を作っている段階から展覧会が終わるまで専門に考えて調整したり事務的なことで動いたりする仕事を専門にしている人です。
ここで、対話のグランドルールを皆さんと共有したいと思います。これは、このイベントが主催者側にとっても参加者側にとっても安全であるためのルールです。
まず1つ目。「この場所はトランス差別に反対し、みんなが生きやすい社会について考える場です」。それをみんなで考えるために集まったということを共有したいと思います。
2つ目。「他の参加者へのリスペクトを大切に、決めつけや否定はやめましょう」。ということで、前半は私たちが主に話しますが、後半は皆さん同士で話し合うこともあるので、その時に他の参加者へのリスペクトを大切にしましょう。
3つ目。「他の人の話は遮らず最後まで聞く」。気持ちが盛り上がってくると。人の発言を遮って話したいと思う方がいるかもしれないけど、少し落ち着いて、まずは他の人の話を最後まで聞いて、その上でどうだったかというのを話すようにしたら、お互いにすごく気持ちいい空間になると思います。
4つ目。「画面越しだからこそ、リアクションでお互いに安心を」。きちんと聞こえてるのかなとか、伝わっているかなとか、少し緊張してしまうかもしれませんので、何かあった時にはZoomのリアクションというボタンを使ってもらえると安心できて嬉しいです。
5つ目。「ここで話したことは、この場所だけで」。今回、“痛み”というものが大きなテーマになってくるので、個人的なお話や経験も出てくると思いますが、安全に話せる場にするために、個人的なことを会が終わってから外で言いふらすことは止めましょう。
最後。「苦しくなったら無理せず」。いろんな言葉が出てきますので、嫌なことを思い出したり、体調悪くなったりしたら途中退出してもらって大丈夫ですので、自分のペースで過ごしましょう。
岩瀬海さん) では、『例えば「天気の話をするように痛みについて話せれば」』という企画(以下、「例えば展」)が一体どういうもので、どう始まったのかという話をしていきたいと思います。
2018年に政治家による「LGBTQは生産性がない」というどストライクな差別発言がテレビ放送を通して流れてしまいました。
2019年には、お茶の水女子大がトランスジェンダーの学生を2020年度から受け入れることが発表され、これを機にトランスジェンダーへの差別が激化したと言えます。それまで多くの人にとってトランスジェンダーというものが存在していなかったのが、その発表によって初めてトランスジェンダーという存在を知った人たちが、意図的に差別的な発言をすることが増えていき、それに関連してSNSでのトランスへの暴言、差別発言が増大しました。
この時期に、アート業界でもフェミニズムをテーマとした展覧会が増えていきました。特に2019年から大手のメディアもたくさん紹介するようになって有名になってきたと思います。ですけど、その時期には、「フェミニストです」と公言をしながらもトランスジェンダーへの差別をする人たちが後を絶ちませんでした。展覧会などでも、「フェミニズム」と言いながらもトランスの現状を語るものが、私の記憶ではほぼ無かったのが2019年です。
それで私たちも何かしなくてはという思いがあり、私たちが住んでいる秋田だからこそ、こういう話を始めるのにぴったりなのかもしれないと、私たちの活動が始まりました。
私たちの展覧会は、これまで秋田のギャラリーで行ってきました。空間全体を使った大きな作品であるインスタレーションを展示したり、小さな空間を活かした彫刻を配置したりしました。作品だけではなく、“お天気シート”という、来てくれた方は誰でも自分の思いを書いて貼り付けて公開できる、もしくは自分で持って帰れるものも作りました。自分がモヤモヤしていることや、悩み、人に言えなかったことを、対面ではなくテキストで残していくというインタラクティブアートとも言われる表現です。また、展覧会の会場内で、お話し会やLGBTQに関する勉強会もゲストを呼んで開催しました。
トランスジェンダーの人が被る困難は社会問題の縮図
中島さん)こんな感じで、現状に対して何かアクションをしたいと思って3人で展覧会をやりました。
展覧会の中で勉強会もやってみて思ったことが、もっと専門性、知識をつけないと話せないということでした。
2022年に『トランスジェンダー問題―議論は正義のために-』というショーン・フェイさんの著書を高井ゆと里さんが翻訳した本が日本で出版されました。それまで日本では、トランスジェンダーについてきちんと研究されて書籍化された本が少なかった中で、非常にまとまった状態で出版されたので、読んでみようと思ったのですが、この本が結構難しかったのです。長い上に文体が硬く、差別について語るので苦しい内容が多く紹介されていることもあって、1人で読むのではなく、trunkのメンバーみんなで勉強会を行いました。
この本の中で、トランスジェンダーの人が被る困難は社会問題の縮図であるということが繰り返し語られています。そして、トランスの解放は、トランスの人々だけでなく、差別を体験する他の人の解放にもつながるということを学びました。
いろんな問題がつながっているということです。例えば、トランスジェンダー女性に対する過剰な差別発言が女性蔑視やホモソーシャルにつながる。性別変更に必要な日本の法制度からは、日本の持つ優生思想や、障害を持つ人たちへの差別が根深いことがよくわかる。トランスの就職率の低さからは、学歴社会や貧困の問題が浮き出てくる。トランスの婚姻状況は、日本で同性婚ができないことを多角的に見るきっかけにもなる。このように、トランスの問題を語ることがトランスだけの話に終わらない。当然のことですけど、いろんなことが深くつながっていることがよく分かりました。
このように自分たちで行った展覧会や勉強会はtrunkでの元々の活動と密接に関わってきたということもあり、単発で終わらせる問題ではなく続けていこうということでプロジェクト化していきました。
そこで翌2023年に、展覧会を“When we talk about us,”と名付けて、秋田市文化創造館という大きな建物の1階と2階を貸し切り、1階で「例えば展」のプロジェクトの場所にして、2階を現代美術の展覧会を開催する場所にして行いました。この時、「例えば展」では、本や雑誌・漫画を自由に鑑賞者が手に取って読めるフリースペースを作りました。読むだけではなくて、自分でZINE(ジン)を作ったり、他の人が作ったZINEを読んだりもできる場です。置いた本は、trunkのメンバーが興味のある本や勉強した本などです。いろんな問題が関わってくるので、多様な種類の本が置かれました。「例えば展」には、和田華子さんの作品も展示しました。
また、trunkのメンバーは元々ラジオ配信もしていたので、この会場でラジオを配信し、曲のリクエストを募りしました。トークイベントも行い、先ほど紹介した『トランスジェンダー問題』の翻訳をした高井ゆと里さんや、東北でずっと活動されていた性と人権ネットワークESTOという団体の真木さん、政治家の依田花蓮さん、結婚相談所を運営されている松倉みほ子さんなど、秋田と秋田県外も含めていろんな方にお声がけして、手話通訳もお願いして開催しました。他には読書会や勉強会も行いました。
2階の展覧会では、ジェンダーや痛みなどをテーマにしている作家さんを集めて、西原珉さんにキュレーションしていただきました。この展覧会で見たキャプションに専門的な単語も出ていても、1階に下りた時に「例えば展」にいろんな書籍があるので、分からなかった単語など自分の必要な知識を自分のタイミングで見られます。そういったことを理想にして、1階と2階をセットにして開催しました。
岩瀬さん) ここで、私からは、今年2025年度に開催する「例えば展」の話をしようと思います。
今年は11月26日から12月2日までの開催を予定しています。会場は今までずっと秋田でやっていましたが、今年は秋田を飛び出して東京で開催しようと企画が進んでいます。
今回の「例えば展」でも、現代美術の展示とイベントを引き続き行おうと思ってます。今回は会期中に引っ越しが入ります。2025年の11月26日から29日は、東京藝術大学上野キャンパス大学会館2階の展示室で行います。このスペースはいわゆるホワイトキューブという四角い白い部屋なので、主に視覚芸術の展示、美術作品の展示をしようと思っています。そして、29日に全部の作品を陳列館という2階建ての大きなギャラリーに移動します。11月29日から12月2日の会期ではパフォーマンスやトークイベントなどをメインに行おうと思っていますし、どんどん追加される作品も見られると思います。2つの会場は歩いて3分程の距離ですので、11月29日は引っ越しの様子も見ながら参加してもらえる感じです。
意思表明の一手段として、出品に限らず多様な方法で参加できる開かれた展覧会に
中島伽耶子さん) 今までの「例えばプロジェクト」では私たちメンバーが作った作品を展示したり、私たちが誰かにお願いして作品を出してもらったりしていましたが、今回は参加者を広く募集しようと思っています。
表現も自由ですし、私たちが信頼できると思った人たち、一緒に何かしたいなと思った人たちに声をかけて、またその人たちも自分が信頼できる人たちに声をかけて、という感じで話していくにつれて参加者が増えていくようにしたいと考えています。無理に一緒にやろうというのでもなく、コミュニティを1つにまとめたいとも思っていないですし、存在しているコミュニティがゆっくりつながって、1つの形として現れていくような展覧会が作れたらと思っております。
何か作品を出すことが1つの意思表明みたいになればと思っているので、作品を作っている人には作品を出してもらえたら嬉しいと思うけれども、そうでない人にも例えば好きな本や日用品を飾ってみたり文章を書いてみたりとかいろんな方法で参加してもらえたらと思っています。
それでも慣れてなくてハードルが高いと感じる人も多くいると思うので、今回「バスルームソング」と名付けて、ラジオで曲をリクエストするような感じで、展覧会に曲をリクエストすることを1つの参加方法として提示しています。テーマは「バスルームのように個人的だけれども、自分を温めてくれる曲」です。ラジオネームとその曲を選んだ思いみたいなのを書いてリクエストしてもらって、会場で流せたらと思っています。
複雑な感情や状況をそのまま伝えられるアートが持つ可能性 アートを通して体験することの当事者性
そもそも、なぜtrunkは展覧会をアクティビズムの1つの方法として選ぶのか疑問に思われるかもしれません。まず、先ほど紹介した3人のメンバーが美術が好きで、好きだからこそ継続していける可能性がある。やはり続けていかないと意味がないこともあるので、展覧会や美術というものを選んでいます。
また、アート作品というものが、複雑な感情や状況をそのまま伝えられる可能性があると思っているからです。何か白黒つけるとか、法律をこうしないといけないとか、話し合わなければいけないことはたくさんありますが、個人の感情をそのまま形にして見た人に伝えられることが持つ可能性を信じています。
展覧会はひらかれた場所として私たちが提示しやすいとも思っています。来場者は何か買わないといけないわけでもないですし、何かを見に来るフラットな場所として作れたらと思っています。
展覧会を通して体験することには当事者性があります。作った人の感情を、作品を見ることによって感じ取り、自分に近づけて考えやすいと思っています。
さらに、作家ではなく作品が前に出ることによる安全性をすごく感じています。活動をする時は自分が前に出ないといけないことが多いですが、展覧会は作家本人ではなくて作品が鑑賞者と出会う場所なので、作った本人が安全に自分の気持ちや経験を表に出せる方法だと思っています。声を上げることが安全でないからこそ展覧会というものを選んでいるとしみじみ思っています。アウティングの問題もありますし、パレードに参加したいけれども街中を歩くことが危険を伴うから行けない人や、誰かにバレることを恐れて声を上げられないという人も多くいると思います。だから、ラジオで曲を1つ選ぶとか、自分の好きな本を送るとか、自分が前に出ないそういうアクションで声を上げる方法があってもいいよねと思いながら展覧会を選んでいます。
アート界のハラスメントやジェンダーバランスの問題
多様な人が共存できる社会を目指しセーファー・スペースとしての展覧会を実践
抵抗としてのアートが果たす役割とは
岩瀬海さん) ここで、皆さんにお話ししておきたいことがあります。美術の世界は自由なのではないかと思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、いろんな事例を見ながら日本で美術の世界が今どんな感じなのか見ていこうと思います。
「表現の現場調査団」というグループがあります。表現の現場で起こるハラスメントなど、あらゆる問題を調査する。解決することも目的ではあるだろうけど、そもそも問題があることが分からなければ解決できないので、まずは問題を調査しようというところから始まりました。
「表現の現場で起こるハラスメントに対して声を上げづらい状況が長く続いた。要因の1つに、評価する・評価される側の権力勾配、ジェンダーバランスの均衡がある。例えば、美術大学では女子学生が半数を超えるにも関わらず男性教員が多い現状。コンペなどの審査員に男性が多い。美術館職員に女性が多いが、館長のほとんどが男性。2022年に『ジェンダーバランス白書』を発表。調査とアンケートで、数字による可視化が行われ、問題を語る土壌が作られた。」
すごい不均衡があったのです。みんななんとなく感じていたけど、やはり数字に出してみると歴然とした結果が出てきました。2019年に結構いろんなジェンダーをめぐる問題があって、その中で話題に上った1つに「あいちトリエンナーレ2019」があります。津田大介さんを芸術監督に迎え愛知で開催された芸術祭です。“トリエンナーレ”なので3年に1回、毎回行われていたのですけど、この2019年は参加アーティストの男女比がほぼ半々になるように設定されたことが、それまでとは異なっていました。本来驚くことではないと思うけど、今までは歴然として男性が多かったことや、東京医科大学が女子生徒の得点を不正操作したけ事件など、露骨な女性差別がある現状に向き合う形で2019年のこの芸術祭がなされました。同年のベネチアビエンナーレ、イタリアのベネチアで行われる国際的な芸術祭でも男女比が半々になったということです。2019年はアート界の中でもだいぶジェンダー問題が取り上げられたと思います。
展覧会という形ですと、「カナリアがさえずりを止めるとき」という2020年に行われた展覧会があります。広島で開催されたのですけど、広島もこの時、美術大学でのハラスメント問題が取り沙汰された時期でした。アート界に見られる著しいジェンダーアンバランスや相次ぐハラスメントに対して、展覧会という形で作家が声を上げました。また、「フェミニズムズ/FEMINISMS」という展覧会もありました。金沢21世紀美術館という大きな現代美術館でフェミニズムがメインの展覧会が開催されました。これも女性作家がきちんと採用されて出展していました。
コレクティブ、アートグループでは「ケルベロスセオリー」があります。今回、ゲストとして個人で話していただく山もといとみさんが所属するグループです。フェミニズム・アートコレクティブであり、クィアやフェミニズムの視点から「セーファー・スペース」としての展覧会を実践する活動を行っています。社会運動から生まれたセーファー・スペースの概念を、フェミニズムの文脈で実践し、保守的な価値観に抵抗する活動を通じて、多様な人が共存できる社会の実現を目指しているグループです。
ウェブで見つけた海外の事例ですが、“あなたたちがフォローするべき10人のトランスのアートクリエイター”という記事ではトランスのアーティストが10人紹介されています(ARTSPER MAGAGINE 2025/6/27)。また、同誌の2022年6月14日の記事には“私たちが愛する7人のLGBTQ+アーティスト”があり、面白い記事です。日本のコミュニティにいても海外のクィアなアーティストたちとつながれることはあまりないので、同じアイデンティティを持った人たちの活動を知れるという面では貴重です。
日本のウェブマガジンの事例では、“TOKYO ART BEAT”という有名なアート系のメディアがあります。2025年6月4日の記事に、「6月『プライド月間』を機に見たい、展覧会7選。アートを通じてセクシュアリティやジェンダーをめぐる多様な視点に触れる」というのがあります。でも、これは大半がゲイ男性といわれる人たちの展覧会で、インターセクショナルでなく、「それで本当に多様か?」という感じの内容ではありました。
これも海外で起きた出来事の記事ですけど、「トランプ政権下で問われる多様性の意義、アートが果たす役割とは」(alterna, 2025/8/26)ということで、ゲティ・センターという展覧会ができる有名な場所で、クィアの歴史作品をいろいろ展示していることが書かれた記事があります。“抵抗としてのアート”というものが、どう役割を果たすのか考えさせられます。
アーティスト・イン・レジデンス(AIR)について少し話していきたいと思います。AIRとは、国内外からアーティストを一定期間、招聘して滞在中の活動を支援する事業です。滞在期間は1ヶ月程度のものから3年程のものもあります。世界中で実施され1300件以上あるとされています。滞在先の家賃やスタジオ代、渡航費などが全部補助されるもので、若手のアーティストたちがアート活動を続けていくためには素晴らしい制度です。
でも、いろんな問題があると私は思っています。とくにトランスの人や持病があるアーティストは新しい土地で医療を受けるのが非常に困難で、長期間外に出ていくのが難しいという問題があります。それが日本国内であっても困難なのに、さらに海外に行ってしまうとなると、少し想像するだけで大変なことがわかります。なので、安全性もですけど、数が限られるクィアなアーティストたちがAIRを利用できるのか疑問です。
そんな中、2021年から始まったファイヤーアイランド・アーティストインレジデンスは、アメリカのニューヨークの島ですけど、世界初のLGBTQアーティスト・イン・レジデンスと言われています。世界中のクィアたちが集まってアート活動ができる。LGBTQの人たちが参加しやすいフレンドリーなレジデンスだと言われています。これまでレジデンスのことを知らなくて、今回調べて、こういうものがあるという事実に少し驚きました。
中島伽耶子さん) そんな感じで、私たち以外にもアートなどの表現で意思表明をしたり、活動を進めていたりという事例はあります。選挙に行く、パレードに参加するぐらいの一つの選択肢として、展覧会にも参加してみる、というように気軽な発表の場所として作っていけたらと思っています。
まず集まる、まず表明してみる。そこから話していけるのかなと思います。先程ご紹介した今年の11月に開催する「例えば展」もよかったら皆さん参加してみてください。

(「例えば『天気の話をするように痛みについて話せれば』2025」参加申し込みフォームのQRコード)
最後にもう一つの事例を紹介させてください。私と、今回ゲストで参加してくださっている美馬摩耶さんと山もといとみさんと、他のメンバーでやっているプロジェクト、クィアアートイベント「貝殻をあつめる、道路に線をのこす」を2025年10月17日から20日に開催します。京都のTARO HOUSEという京都駅から徒歩5分位のところにある面白いギャラリーでやります。そこでもクィア研究をしている方やノンバイナリーの研究している方たちを呼んで一緒にトークイベントもします。実践として、京都ですごくクィアなアートイベントやったらどうなるか、みたいなのをやろうと思っています。
前半でのお話はここまでにしようと思います。ありがとうございました。

( クィアアートイベント「貝殻をあつめる、道路に線をのこす」のInstagramのQRコード)
――グループ対話とグループ発表を経て、ゲストからのコメント――
※グループ対話を3セッション行いました。各グループでは、セッション毎に異なるゲストがアート作品を携えて交代で訪れ、作品の背景等をお話しした後に、それをきっかけに対話が行われました。その後、会場全体で共有するために印象に残ったことを各グループから発表いただき、ゲストからコメントをいただきました。
山もといとみさん) グループセッションでは、今日のこの時間で感じたことや思ったことについてお話を聞けてすごくよかったです。美術を中心にして考えているとなかなか出てこないような意見も聴けました。このように関わりあいの場に表現物があることの可能性を皆さんに感じていただけたのがすごいなあと思っていました。ありがとうございます。
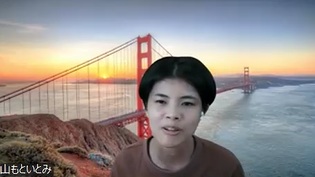
櫻井莉菜さん) 私はアートマネジメントを専門にしています。アートマネージャーということで、グループセッションでお話した内容はアーティストである他のゲストの皆さんとは結構違う内容になってしまったのではないかと心配していました。でも、各グループで、皆さんそれぞれの考えや活動の話とかを聴けて、私の方がとても勉強になりました。先ほどのグループ発表では、皆さんの感想もたくさん聞けて、きちんと受け止めてくださったというのが分かって、すごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。

美馬摩耶さん) グループセッションでは、気になる問題についても話せました。インドに住んでいたので、インドの社会と日本との違いについて、展示空間に誰が入れて誰が入れないかという話もできましたし、皆さんが考えていることを聞けてよかったなと思います。
私の作品を見て、皆さんそれぞれ違うことを意識されたことは面白かったです。感謝しています。

明戸隆浩さん) 最後、岩瀬さんと中島さんには、僕から少し気になったことで聞きたいことがあります。今回オンラインの形で、普段、展示スペースで話すのとはだいぶ違う感じだったと思いますが、そのあたり、どうでしょうか。
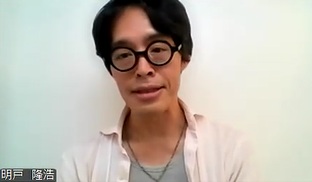
岩瀬海さん) 各グループセッションが20分間で、とても早いなと感じました。盛り上がってきた頃に終わり、みたいな感じだったので、もっと喋りたいなと思いました。
あと、来る層が違うというのもあります。オンラインか展示スペースか、でもそうですし、秋田と東京ということでも違います。今年の「例えば展」の会場は上野なので非常にアクセスが良くて、みなさん大体が知っている場所です。一方、秋田で実施すると場所を知っている人が限られていて、そこで展示をやっていることを知っている人もとても少ない中で行うので、いつも寂しい感じになります。ただ、そこに来てくれた人とは、非常に濃厚な話ができます。今回のオンラインの場もそういう場だったかなと思います。
グループセッションで一緒になった皆さんは何かしらアートというものに可能性を感じてくださっていました。私自身、アートの即効力のなさ――彫刻という私の表現形態は時間がかかってしまうことに対して、世の中の情勢は常に変化していること――にもどかしさを感じていたのですけど、今日、皆さんと話してみて、アートは遅くても、じわじわと長いスパンで考えるとやはり続けていきたいという気持ちが強くなりました。ありがとうございました。

中島伽耶子さん) 今回の展覧会の会場は東京藝大の敷地内なのでアートが好きな人がメインになるのかなと思う一方で、アートが好きだからといってトランスジェンダーの現状や差別の問題に関心がある人がどれだけいるかというと、そんなに多くない気もします。秋田で開催した時とは違う層が来るといいなとは思います。
世の中で何かを表現している人たちに、それが持ちえる暴力性や、自分が持っている危うさや加害性みたいなものがあることに気づいていただけるといいなと思います。
今日のグループセッションで会った皆さんも、自分で活動している人や実践をしている人が結構多かったので、これがきっかけで上野の藝大のtrunkの展覧会に行ってみるとか、何も作ったことないけれど少し関わってみようかなみたいな感じで、普段だったら交わらない層がつながると嬉しいなと思いながら皆さんのお話を聴いて聞いておりました。
あと、グループセッションの時間が20分間というのは難しいですね。これから、みたいなところで「後1分」と表示されてしまう。でも、20分で話せることは大したことではないかもしれないけれど、個人がいろいろ考えていく種をまけていたらいいなと思います。ありがとうございました。

明戸隆浩さん) はい、ありがとうございます。最後にオンラインと現場の違いについて聞いたのは、前半のお話の最後にもあったと思いますが、展示空間をつくることは、そうした空間をつくることによるリスクもありつつ、でもそこに実際に人が来るという意義もある。オンラインはその点物足りなく感じてしまうけれども、最後に中島さんが「種」と仰っていましたが、その時間内で全部が完結するわけではなくて、そこから何か新しく別のことにつながっていくことは絶対あると思います。それは意外と目に見えなくて、後から「実は…」とわかるような話だと思うけれど、そういう場に今日がなっていればいいなと思います。
今日の話は11月のtrunkの展覧会を控えた1つのステップでもあるので、今日もし関心を持っていただけたら、普段あまりアートの場に行かない方も、上野はアクセスもよくて週末に散歩しつつ寄れるところでもあると思うので、ぜひ展覧会を訪れていただければと思います。実際trunkの展覧会はアートに対する敷居を下げて、どれだけ広く発信していけるかがとても考えられていると思うので、いつもの秋田とは違う東京という場所で、うまく花開いていけるといいですね。
●次回SJFアドボカシーカフェのご案内★参加者募集★
『パレスチナの和平構築―紛争当事者の若者が主導する対話から―』
【日時】2025年9月27日(土)13:30~16:00
【詳細・お申込み】こちらから
※今回25年8月30日のアドボカシーカフェのご案内チラシはこちらから(ご参考)

