ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第91回開催報告
核のごみ処分問題における対話の可能性
―処分場の調査地域住民の声から共に考える―
2025年6月25日、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)は、三木信香さん(「子どもたちに核のゴミのない寿都を!町民の会」共同代表)、石丸初美さん(「核ゴミお断り!10万年先の子どもも守る九州の会」)、川﨑彩子さん(原子力資料情報室/Fridays For Future)、高野聡さん(原子力資料情報室/特定放射性廃棄物小委員会委員)を迎えてSJFアドボカシーカフェを開催しました。
核のごみ処分問題を考える際の7つの観点から、現状に対する肯定的意見と否定的意見が高野さんから解説されました。
その一つ、「世代間の公平性」を取り上げた若い世代の川﨑さんは、社会的に強い立場からの「若者や将来世代のため」という倫理的に聞こえる語りの先行は、批判的な思考の機会を奪う抑圧となり得ることを指摘しました。実際は、若者に意思決定権がなく、権力者による決定への理解を醸成するために利用されている構造が浮き彫りにされました。それは、三木さんや石丸さんたち市民が「子どものため」を願ってよりよい社会に向けて取り組まれているのとは全く異なることも若者は気づいています。
核ごみの最終処分場候補地における文献調査について、現地住民と国や事業者(NUMO)との「対話を行う場」や「対話の場」は対話になっていない住民説明会だと石丸さんや三木さんは実態を話し、住民を守りながらも自由な対話ができる開かれた場にすることを考える必要があると問題提起しました。
北海道寿都町では、賛成派と慎重派が共に対話できる機会を設けることが難しいなか多くの住民が静かな分断に苦しんでおり、文献調査に手を挙げた寿都町長も国やNUMOに実質的には押し付けられたのだろうと思うようになったと三木さんは語り、核のゴミ処分の問題が全国民の問題となるような最終処分法の建付けにするべきだと提言されました。
佐賀県玄海町では、国からの申し入れを町長が受け入れる形で文献調査が開始され、住民に知らされてから十分な説明や議論の機会がなく非常な早さで進んだことを石丸さんは報告し、それでも「一人でもいいから伝えたい座談会」を自ら開き続け、参加者が自由に発言できる場をつくってきたところ、遠方から率先して修学旅行で話を聴きに来た中学生との出会いもあったことが語られました。
国やNUMOが主導した寿都町の「対話の場」を検証する報告書を北海道市民が作成し、特定放射性廃棄物小委員会に送付、経済産業省に質問し、そこには「私たちが思う『真の対話』とはこうだ」といったことも提示されていると高野さんは紹介し、諦めずに活動を続けて起こせた小さな変化は、みんなで注目すれば大きな成果になると希望を表しました。
詳しくは以下をご覧ください。 ※コーディネーターは佐々木貴子(SJF運営委員)
 (写真=パネル対話:上左から時計回りで川﨑彩子さん,高野聡さん,石丸初美さん,佐々木貴子さん,三木信香さん)
(写真=パネル対話:上左から時計回りで川﨑彩子さん,高野聡さん,石丸初美さん,佐々木貴子さん,三木信香さん)
目次
——高野聡さんの基調講演:「核のごみ問題のよりよい対話に向けて考えておきたいこと」——
今日の講演の趣旨から説明したいと思います。私は普段は脱原発の立場で活動しており、核のゴミについても、この地層処分は現在の科学的知見では安全性は確保されていないために実施すべきではないという立場です。しかし、今回の講演では、その私の考えを説明するのではなく、この問題について広く深く議論するために考えておいたほうがいい論点を紹介することに重点を置くことを、まずご了承いただきたいと思います。
自己紹介を簡単にします。原発反対の民間研究機関である原子力資料情報室で活動しています。また、経済産業省の審議会である特定放射性廃棄物小委員会の委員もしており、政府でどのような議論が行われているのか、もし関心のある方がいらっしゃれば、後の質疑応答の時間に聞いていただければと思います。
まず基礎知識から入りたいと思います。原発の運転によってゴミが出るということは皆さんご存知かと思いますけれども、その中で、非常に放射線量の高いものと低いものがあり、高レベルと低レベルで分かれています。今回、この高レベル放射性廃棄物に関する話をします。法律用語では、第一種の特定放射性廃棄物となります。また、福島原発事故由来の、例えばデブリと呼ばれる溶け落ちた核燃料棒というのも処分しなければ今後ならないのですけれども、この第一種特定放射性廃棄物という法律の枠組みには入っていないので、今回は扱わない形になります。
原発の運転によって使用済み核燃料が発生し、巨大なプールで冷却保存されています。これは高レベル放射性廃棄物ですが、これを核のゴミと思っていらっしゃる方がいると思いますけれども、日本の少なくとも法律の建付けではそうなっていない。なぜなら、再処理というものをするからです。この使用済み核燃料の中にある、わずかなプルトニウムを取り出して燃料として再利用する。その過程で発生する高レベル放射性廃液をガラスで混ぜてステンレス容器に入れる。これをガラス固化体といい、これが日本でいう高レベル放射性廃棄物となっています。
このガラス固化体ですけれども、製造直後はものすごい高線量の放射線を放ちます。そばにいるだけで、たった20秒ぐらいで死んでしまう強さです。このガラス固化体は現在2500本ぐらいあり、青森県の六ヶ所村の地上施設に保管されています。これは2045年までに青森県外に搬出することが約束になっています。
これはどれくらいの分量があるのか、その規模感についても確認しておくと、現在の使用済み核燃料を日本政府はすべて再処理する方針で、そうするとだいたい2万7000分本ぐらいのガラス固化体が更に発生する、つまり現在の10倍以上が新たに発生することになります。最終処分場には約4万本のガラス固化体を処分予定で、そういう容量のある施設が全国に1カ所造られようとしています。
再処理の過程では、それ以外にも、TRU廃棄物という低レベルの放射性廃棄物も出てきます。これらも最終処分場で処分されます。
現在、再処理前の使用済み核燃料がどんどん溜まり続けてしまっています。現在1万9000トンぐらいの使用済み核燃料があり、各原発サイトに保管されていて、貯蔵容量全体のもう80%ぐらいが埋まってしまっている状況です。六ヶ所村に再処理工場があるとはいえ、実はまだ完成していません。福島原発事故以降に厳しくなった安全基準を満たすことが今後もおそらく難しいということで、なかなか稼働の見通しがたっていません。その間はずっと貯蔵施設に溜まり続けていて廃棄ができないので、空きをつくるために、青森県むつ市に中間貯蔵施設という原発サイト外にある使用済み核燃料の貯蔵施設が造られて稼働しており、山口県上関町でも現在その建設のための調査が実施されています。
使用済み核燃料を再処理した核のゴミの処分方法は、現在の日本では地層処分という方法が計画されています。地下だいたい300から500メートルのところに埋めて捨てる形です。先述のガラス固化体を鋼鉄でくるみ、さらに粘土質のものでくるむ。これが人工バリアと呼ばれています。その後、地下奥深くの岩盤で放射性物質を閉じ込め、こちらは天然バリアと呼ばれていて、これら多重のバリアシステムになっているということです。1999年の政府関連の技術報告書では、日本でも地層処分の技術基盤が整備されたとなっています。
このように厳重に処分しないといけない理由は、自然のウラン鉱石のレベルに放射能レベルが低下するまでの10万年間ぐらい人間の生活圏から隔離しないといけないという、天文学的な期間の管理をしないといけないからということになっています。
地下施設のイメージとしては、地下300メートル以深のところに縦横3㎞×3kmぐらいの施設を造り、総延長が200キロぐらいの坑道がある形になります。
日本政府は、先述の天然バリアがある理想的な地下環境が日本でどこにあるのかを示す地図、科学的特性マップを2017年に作りました。これは逆に言えば、放射性物質をあまり閉じ込められない好ましくない地下環境を示して、それ以外のところだったら比較的OKだという発想で作られております。好ましくないところは例えば火山や断層、地震活動や隆起・侵食のあるところ等で大体30%あり、それ以外では地下資源があるところも人類が今後掘ってしまうかもしれないから好ましくないとされていて5%ぐらいあり、これらが色分けして示されています。なので、残りの65%ぐらいが、相対的に好ましいのではないかという形で色分けされています。
地層処分事業の全体プロセスについては、処分場の建設の前に3段階の調査プロセス、文献調査・概要調査・精密調査があり、それらに20年ぐらいかかるということです。日本の特徴として、調査を受け入れた自体体には交付金というものが後でいいのですけども交付されます。そして、処分場の建設で10年程度、実際の処分場の操業と閉鎖で50年以上ということで、事業全体では大体100年以上かかるということで、非常に息の長い事業になります。
政策の推進の体系ですけれども、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(最終処分法)が2000年に制定されて、経済産業省が政策の基本方針を作成・公表し、それに基づいて推進する形になっています。
事業者は別途、NUMO(ニューモ)という組織があります。このスタッフの多くが電力会社からの出向社員で、資金においてはもう100%電力会社からの拠出金なので、ほぼ電力会社と見ておいていいと思います。
以上、前提となる知識を確認しました。
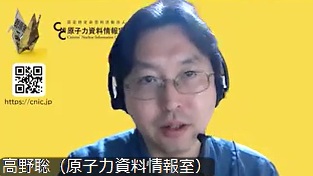
核のごみ問題を考える7つのポイント 現状に対する肯定的意見と否定的意見
では、この問題をどういう観点から考えたらいいのか。私が考える7つのポイントを挙げていきます。それぞれについて、現状を説明した後、その現状に対する肯定的意見と否定的意見という形で、お話ししたいと思います。
① 世代間の公平性
現状は、核のゴミの最終処分政策に関する基本方針は経産省が定めるのですが、この基本方針には、「原発を利用し、核のごみを発生させた現世代の責任として将来世代に負担を先送りにしないよう、その対策を進めることが不可欠である」と書かれているのです。
これに対する肯定的な意見としては、世代間倫理、世代間の負担の公平性の観点から正しい。処分の先送りは無責任ですし、地層処分の安全性も確保されているのだから、処分したほうが安全。
それに対して否定的な意見としては、核のゴミが既にあるというのは認めるけど、だからすぐ処分場を探さないといけないということではない。長期保管の選択肢――いわゆる”wait and see”、事態をしばらく見据える形――もある。先送りにするなという聞こえのいい号令によって、すぐ処分場を探さないといけないという現行の政策の枠組みを十分に検証せずに前提として考えてしまう危険性もある。地層処分の安全性が確保されていないので、後世に取りかえしのつかない被害が及んでしまうことを考慮し、決定権を後世に残すことも公正で倫理的であり得るという考え方です。
② 地層処分の安全性
地層処分は、現状では最終処分法の第二条に規定されている処分法です。
肯定的な意見としては、もうこれは最適な処分方法だというのが世界的な認識だし、日本でも技術基盤が整備されている。
否定的な意見としては、日本では専門家の間でも合意が取れていない。なぜなら、4つのプレートがぶつかり合うという非常に特殊な地下環境がある日本で、具体的には2023年の10月に地殻研究者300人が現在の科学的な水準や知見では地層処分が安全なところを探すことができない、というような声明も出している。重要なことは、先述の技術報告書や科学的特性マップなど地層処分の重要な意思決定には、地層処分に反対・懐疑派の専門家が排除されていて、原発安全神話と同じような構造で、都合の悪いことを政府は聞かないで意思決定しているのではないか。
③ 最終処分法の目的
現状の最終処分法の目的は第一条に書かれていて、「発電に関する原子力の適正な利用に資するため、(中略)発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与すること」です。要するに、原発の今後の継続的な利用をスムーズにするための環境整備として最終処分場を探すということです。
肯定的な意見としては、資源の少ない日本では、原発はエネルギー安全保障に役立つことは明白。その推進に資するので問題ない。
否定的な意見としては、国民の合意を取れていない。規制と推進の分離が、そういう建付けではできにくくなってしまう。例えば、原発推進の機関でもある日本原子力文化財団が、毎年同じ質問で世論調査をしている。「今後の原発の利用についてどう思うか」という問いに対する結果では、「即時廃止」と「徐々に廃止」がだんだん減少していると図示されているが、現在でも45%ぐらいを占めていて、「増加」や「維持」は18%ぐらいなのに比べると多い意見になっている。
④ 交付金
次の論点は、交付金についてです。敬意と感謝の形として交付金を交付すると基本方針(特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針)に書かれているのです。「事業の実現が社会全体の利益であるとの認識に基づき、その実現に貢献する地域に対し、敬意や感謝の念を持つとともに、社会として適切に利益を還元していく必要があるとの認識が、広く国民に共有されることが重要である」と。
肯定的意見としては、いわゆるNIMBY(ニンビー;Not In My Back Yard)の事業で、最終処分施設の必要性は理解するけれども私の裏庭・私たち地域ではやってほしくないという性格が強く、困難な課題の解決に貢献するので敬意と感謝、利益の還元の具体的な形として交付金は必要。交付金は地方財政を豊かにし、地域経済の発展に寄与する。
否定的な意見としては、事業の目的はそのような形では合意されていないし、交付金の地域経済への効果は限定的で、むしろ原発交付金への依存体質を生んでしまって、住民自治をないがしろにする。原発関連施設の立地自治体の地域財政と人口の動態のデータによると、財政力指数は、どれほど財政力があるか・健全かを示す数値ですけれども、全国平均あるいはその自治体の広域自治体よりは上回っていて、地域財政に貢献する効果はあるだろう。しかし、人口流出についてはどうかというと、人口の変化のデータによると、流出の抑制効果はほとんどの地域で無い。また、住民の所得も、周辺自治体より高い傾向にあるわけではない。
⑤ 原発推進組織による社会的議論の推進
現状では、最終処分法の目的が先述のような形になっているので、経産省・NUMO・電力会社という原発推進組織が社会的議論を主導するということで、例えば対話型全国説明会のようなことを全国的に行っています。
肯定的な意見としては、政策の目的はもう合意済みだし、地層処分への理解が足りないために反対や拒否している市民が多いので丁寧な説明や理解の醸成を、事業者が主体的に行えばいい。
否定的な意見としては、核のゴミがこれから発生することをどれくらい社会として許容するのかという総量規制や、使用済み核燃料の再処理を止めてそのまま直接処分するとか、原発推進ではない政策オプションがあるけれども、それは議論しないということなので政策変更の可能性が排除されてしまっている。また、直接処分に関しては、最終処分政策の前提となっている核燃料サイクルが六ケ所再処理工場はずっと動いていなくて、それだけで既に現在の核燃料サイクルは破綻していると言っていい。この現状で議論を進めていっていいのか、そこから話し合わないといけないのではないか。 あと、市民は理解不足というよりも、むしろ必要なのは、政策プロセスの中に主体的な意思決定ができる参加を保障することだ。
⑥ 若者世代をターゲットにした広報活動
例えば、高校生や大学生をターゲットにしたり、あるいは経産省主催のシンポジウムで影響力のある若者、インフルエンサーを参加させたりしています。
肯定的な意見としては、SDGsに示された「11.住み続けられるまちづくりを」という理念に沿う。
否定的な意見としては、広報に過ぎないのに、学生が何か教育活動だと思って参加することが果たして健全なのか。実際、イベントの参加者の発言例として、寿都の高校生や大学生が六ヶ所村に関して「自分たちの手で生きていく町を作るという信念と主体的な姿に感銘を受けた」と言ったり、あるいはシンポジウムの登壇者が「処分場を受け入れることにリスペクトするし、かっこいいと考える若者が増えている。受け入れれば結果としてチャンスが増える」と言ったりしている。しかし、原発推進事業者にとって都合のいい発言しか出てきていないというのが現実ではないか。
⑦ 交付金付与+自治体手上げ方式で始まる文献調査
調査の開始は、首長が応募するか、あるいは国が申し入れをしてそれを首長が受け入れるか、この2つのパターンです。そして交付金が落ちるという形になっております。
肯定的な意見としては、最終処分場の意義を十分理解してくれた自治体に、何らかの形で還元するのは当然だ。
否定的な意見としては、この20億円の交付金を魅力的に感じてしまうのは、貧しい自治体と財政的に苦しい小さな自治体であり、結果的にそういう自治体がターゲットになってしまうのではないか。地域の問題に矮小化されてしまう。あるいは、交付金につられた首長や一部の有力者が住民の意思を無視して強引に応募に走ることによって、地域分断が引き起こされる可能性があるのではないか。
市民参加が保障された第三者機関が、国や事業者による調査候補地の選定プロセスを監視するドイツ
実際、静かな分断が起きてしまっていると感じています。寿都町や玄海町に関しては、この後お話していただけると思いますが、住民への説明が不十分で非常に短い時間で決まってしまったということです。
先述の交付金の手上げ方式、これは止めた方がいいと、実際に応募した寿都の片岡町長も言っているし、国の申し入れを受け入れた玄海の脇山町長も言い出していて、政策見直しの雰囲気が盛り上がっているようです。
注意しないといけないのは、現行の政策の枠組みを維持したまま進めてはいけないのではないか、という政策を提言した報告書が2012年、日本学術会議から出されていることです。これは、従来の政策を見直せとか、地層処分に批判的な科学者も入れてもっと議論しろとか、お金で釣るような選定手続きはやめろとか、いろいろ提言しております。議論を組織する体系も、原発推進の機関に任せてはいけないということで、合意形成に向けた第三者機関が提言されています。
ドイツの事例について最後少しだけ言いますと、ドイツは国が主導していているのですが、国や事業者による調査候補地の選定プロセスを非常に強い権限を持つ第三者機関が監視しています。この機関はNBG(国民参加諮問機関)といって、市民参加が保証されていて、委員18人のうち6名が市民という形で、国の担当官庁や事業者に対していつでも相談可能で意見を述べられます。そのような外国の事例も参考になると思います。
——三木信香さんのお話——
こんにちは、私は今、寿都町から参加させていただいています。町民と賛同人と弁護士さんなどを含めて43名で、「子どもたちに核のゴミのない寿都を!町民の会」という会の活動をさせていただいています。共同代表です。
私たちは、2020年にこの話が出た時に、文献調査に応募することに反対する署名を集めるために町民が集まった会なので、誰1人として元々活動家だったという方はいらっしゃらず、30代から70代の町民で結成しています。長く続いていて、本当は文献調査に反対の署名を町長に出したら、もうそこで終わりだと私は思っていたのです。未だに町の中は静かなふうを装っていますけど、中身はもうぐちゃぐちゃになっている感じがしています。
私は寿都出身ではないのですけど、娘が2歳の時に札幌から引っ越してきて、現在寿都に住んでいます。
2020年8月13日、お盆で朝からそわそわしているなと思ったら、ヘリコプターがすごく飛んでいて、町の中はテレビ局の車が走り回っていて、なんか事故か事件かなと思ったのです。そして、私は娘とパン屋にパンを買いに行ったら、UHB(北海道文化放送)のテレビ局の人にパン屋の端まで追いやられて、いきなり「核のゴミの最終処分場は必要だと思いますか?」と聞かれたのです。今では反省しているのですけど、原発の「げ」の字もわからないただの普通の町民で、とにかくその場を早く去りたくて曖昧なまま「危険じゃなかったら必要だと思います」と言ってパン屋を出たのです。そうしたら、そのすぐ後のYahoo!ニュースで、寿都町に処分場ありきの話になっていて、いかにも私が賛成派のような感じでテレビに流れていて、周りの友達に「大変なこと言っちゃったね」と言われました。
そこからいろいろ勉強をし始めました。「ああ、大変なことを言っちゃった。これはなんとかしなきゃ」という思いがその時はあったんだと思っています。「まず、できることから」と思って、文献調査に反対の署名を集めました。町内は今2600人ぐらいですけど、当時800枚ぐらいチラシを作成して、子どもに関わることなのでママ友に協力をまずお願いしようと思って行動したのですけど、もう既にその時からしがらみや分断があって、旦那が役場だからとか、文献調査に反対だけど建設業の旦那さんを持つ人とかに断られました。それで、ママ友はもうダメだと思って、その当時夫がやっていた魚の仲買人のメンバーと一緒に反対の署名を集めて提出したのが、私たちの会の始まりです。
その後、会としては、住民投票条例制定請求の署名提出や、議会での意見陳述、核抜き条例(寿都町に放射性物質等を持ち込ませない条例)の要望書を提出、寿都町議会全員協議会の議事録の公開に向けた行政訴訟を行ってきました。その他、慎重派の先生を呼んだ勉強会、イベント、議会の傍聴、町民との対話の場づくり、チラシ発行なども行っています。チラシは今、2ヶ月に一回のペースで会員で作っていて、全戸配布しています。

賛成派と慎重派の両方が集える場を
私は賛成派の人の意見も最初の頃からずっと聞きたいと思っていて、自分が知らないことがもっとあるのではないかと思って、そういう対話の場づくりにも挑戦してみたのですけど、私たちの会が主催するイベントは「反対の人たちの集まりでしょう」と言われて、集まるのは私たちと同じ立場の反対のメンバーしかいなくて、賛成派の人の意見はなかなか聞けなかったのです。
いまだにそうなのですけど、最終処分場を本気で考えている人は今、寿都町には多分いないと思います。本当にお金だけ、今だけの考えの人しかいないというのが、なんとなくわかる感じです。
文献調査の報告書案できるまでは、町長は一切勉強会を何も開かなかったのです。私たちは賛成派と慎重派の両方の先生を呼んでイベントを開催してくれることを望んでいたのですけど、そういう動きが全くなく、私たちが企画するイベントにも町長は一切参加しなかったです。その報告書案ができてからは今までシンポジウムが4回ありました。その後、町内の会館8カ所ぐらいで勉強会が開かれました。その場で初めて町長が町民と向き合って話をできる機会があったのです。
最終処分場の文献調査に手を挙げた町長も実質は国やNUMOに押し付けられたのでは 寿都町だけが苦しむのではなく全国民の問題となるような最終処分法の建付けに
片岡町長は、最初は自分の肌感覚で手を上げていたのに、最近は「手挙げ方式は止めたほうがいい」とか、「それが間違いで、町民のみんなに迷惑をかけてしまう」とか、そういう言葉を口に出すようになりました。
ただ、私たちは結構今まで騙されてきているので町長のその言葉が本心なのかどうかは未だわからないですけど、私も最初は「片岡町長がお金欲しさに手を挙げて、寿都町民として恥ずかしい」と思っていたのですけど、結局「国やNUMOに押し付けられているんじゃないか」とだんだん思ってきて、「片岡町長すら騙されているんじゃないか」と思うようになってきたのです。
やはり他に手を挙げるところもなくて話だけいろいろ進んでいきますけど、この間に国やNUMOの人は誰も寿都に来ていません。これだけ分断したり問題になったりしているのにもかかわらず、多分それも知っていると思うのですけど、ほったらかしです。それで、町民だけが揉めている状況です。隣で昨日まで挨拶していた人とそれを機にもう顔を合わせることすら辛くなったりしました。だから最初は町長を恨んでいましたけど、今は本当に「国やNUMOの人たちにもっと考えてほしい」という思いがすごく強くなりました。
特定放射性廃棄物小委員会には高野さんも出ていらっしゃるのですけど、その3回目のYouTubeを見た時に、あまりにも委員の皆さんが他人事というか、「真面目に考えて本当にその答えですか」と思いました。私たちはその前に勉強会とかに出ていたのでNUMOのインタビューを仲間5人で受けたのです。それはNUMOに協力したかったわけではなくて、寿都町でこんな苦しいことが起きているということを皆さんにお伝えしたくて協力したのですけど、結局、私たち反対派の意見は全く出ないでYouTubeに流されていたのです。そのYouTubeを見て、ひどすぎるということで意見書を出しました。 そうしたら、その3カ月後にやっとNUMOの理事の方が寿都に来て、形だけかもしれないけど、謝罪したのです。ちゃんとそういうお話ができたのは、それが初めてでした。
本当に、昨日まで仲のよかった町民がこんなにも仲が悪くなるのか、というのはどこの町でも起きる可能性は絶対あると思うのです。なので、この問題は私たち寿都町民だけが苦しむことではなく、押し付けられることでもないと思っていますが、最終処分法の建付けはそのようになっているという現実があります。でも、国民のお金を使うことですし、全国民の問題だと思います。国側の考え方や進め方を今以上に確認や整理をして、調査や議論をもっとしていってほしいと思っています。
私たちはこれから住民投票と新しく町長選挙があります。前回は反対派の方が200票差で負けてしまいましたけど、やっぱり町長が変わらないとダメなのかなという思いがあります。私たちと考えが同じ立場の方が出馬を考えていて、もし勝てれば何か変わるのかなと期待しつつ、私たちは生活も仕事もありますし、子育てもしなきゃないしで、やることがたくさんあって思い通りに活動はできないですけど、今まで続けてこられたので、これからも細くでも長く、絶対負けないような活動をしていこうと思っています。
今日、話を聴いていただけた皆さんには、寿都町で町民だけでこんなに頑張っている会があるということを誰かお一人でもいいので伝えていただいて、皆さんに知っていただけたらありがたいと思います。
——石丸初美さんのお話:
「玄海町/住民は何が起きているのか知らされないまま『文献調査開始』」——
みなさん、こんにちは。佐賀県の玄海町は今何が起きているのか分からないまま文献調査が始まっています。私は「核ゴミお断り!10万年先の子どもも守る会・九州」で活動しています。玄海町は原発立地の町なので、核ゴミの問題があがっても声を上げることがなかなか難しい地域です。原発問題が浮上した当時(昭和40年)から長い間、反原発の声を挙げてきた住民はおられます。しかし高齢化して、私が知る限りではお世話になっている80代と90代のお2人だけです。今回の核ごみ文献調査問題については、このお二人と一緒に相談しながら近隣住民の私たちも一緒になって、反原発の皆さんに声かけて取り組むことにしました。
佐賀県玄海町で最終処分場の文献調査の実行にいたったプロセス
玄海町には原発があり、1・2号機は廃炉が決定、3・4号機が動いています。3号機は、2009年から国内で初めて運転されたプルサーマルです。それを機に私たちは運動を立ち上げ、裁判運動へと続いています。玄海原発は通常運転時、トリチウムの量が国内で最も多く放出されております。それと玄海原発は北部九州の西側に位置するため偏西風の影響を受け、事故が起きれば被爆は日本全域に拡散するリスクが非常に高い場所立っております。
そして玄海町は今回、文献調査を受け入れた自治体です。2024年の5月10日、脇山玄海町長は文献調査を受け入れました。「お金目的ではありません」と言って受け入れました。今回の文献調査は、旅館組合・飲食業組合・建設業組合の3団体の請願を受けてスタートしましたが、3つの請願は、「原発の立地場所の安全確認」、「文献調査で過去のデータをもとに地域防災計画にとって重要である」との受入れ理由となっています。最終処分場が目的ではありません。それで、この件について玄海町議員から「最終処分場の建設を目的としない応募は法に反する可能性はないのか」、「極端に言えば詐欺みたいなことに当たらないのか」と、去年特別委の場で経産省とNUOMに対し質問がありました(2024年4月17日)。国の回答は「国は法に触れるようなことを決定することはしません。決定されたということは法に触れない」と回答しました。
こうして去年の1月からの大変な半年間でした。文献調査が実行されるまでの経緯を一覧表で示します。
・2024年1~3月 旅館組合、飲食業組合、防災対策協議会(建設業)から請願書提出
・4月4日 文献調査受入を求める請願書を町議会に提出、受理される。
・4月15日 原子力対策特別委員会(特別委)に「3つの請願」が付託され表面化 (報道機関も一般住民もこの時から知ることになった)
・4月17日 1回目特別委で「文献調査請願審査」資源エネ庁、NUMO担当者4名参考人召致され、説明と質疑があった。
・4月25日 2回目特別委で「文献調査請願を6対3で採択」
・4月26日 玄海町本会議で「文献調査請願6対3で採決」
・5月1日 国(経済産業省)が、玄海町へ申し入れをするために訪問
・5月7日 脇山玄海町長・経産省を訪れ斎藤健経済産業大臣と会談。「大臣から『文献調査から最終処分場に直結するわけではない』と言質をいただいた」と三日後の受入れ表明
・5月10日 脇山町長、核ゴミ最終処分場文献調査決める
・5月27日 記者会見で脇山町長は「本当は文献調査に手を挙げたくなかった」と信じがたい発言
・6月10日 2年間の文献調査が開始される
6月10日、2年間の文献調査が開始され進行中です。4月15日に表面化してから、住民に説明もしないまま、1カ月もたたないうちに猛スピードで5月10日に決定されました。私たちには突如湧いてきた話で緊急の抗議行動をみんなで決めて、署名集めをして要請書を出すことになり、5日間で10,582筆と53団体の署名を添えて提出しました。
さらに、町民の生の声を聞こうということで、直接電話かけしてアンケートをとることにしました。NTT登録の玄海町民824件に電話をかけて、111人がアンケートに答えてくれました。結果、「住民に知らされていません」という方が80%、「わからない」という方19%、合わせて99%の人たちがほとんど知らなかった状態で勝手に決められていることがわかりました。また、「最終処分場を作るなんて絶対に反対」といった怒りの声が電話で届きました。こういった住民の声を無視した文献調査であることには間違いありません。
実は、文献調査の問題が明るみになる4年前(2020年)から、玄海町議会では文献調査問題が議論されていたことが後で分かりました。寿都町や神恵内村の文献調査がスタート(2020年11月)した翌月(2020年12月)から玄海町議会で議論されていました。当時10名いた議員のうち8名が文献調査を受け入れるべきだと表明していたそうです。

住民と国・事業者の「対話を行う場」 住民を守りながらも自由な対話ができる開かれた説明会には?
2024年6月に文献調査が始まってから1年間、何も説明はなかったのですが、ここに来てやっと一回目の「対話を行う場」という説明会を開くチラシが住民の方に撒かれました。そのチラシには、「地層処分の賛否を議論する場ではなく、皆さまの素朴な疑問や不安について意見交換し、関心を深めていただければと思います」と書かれていました。この対話を行う場には、応募人数は町民5名、区長・各種組織団体から15名、合わせて20名で、3カ月に一度の割合で行うという話です。今、文献調査が始まって1年が過ぎたので、あと1年しかありません。対話を行う場は3カ月に一度だというので、あと4回か5回しかないはずで、いったいどれだけの住民に説明するつもりなのかと疑問です。
この対話を行う場のプログラムは、開会(事務局からの報告など:公開)15分、参加者紹介(非公開)10分、文献調査の概要(NUMO説明:公開)40分、参加者によるグループ討議(非公開)25分、そしてグループ意見発表と質疑応答(非公開)25分となっています。住民の傍聴は当然できず、マスコミだけは入れるのですが、非公開の部分はマスコミも退出しないといけないという状況です。
異常なまでの報道陣への対応だなと思ったのでマスコミの方に聞いたところ、非公開の時間は報道陣は報道陣特別室から出ないようにということだったそうです。理由は「この対話を行う場は市役所の閉館時間に貸していただいているので不必要に動き回らないでほしい」という要望だったそうです。トイレも職員に声をかけなければならない感じだったという話でした。
参加者が帰った後、報道陣に対してファシリテーターから対話を行う場の内容について説明があったそうです。
この会の挨拶の時に、NUMO玄海交流センター所長の橋口久徳氏の話があり、そこでも「賛否を問わない形で意見交換をしていただければ」ということを言っていました(動画配信による)。また、経産省課長の横手広樹氏が話した言葉が、「原子力発電所を利用してきている以上、避けては通れない課題です。現世代への責任です。2000年から最終処分については取り組んできたが、背景にはNIMBY問題があり、処分場が必要であることは分かりますが自分のところではやめてくれといった話になりがちな課題(動画配信による)」という趣旨でした。とてもひどいなと思います。自由に議論してくれと言いながら、住民に自由な発言を妨げるような挨拶だと思います。
「対話を行う場」を非公開にする理由として「活発な議論ができるように、プライバシーを守るために、住民を守るために」というのです。このような理由を非公開の盾としていること自体が問題ではないかと思います。開かれた説明会をどうすればできるのか、住民をどうしたら守れるのか、自由な討議はどうすればできるのか、これを本気で考えなければならないのではないでしょうか。地元住民はもとより、近隣自治体、ひいては国民全体の問題としなければならない重大な問題です。公開の場で賛否両論の専門家を交えて時間を取って、国民に説明してもらいたいと思います。
今年の4月7日と6月20日、文献調査についてNUMOと実行委員会に質問要請書を提出しました。 次の概要調査に進むには、県知事の同意が必要ですが、佐賀県の山口知事は「新たな負担を受け入れる考えはない」と言っていますが、本当にそうなのか疑問です。
北海道新聞の2020年9月6日の誌面には、経産省に取材した記事があり、「知事反対でも(最終処分場の候補地から)除外せず」「文献調査をした実績は残る。国は首長の翻意など情勢が変化することも想定し、時間をかけて調査継続への理解を求めていく方針だ」と言っています。
また、2000年5月10日の第147回国会、衆議院商工委員会第17号という議事録ですけど、最終処分法を決めた議論の場について、横路委員が「(知事や町長が)反対してもやるということですか」と質問したときに、深谷国務大臣が、「管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞いて、これを極めて重く受け止めて、最終的には国が決定するものだ、そういう規定であります」と言っています。
これまで活動の中で、何度も要請書を提出してきました。しかし、納得いかない回答ばかりです。誰が責任をとるのか大事なことはあいまいな言葉を繰り返すだけです。私たちは法律を調べる術を持ちません。たまに調べて結果を得ることもありますが、法律の隅に責任のたらいまわしのような文章が書いてあります。知らされていないことばかりが原発問題です。
10万年も人の暮らしから隔離し管理が必要な危険な核廃棄物は、まずこれ以上増やしてはならないのが国と電力会社が最優先で取り掛かるべき問題です。私たちは、地震国日本では全ての原発は一刻も早く廃炉にし、安心できる社会を次の世代に渡したいと願っています。今後とも原発を止めるために、みんなで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
——川﨑彩子さんからのお話——
よろしくお願いいたします。私は東京から参加しております。今年の4月から、原子力資料情報室のスタッフとして活動しています。
これまで気候変動の解決や気候正義のことを中心に活動をしてきました。学生の時から活動している中で、どうして原発の問題についても活動しようと思ったのかというと、さまざまな問題が不公正なことを生み出しているという共通点があることに気づいたからです。
「気候正義」という言葉を出しましたが、気候変動というのは社会格差に強く結びついている問題です。温室効果ガスをより排出していない人、社会的に弱い立場に置かれている人に真っ先により大きな影響を与える問題です。これは原発のことでも、東京より地方の方々に先にしわ寄せが行ってしまっている構造と共通していると考えています。そのため、政策決定プロセスにおいて、公正であるということがとても重要です。

「若者や将来世代のため」という一見倫理的な語りの先行は、批判的な思考機会を奪う抑圧
若者に実際は意思決定権が無く、権力者の決定への理解を醸成するために利用されている構造
さまざまな不公正の中でも、「世代間の不公正」ということを私からは取り上げたいと思います。温暖化の問題で言うと、後に生まれた世代の人ほど生涯にわたってより深刻な環境の中で過ごさなければならないことです。
核ゴミの問題の中で、私が問題意識と感じていることを、ここから話したいと思います。NUMOや経産省のプロジェクトとして、若者世代をターゲットにした広報活動があると高野さんから紹介されました。その広報活動というのが、事業者側のNUMOの広報になってしまっている。核ゴミの問題をいろんな角度から理解するのではなく、広報になってしまっているということ以上にもっと根深い問題が「世代間の不公正」の観点からあるのではないかと私は考えています。
まずは先ほど石丸さんのお話にあった、「地域のために」、「プライバシーのために」、議論を非公開にすることは良くないということにも共通するかなと感じました。
この核ゴミの問題を「後回しにしてはいけない」、「次世代に今の世代が責任を持って行うべき」という一見とても倫理的な語りが先行していて、次の世代にいい環境を残すべきという考え方自体は、多くの人が否定しづらいものだと思います。ですが、それが覆い隠してしまうものがいろいろあるのではないかと思っています。特に若者の世代にとっては「あなたたちの世代のために必要だ」というメッセージになってしまうことによって、批判的に考える機会を奪ってしまうのではないかと感じました。
それから、「将来世代のため」、「若者のため」という建付けでありながら、若者は意思決定権を実際は持っていなく、理解醸成のターゲットにされてしまうことがあります。その根底には、若者はまだ考えることができないだろうという差別的な意識や、特定の政策によってみんなの環境が改善できるという考え方があるのではないかと思います。このように、「若者や将来世代のため」というフレーズが、その世代の意見を聞くということの必要性を覆い隠していて、意思決定権における公正さが失われていると考えています。
こういった構造は、核ゴミの問題以外にも見られていると思います。例えば、「生まれてくる子どもがかわいそうだから、夫婦別姓は実現されるべきではない」とか、「子どもたちを守るため、性的マイノリティの権利を認めすぎるのはよくない」――これは事実としてではなく、そういった言説があることを紹介しているだけですけど――。あとは、「18歳未満は保護される対象であるべきだから、選挙運動をする権利は認められない」とか。
そういった世代間倫理や「誰々のため」という考え方を、社会的に強い立場にある、核ゴミの問題で言えばNUMOなどの事業者が利用することによって、若者や将来世代が権力者によって政策等の正当化のために利用されている現状がある、というのが私の問題意識です。運営上、いくら対話なるものが行われるとしても、このような無意識的な抑圧が指摘されない限りは、本当の意味での対話は難しいのではないかと考えています。
—パネル対話(三木信香さん、石丸初美さん、川﨑彩子さん、高野聡さん、佐々木貴子さん)—
佐々木貴子さん) 科学的に議論が進まないのがいつも不思議で、情報格差があるのです。情報をどちらも同じく持ちながら考えることができればいいのにと、外環の問題ですごく歯がゆい思いをしたことがあります。パブリックインボルブメントといういい制度ができたなと初めは小躍りして毎回傍聴に行ったのですけど、賛成派からは何一つ意見が出てきませんでした。これで何が決まっていくのかという感じです。原発の核ゴミの処分に関しても、まだそのプロセスはやはり住民にとってベールの向こうで話されていることでしかないと実感しました。行政による対話集会というのは、そういうものに陥りやすいのでしょうかね。
高野聡さん) 三木さんは寿都町で4年間の文献調査を経験したということで、玄海町の町民当事者の石丸さんにアドバイスはありますか。政府やNUMOへの対応もしておられたと思いますし、町民とこの問題でどのようにコミュニケーションしたらいいのかについて等、何かありましたらお願いしたいです。
それから、石丸さんはこれから玄海町で本格的に文献調査が進むということで、寿都町で調査の4年間の経験がある三木さんに対してお伺いしたいことがあったら、ぜひ尋ねていただきたいと思っております。
最終処分場の文献調査について、おかしいと思ったことはすぐに追及して答えを出してもらい続けた
三木信香さん) NUMOや国は寿都町や神恵内村で失敗したことを玄海町ではうまくやろうとしているのではないかと感じたのです。玄海町の「対話を行う場」の話がありましたが、寿都では「対話の場」というのが作られました。その対話の場で偏りがすごくて、町長指名の17~18人が出たのですが、町民の公募もなければ、女性が1人で、年齢的にも一番若い人が30代1人で、あとはもう60代、70代の方で、構成もおかしいということを私たちは何回も訴えました。
「対話の場」だけど対話になっていないという玄海町の話がありましたが、寿都もほとんど非公開で、公開できるところだけを見ても全然対話になっていないと感じて、そこも問題として何回もNUMOや町や国に出したのですよ。それで次の玄海町では「対話を行う場」とうまいこと変えて言っていると思うのですけど、結果、名前を変えただけでやっていることは一緒かなと思うので。
私たちはおかしいと思ったことは常に意見書や質問状を出し続けて、答えを出してもらいました。大した答えではなかったのですけど、聞いておかしいと思ったことは常に直ぐに役場などに質問状などを出して、更生をしてもらいたいなと思って活動をしてきました。何か小さくてもいいので、私たちはとにかく抵抗してきました。
それで文献調査は2年では終わらないで結構長引きました。私たちがそういう活動をしたからとは言えないですけど、片岡町長はそんなに長引くとか反対する人たちがいるとは思っていなかったでしょう。 だけど私たち結構根強く頑張ったので、文献調査の報告書案もやっと4年目で出ました。なので、おかしいと思ったことはすぐ取り上げて追及するべきだなあと思って今も活動しています。
「対話の場」だけど対話になっていない住民説明会 実行委員会の顔は見えずNUMOが介在
石丸初美さん) ありがとうございます。
文献調査がスタートした6月10日からやっと1年が過ぎて説明会がありました。寿都町や神恵内村での住民説明会の回数と、どういう時期にどういうふうに行われたのか。玄海町の「対話を行う場」では住民の応募はたった5名、あまりにも少ないと思います。寿都町や神恵内村での反省の上で玄海町はやっているということだと思いますが、何を学習したのか疑問です。
玄海は実行委員会が非公開で4名指名されていますが、どういう人なのか、どういう立場の人なのか何もわかりません。実行委員会に要請書を出したくても「NUMOを通してください」ということでNUMOが前面に出てきて、実行委員会の方の顔は全く出てきません。実行委員会あての要請書はNUMOが受け取って、実行委員会からの回答をNUMOが貰って回答するというようにNUMOが盾になってしまっています。寿都町ではどういう状況だったのでしょうか。
三木さん) ニュースに出て町民は初めて知ったのですけど、何年か前から町長と仲のいい議員は話や計画はしていたのではないかなと思います。もう次々とすごいスピードで進んでいったので。町長が国に手続きをして1ヶ月半後ぐらいから住民説明会を各会館で行われました。その一回目の時はみんな訳がわからないので、割と参加者が多かったです。その時は町長と副町長と町民だったのですけど、この説明会が終わってから1か月も経たないうちに今度はNUMOの説明会がありました。NUMOは文献調査や処分場など事業について話をしたのですけど、一回目は結構な人数が集まったと記憶しています。
寿都町は片岡町長の独断ですべて始まったので。ただ、何年か前からそういう計画はあったのではないかなという気はしています。
川﨑彩子さん) 1つ素朴な質問があります。三木さんの発表の中で、最初はお金目当てで町長が手を挙げたことを町民としてすごく恥ずかしいという気持ちになったり町長を恨んだりしたというところから、最終的には国やNUMOに町長も含めて自分たちが押し付けられてきたのではないかと思ったというところが印象的でした。 どういったところからそういうふうに感じ方が変化したのでしょうか。
三木さん) 最初は町民に向けての活動しかしていませんでした。寿都町はふるさと納税もすごく良くて、お金にそんなに困っている町ではないと思っていたので、お金目当てで文献調査に手を挙げたのかと思ったら、なんでそんなにお金が欲しいんだろうと思いました。ちょっと買い物に行って寿都町という住所を書くのも嫌なぐらい、寿都町民であることが嫌になりました。
でも、周りの活動家の方からは、「寿都町だけの問題じゃないから、何かできることがあったら何でも言って」とたくさんお声をいただいて、なんで町長が手を挙げてこんなふうになっているのに「寿都町だけの問題じゃない」とみんな言ってくれるのかなと最初は思っていました。
だんだん、対話の場などいろんなことに参加していく中で、この法律のあり方がやっぱりおかしいと自分なりに理解できてきた時に、「ああ、これは多分、こういう田舎町に押し付けられているのかもしれない」と思えてきました。それで、「町長も、もしかして押し付けられたのかな」という思いがだんだん出てきて、それはだいたい3年目か4年目ぐらいで、そこから「これって、国にやらされているんだなあ」というふうに考え方が少しずつ変わってきたという感じです。
――グループ対話とグループ発表を経て、ゲストからのコメント――
※グループにゲストも加わり、グループの方々に感想や意見、ご質問を話し合っていただいた後、会場全体で共有するために印象に残ったことを各グループから発表いただき、ゲストからコメントをいただきました。
佐々木貴子さん) 皆さん、発表ありがとうございました。 市民が主体者として話す場をつくるプロセスに必要な情報も不足しているのではないか、その仕組みもまだまだではないか、まちづくりに事業者や国が入ってくるのは違うのではないかといった問題点も明らかになってきたと思われます。

北海道の市民が国・事業者主導の「対話の場」を検証する報告書を作成、特定放射性廃棄物小委員会に送付、経産省に質問 小さな変化もみんなで注目すれば大きな成果に
高野聡さん) みなさんからの問題提起に対する自分なりの答えとしては、成果は小さいけれども出ているのです。川﨑さんから「対話というのを一括りにして、非常にいい加減な形で使われている」という問題提起があって、まさしくそうですけど、寿都や神恵内で行われた「対話の場」の検証をNUMOがした際に、北海道の市民たちが独自に「対話の場」を検証して、報告書まで作っているのです。そして、それを私が所属する特定放射性廃棄物小委員会に送って、経産省にも質問しているのです。その市民が報告書を作った際には、川﨑さんの「対話」というものも市民がきちんと具体的な寿都の例を検証して、「私たちが思う『真の対話』とはこうだ」みたいな形で提示しているのですよ。
それはあまり知られていないですけれども、そういう活動を多くの人が知ることで、この小さな変化を大きくできると思うので、諦めずに活動して、その小さな成果でもみんなで注目すれば大きな成果になると思っています。引き続き、私自身は皆さんといろいろ連携して意見交換して、この問題に当たっていきたいと思っております。
三木信香さん) 川﨑さんのお話を聞いてちょっと思ったのですけど、私たちは「子どもたちに核のゴミのない寿都を!」という名前でやっているのですけど、それは子どもにプレッシャーになってしまうのかなと。でも私は、子どもが寿都をすごく好きで、たぶん永住するだろうなと思っていて、私たち親が死んで1人で寿都に残った時に、私と似ているので同じことできっと苦しむのではないかと思って、今活動しているのもあるのです。
私たちが住民投票条例を町に出した時は、16歳以上が何々に投票できるようにしてほしいとか、とにかく子どものためにというところを大前提にしてやってきたけど、結局、子どもが話せる場は今ないでですよね。
それでも、ハッピーロードの人たちに福島に連れて行かれて向こうの意見を植え付けられたような高校生と、私たちの会は活動を始めて6年目にして、話をすることができるようになったのです。その子の話を、こっちの意見をとりあえず一回目は言わないようにして聴いていたのですけど、全くいいことしか福島で聞いてなくて偏りが結構あって、そういう子どもがきちんと話せたり参加できたりする場を作るとしたら、どういう場がいいのかなと思ったことがあります。
あと、うちの子が住民説明会に小学校4年生か3年生の時に友達2人と行きたいと自分から言って行ったのです。質問を子どもたち2人で考えていって、うちの子は片岡町長に「核のゴミは安全なんですか?」と質問をしました。小学生でしたから、片岡町長は「わからないので、一緒に勉強しましょう」と言いました。もう1人の子が「核のゴミは寿都1箇所になんで集めるんですか?」と質問したら、それも「わからないので、一緒に勉強しましょう」と町長は答えました。それを言われて、2人ともさらに訳がわからなくなって帰ってきました。子ども自身の意思で行ったのですけど、周りの人たちから、「子どもを出したらおしまいだよね」とか「子どもに言わせているんでしょう」とか「やらせだよね」というのを私たちはすごく浴びたのです。でも、私は根気強くそういうイベントには子どもを連れていっているのですけど、そういう場をもっと増やすためにはどうしたらいいのかなと、川﨑さんの話を聞いて思いました。また相談に乗ってもらえたらと思います。
一人でもいいから伝えたい座談会を続けて 参加者が自由に発言できる場づくり 修学旅行の中学生も
石丸初美さん) 原発問題は「いのちと暮らし、そして社会や政治を知る大事な問題だ」ということが分かりました。伝えてくれた人に今、感謝しています。
私は知らないで過ごしてきた反省を踏まえて、一人でも伝える事が出来るかもしれないと、2009年から座談会を続けています。座談会は参加した人が、日頃思っていることを自由に発言できるところがいいと思っています。私自身が、講演会など人前で手を挙げて質問する勇気も自身もない人間なので、初めて聞く人も参加しやすい座談会を「一人からいいので聞いてください」と呼びかけてきました。
原発問題は大事なはずなのに、知らされていない事ばかりです。知ることで、暮らしの問題だということがわかる話です。ある中学生が修学旅行で玄海原発を視察にきて、その際、勉強会を頼んできました。中学生の子どもたちに話すには責任があり、資料も確認して作りました。みんな真剣に聞いてくれました。「初めて聞くことばかりだった」、「よくわかりました」といろんな感想をくれました。大人になったとき、「原発」という言葉に出会ったとき、考えるきっかけになればと思っています。子育て中のママたちにも伝えています。原発問題は知らない人に伝える事が大事と思っています。
「子どものため」という真意の違いに気づいている若者
川﨑彩子さん) 最後の最後に三木さんが私の話に触れてくださって、私は三木さんや他のいろんな住民の方々が本当に子どものために今の関係を残したいっていうことと、事業者側や国が「子どものため」と言いながらこの選択肢を取ることが子どものためだというふうに事業を進めようとするということとは全然違うと思っています。なので、三木さんも石丸さんも他の方も、これからも子どものためにということで活動を続けていただきたいなと私は思っています。
私は東京に今住んでいるということもあって、この問題の責任もすごく大きいなと思っていて、東京という地域からだからこそ、これを機に私の世代の人も含めて一緒にもっと考えたいなと思っています。
本日はありがとうございました。
佐々木さん) ありがとうございました。先ほど高野さんが小さい積み重ねを声に出したり、形にしたりすることで少しずつ広がっていっているということを話されました。政策のプロセスを透明にしていき市民の自治をきちんと守っていくような仕組みづくりを、ぜひみなさんと一緒に進められたらと思います。今日は本当にありがとうございました。
●次回SJFアドボカシーカフェのご案内★参加者募集★
『「薬物依存×女性」―尊厳をもって生きていくためにケアの視点を薬物政策に―』
【日時】2025年7月26日(土)13:30~16:00
【詳細・お申込み】こちらから
※今回25年6月25日のアドボカシーカフェのご案内チラシはこちらから(ご参考)

