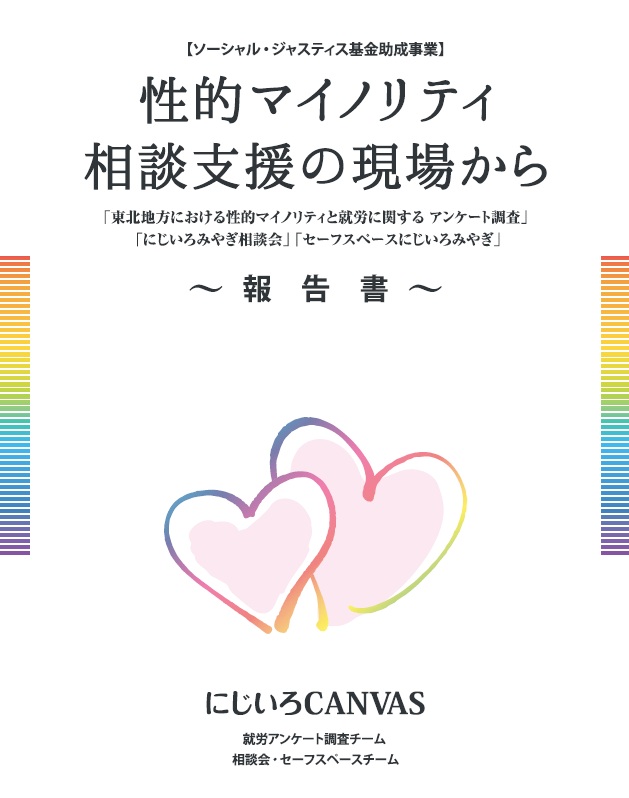ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)第11回助成
にじいろCANVAS
SJF助成事業最終報告(25年8月)
◆助成事業名:『にじいろみやぎ相談会・セーフスペースにじいろみやぎ開催、セクシュアリティと就労調査』
◆相談活動、居場所づくり活動を通して困難を抱えた性的マイノリティの課題解決を支援するとともに、そのニーズを把握し、持続的に支援可能な体制を構築する。
◆就労、特にその入り口となる学生時代の就職活動において困難を抱えてしまいがちな性的マイノリティの実態を把握し、キャリア支援の現場におけるジェンダー・セクシュアリティの扱いについての課題を明確化する。
◆上記活動・調査により明らかになった問題点を実際にキャリア支援に関わる機関と共有し、適切な対応がなされるよう働きかけることで、就職活動におけるジェンダー・セクシュアリティについての無理解・偏見に基づく不当な扱いをなくす。
◆助成金額 : 260万円
◆助成事業期間 : 2023年1月~2025年8月 *8カ月延長した
◆実施事業と内容:
◆相談会(2023年4月から2024年12月まで実施)
2023年4月10日から2024年12月21日まで、台風接近のため1回中止をしたが、毎月第4土曜日、偶数月の第2月曜日で合計33回、53件の相談会を実施した。1次相談とし、相談員は2人一組で対応した。(詳細は別添冊子を参照)
相談者が相談会の情報を知ったのは、当団体のSNSとホームページからという結果にもあるように、相談会の告知はSNSでの広報が主だった。
ほぼ毎回相談の申込があり、これまで当団体のことを知らない人、セクシュアルマイノリティの支援団体とつながったことがない人たちからの相談もあった。私たちが想定いたより多くの方々の申し込みを頂いた。
相談者の年齢も、10代から70代と幅広い年代に利用された。
利用者の自認するセクシュアリティは、トランスジェンダーが半数を占め、その他様々なセクシュアリティの方、セクシュアリティが決められない人からの相談もあった。
連携の観点からも、相談者がつながる社会資源について伺ったところ、相談者がつながる社会的支援は、医療、精神医療、保健福祉に関わる機関、就労・自立支援に関わる機関、LGBTコミュニティで47%を占める一方、全くつながりがないと言う方も10%ほどおり、社会的な孤立にある人がいることがわかった。今回、そのような方とつながれたことは、とてもうれしく思った。
相談者が抱える相談内容は、 セクシュアリティに関する相談、仕事・職場に関する相談、人間関係、家族・親戚、学校が上げられ、75%を占めました。自身のセクシュアリティと向き合う中、社会の中にセクシュアルマイノリティへの偏見、差別がある中での生きづらさ、人間関係を築く難しさを感じていることが伺えた。
相談会で相談員が行った対応は、傾聴、助言、情報共有、社会資源紹介、課題整理、支持などだった。
相談者が事後のアンケートで良かった点に、自分の困りごとを整理することができた31%、自分のこれからの希望を整理することができた22%とあり、相談員の、傾聴と課題整理の対応がうまく機能していたことが伺えた。
また、事後アンケートで「今回の相談の担当カウンセラーは、安心して相談できる雰囲気でしたか」という質問には、そう思う92%、どちらかというとそう思う2%の結果で、相談員たちは、はじめて出会った相談者も心開きやすくするなるよう、安心感を与えていたことが伺えた。
◆セーフスペースにじいろみやぎ
2ヶ月に1回奇数月の土曜日13時30分~17時30分に開催したセーフスペースは全10回となった。(詳細は別添冊子を参照)
セーフスペースには、当団体をはじめ県内・近隣のセクシュアルマイノリティ支援団体とつながっている方もいるが、セクシュアルマイノリティ関係団体とは全くつながっていない方々の参加もあった。全10回開催されたセーフスペースの申し込みおよび参加人数は、当初想定していた人数を遙かに超えのべ人数で申し込みが115人、参加人数は97人となった。開催会場は、プライバシー保護の観点から、参加者申し込みがあった方にのみお知らせし、当日は、呼ばれたい名前で参加して頂き、事前にお知らせするグランドルール【参照1】を守って参加して頂いた。
セーフスペースを始めたばかりの時は、スタッフは、当日はじめて出会う人たちの緊張を和らげ盛り上げることに集中していた。無言にしないで、手持ち無沙汰にしないで、何かをしてもらわなくては等試行錯誤だった。4時間という時間がとても長く感じられた。また、2ヶ月に1回の開催ですので、継続性を求めるのも難しいというのが悩みだった。
演劇をやりたいという声がでると、スタッフの知り合いの演劇人をゲストに呼んでみたり、お菓子づくりができる会場の時には、調理学の先生をゲストにお菓子作りを教えて頂いたりと言うこともしてみた。
そのような経験をしていく中で気づかされ、以下のことに注意するようになった。
1.全員で同じことを一斉にやりましょうにならないようにすること
2.開催場所はできるだけ日常を感じることができる場とすること
3.安全・安心が守られる場であること
そして、場づくりはスタッフだけが考えればよいというものではなく、参加者のみなさんとともにつくっていくものと言う考えにも変化していったように思う。勇気を振り絞ってセーフスペースの扉を開いて参加してくださった方々の声に耳を傾け、一緒に考える場をイメージするようになった。
セーフスペースで、何をセーフにするのかは大切な課題である。
セーフスペースは相談会とは違い、具体的な悩みや相談したいことが参加者の中にあるから参加しているわけではない。しかし、参加者のみなさんは、日常生活の中で何らかの生きづらさを感じ過ごしている方々である。
セーフスペースにじいろみやぎで、安心して自分らしくいることができ、考えや思い、感じたことを言葉にし他者と「対話」できる場であることは、参加者が抱えているモヤモヤを整理したり、元の生活に戻ったときの日常の生きづらさをとの対峙の角度を変えることにつながると思う。助成金がなくなると、資金面では大変になるが、セーフスペースを継続させていきたいというスタッフと参加者とともに、その場にいる人みんなで、心地よく楽に過ごすことを「対話」を通して模索して行きたいと考えている。今後は、自分たちでつくったものを販売したり、助成金やカンパで運営していくことになる。コミュニティや地域に賛同・協力を願いたい。
これまでのセーフスペースの様子は、スタッフが当番でnoteにて報告している(こちらから)。
◆相談員事例検討会:相談会で受けた事例について報告と検討
毎月第2月曜日 20:00~21:00
2023年:5/16、6/19、7/17、8/21、9/18、10/16、11/20、12/18
2024年:1/15、2/12、3/18、4/15、5/20
◆相談員研修会:毎月第2月曜日 21:00~22:00(ZOOM)
2023年
・5/16:2例のロールプレイングと検討(ZOOM)
・6/19:セクシャリティの受容課程とカミングアウトの段階、発達段階に沿った性自認、性的指向の気づきや需要
・7/17:トランスジェンダーと性別移行について
・8/21:セクマイと家族
・9/18:臨床心理士研修会報告、臨床心理士とは
・10/16:上半期の振り返り 以後は事例検討時に適宜実施
◆アンケート調査(2023年10/25~12/25)実施とまとめ
①就職活動とジェンダー・セクシュアリティに関するアンケート調査
②キャリア支援のジェンダー・セクシュアリティに関するアンケート調査
上記、アンケートを集計したものは、2024年4月23日(土)アドボカシーカフェにて発表した。
【冊子公開サイト https://note.com/2416canvas/n/nca5981a5fa57】
◆ネットワーク構築講演会
2023年9月24日〈日〉13:00開場 ⒔:30~16:30(仙台市子育てふれあいプラザのびすく泉中央ホール)
「セクシュアルマイノリティと子育て・家族・結婚」
講師:小野 春氏
共催:公益社団法人Marriage For All Japan結婚の自由をすべての人に
後援:宮城県 仙台市
協力:一般社団法人マザー・ウイング
広報活動:子育てふれあいプラザのびすく関係機関、公共施設へのチラシ配架、みやぎアピール大行進にてチラシ配布、SNS発信、まなびのめ、マチコ、仙台市子育て情報サイト等Web広報サイトに掲載、プレスリリース等を行った。
【実施報告】
入場者数:46名(内スタッフ11名含)
来場者からのアンケートからは、「満足」、「やや満足」の感想をいただいた。これまで宮城県内では、なかなか取り上げられてこられなかった「セクシュアルマイノリティの子育て・家族・結婚」を講演テーマにすることにより、これまでつながれていなかった、子育て支援に携わる方々や子育て中の当事者とのつながりをつくることができた。また9/19に仙台市から来年中にパートナーシップ制度創設の話しもでたためか、パートナーシップとの関わりから新聞社、テレビ局などからの取材も入り、私たちの活動をより多くの人々に知って頂く機会とすることができた。
記事掲載:河北新報 9/25掲載 こちらから
報道:ミヤギテレビ 9/28放送 こちらから
◆ジェンダー医療に関する情報交換、連携構築、
◇スカイツリーライン(埼玉県)の団体とつながり、スカイツリーライン企画講座の情報を頂き、オンライン講座への相談スタッフの参加。
「教えて、池袋先生 トランスジェンダーのこれから・・・」
「トランスジェンダーの法的性別変更を解説」
◆県外相談施設・パレードの視察、他団体との連携構築
東京研修(中野ハウジングファースト、パープルハンズ(大人食堂)、プライドハウス東京)
◇他団体開催学習会への参加
2024年7/28(日)開催のオープンダイアローグオンライン研修に、相談員の中から希望者が参加。
◆学習会
①2023年6月11日(日)15:00~17:00(仙台市サポートセンター)
「アンケート調査の方法と種類~就労支援調査に向けて」
講師:しゅんしゅん(社会調査士)
②2023年8月6日〈日〉13:30~16:30(エル・ソーラ仙台)
「性教育をみんなでアップデートしよう!」
講師:性教育を考える会@仙台、特定非営利活動法人キミノトナリ、AROW
③2024年1月18日(木)仙台・栗原パートナーシップ制度導入宣言緊急イベント(ZOOMオンライン)
にじいろCANVA、Color Calibrations共催
④読書会:2024/3/19(土)13:00~17:00(仙台市サポートセンター/ ZOOM)
「トランスジェンダー問題 TRANSGENDER ISSUE」
講師:しゅんしゅんさん、いつきさん
◆交流会:
①つくたべの会:2023年4/7(日)10時~16時(エルパーク仙台)
調理し食事を共にする中で交流を進める会を開催した。
②みやぎにじいろパレード2023うぢらで虹かけっぺし会場にブース出展・交流会場設置。セーフスペース参加者で折った折り紙でブースを飾り、セーフスペースの有志がつくったネイルチップの販売、アフリカンプリントで作成したグッズ、野菜の販売などを行った。また、パレード参加者が交流・休憩できるスペースを設置した。
③つくたべの会:2024年3/24(日)11時~15時(エルパーク仙台)
調理し食事を共にする中で交流を進める会を開催した。
◆事業報告冊子の作成・配布
助成期間を延長し、アンケート調査結果、相談会・セーフスペース開催状況報告、性的マイノリティ相談に関する提言をまとめた冊子を作成した。2025年8月に1000部発行し、にじいろCANVASホームページにて公開し、支援機関・団体、学校などに配布した。今後、パレードなどイベント開催の折にも配布していく。
◆事業計画の達成度 :
申請当初に挙げていた成果イメージは次の3点である。
・宮城・東北地域において、行政・民間の相談支援機関や自助グループが連携し、その人の困難に応じた継続的な相談支援体制が確立される。
・困難を抱えた性的マイノリティ当事者が安心して過ごせる場所が継続的に確保されることにより、就労することや他者と関わることが難しくなってしまった当事者が、再び社会と関わるきっかけが作られる。
・就職活動/キャリア支援の現場において、ジェンダー・セクシュアリティに関する問題が共有され、性的マイノリティはもちろん、あらゆる人にとって重要な人権問題であると認識されることで、就職活動をして社会に出てゆこうとする人が、ジェンダー・セクシュアリティに関する社会規範の抑圧を受けることなく、自身のこれからの働き方を考えることができる。
この3点であった。これらについて形となったもの・課題が見えてきたものがあった。
相談活動では、2年間で53件の相談を受け、セクシュアリティに関する相談の特性・傾向と必要な対応が明らかにできた。相談者の中には他の社会的資源に繋がっていない人も一定数おり、またセクシュアリティを開示できず人間関係に困難を抱えているという孤立した相談者の声を聴くことができた。トランスジェンダーからの相談が多くあったが、これは相談できる機関が足りていなかったことが示されたともいえるだろう。
性的マイノリティの就労調査では、特にトランスジェンダーは非正規の雇用形態が多く、職場で困難を感じることも有意に多いことが示された。困難に遭った時、相談するのは身近なプライベートな関係であり、既存の相談機関にはつながり難い状況も示された。また自由記述欄を通し、就職・転職活動での困難について、回答者から多くの声を聴くことができた。
支援機関に対するアンケート調査では、通常の相談業務の中でセクシュアリティをどのように捉えたらよいかわからないと感じている現状が読み取れた。
多くの支援機関の回答では、LGBTQ当事者もそうではない学生と同じように、少なくとも「偏見」やジェンダーによる 固定観念をもたずに支援することの重要性が述べられている。このことは支援の大前提であろう。しかし、非当事者と「同じ」対応をすることが、本当に当事者のためになるのだろうか。バイアスを持たずに 相手を接することと、支援の場にある異性愛主義やシスジェンダー中心のルールを見直すことはまた別のことである。たとえば、シスジェンダーの人々からは当たり前にみえるエントリーシートの性別記入に関して、それを 当事者にも「同じ対応」として強制するのは本当に支援であるのか。むしろこうした行為は、当事者を支援の場から遠ざけることになりうる。そう考えると、支援者には単に「同じ」対応に専念するよりも、「同じ対応」の裏にある自分たちの「ふつう」を見直す作業が求められるはずである。
また、マニュアルや研修を求める声も聞かれた。これは確かに知識に基づく対応を可能にし、属人的な支援のあり方を変えていく方法の一つになりうるものでもある。 しかし、そのマニュアルで語られるカテゴリーとしての当事者の裏には、個々別々の多様な当事者の生活があり、 ニーズもまた多様であることを意識すべきであると思われる。ある性のカテゴリーとして相談者や利用者を把握し、行う支援と、そのカテゴリーには回収されない個別の状況を把握し、行う支援は十分両立するものである。
今後、これらの視点を広く支援機関等と共有し、より相談者の実態に沿った支援のあり方を模索していきたい。
継続的な相談支援体制の構築にはつなげることができなかった。しかし、それに必要な人材や組織のあり方の方向性が示され、これが今後の地域の相談支援資源に繋がると判断し、この2年間の相談会をもって相談会は休会することとした。
この判断に至った要因は、財政の問題と相談員の不足である。今回の活動を通し、スタッフの一人一人の振り返りから、市民ボランティア団体の活動として相談会を継続させていくために重要と感じられた点を以下に上げる。
⑴ 組織体制
どのようなメンバーで、どのような体制をつくるか。仕事の分担、責任を明確にしながらも、一部の人に負担が集中しない体制や、自分たちの能力に見合った体制をつくる必要がある。
やりたいことと、やれることの見極め、今やれるから大丈夫ではなく、少し余裕をもって動ける体制でなければ、長期継続は難しいことを学んた。
⑵ 相談員自身の自己理解とリカバリーと資質向上
相談者の話に、しっかりと耳を傾けることができるよう相談員自身の心身の安定、コントロールができるよう仕事の割り振りの検討も必要だが、相談員自身が自分の心身に耳を傾ける機会を意図的に持つ必要を感じた。
また、セクシュアルマイノリティへの理解を深めるとともに、疾患、障害についての理解が求められた。
話をする、話を聴くの相談者としての基本的姿勢については、機会あるごとに互いに学び合う必要性を感じた。
⑶ 運営団体の活動と相談員
相談者を客観的に判断し、相談員自身のストレスを考えると、基本的には、相談を行う人間は運営団体の活動とは、コミュニティ特有な狭い人間関係の中、少し距離をおく必要があるのではないかと考えた。
⑷ 1次相談から次につなぐ連携づくり
定期的に継続開催する相談会は、相談スタッフの人材とともにその適切な人数の確保が必要である。相談に耳を傾ける時間を確保するには、スタッフにあたる人たちの奉仕の精神や好意だけでできるものではなく、スタッフが安全、安心して相談に専念できるためにもその時間への報酬も必要である。
今回、本業を持ちながらボランティアとして関わるスタッフのモチベーションは、さまざまだったと思う。
相談事業を専門的に行っていく場合には、有償化し、相談スタッフ自身も専門家としての学びを続けていく覚悟を持った形で行っていくことが、質の維持と継続性の点から必要なのではないかと考える。また、相談会の開催を社会に周知させ円滑に開催し相談者を受け入れていくためには、相談スタッフの他に事務的仕事とコーディネートするスタッフも別途必要であり重要であることを経験することでわかった。
本事業での相談件数は、開催前に予定していた人数をはるかに超え、相談したい人がこんなにいたのだということに驚かされた。また、来たくても場所が遠く来れない方や時間的に難しかったという声もあったので、ニーズがあることがわかった。公的機関の相談に行かずこちらの相談に足を運んだ相談者がいるということは、「セクシュアルマイノリティ」について理解しているという信頼があったからなのではないかと思う。
しかし、今回の事業を市民活動のボランティアとして定期的に継続開催をしていくのはとても難しいと思った。他に相談窓口がないのだから開設する必要性もあるが、セーフティーネットとして開設している既存の公的相談窓口になぜ行きにくいのか、今回の経験から既存の相談窓口の改善を訴えていくことも必要と考えた。
◆事業計画の成果 :
性的マイノリティは人口の数%であると言われているが、その声を発せている人はまだまだ少ない。ジェンダー・セクシュアリティに関する差別の存在がこうした声を聞こえなくさせていると言える。困難があってもプライベートな関係でしか相談できないこと。周囲に理解者がいるとは限らないこと。相談機関にカミングアウトできないこと。相談機関はセクシュアリティの問題がどのようなバリアになっているかを把握しきれていないこと。これらが相談事業からもアンケート調査からも読み取れた。
こうした声に対し、相談事業では傾聴し言語化し共感することで、課題を整理し情報提供し可能な行動を示すことで、相談者をエンパワーできた。また、セーフスペースで共に時間を過ごすことで、より日常的な生活感覚に近い形で人間関係が構築できる実感を持ってもらい、利用者をエンパワーすることができた。
しかし、さらに多くの性的マイノリティの声を聴き続けるためには、相談員など事業を遂行していく人材や安定した組織が必要である。性的マイノリティコミュニティが主体的にこれらを担っていくために、コミュニティ内部での役割の認識を深めていくことと、より広く機関への協力を仰いでいく必要性が強調される形となった。
これらの声を報告冊子にまとめることができ、これにより今後そのつながりを広げていこうとしている。冊子の配布は、自治体などへの提言、相談機関との連携、市民のプライベートな人間関係構築にも役立てるよう活用していく。
シスジェンダー・ヘテロセクシュアル中心で構築されてきた社会構造の中、性的マイノリティの存在は想定されてこなかった。この社会構造を乗り越え、相談支援機関やさらには教育機関など、対人援助の現場をセクシュアリティの多様性を前提としたものに変えていくことの一歩を踏み出せた。
権力や制度は、未だ性的マイノリティの存在を包摂できていない。同性婚実現やLGBT理解増進法の啓発・教育・相談の制度化などに、この成果を生かすべく、今後も発信を続けていきたい。
◆助成事業の目的と照らし合わせ 効果・課題と展望:
【Ⅰ】次の5つの評価軸それぞれについて、当事業において当てはまる具体的事例を挙げた。あるいは、当てはまる事が現時点では無い場合、その点を今後の課題として具体的にどのように考えるかを記載。
前回の中間4次報告の記載内容に対して、更新した点を記載すること。試行錯誤のプロセス、今後の課題やそれに対する見通しなど、具体的・詳細に記述。
(1)当事者主体の徹底した確保
相談会では相談者主体を徹底し、今後の行動が自己選択できるよう配慮した。
セーフスペースでは利用者のエンパワメントを意識し、行動する力を回復できるよう配慮した。
(2)法制度・社会変革への機動力
相談会・セーフスペース運営に注力したため、本事業での政策提言には至らなかった。しかし、この間は仙台市パートナーシップ制度への当事者ヒアリングへの参加、結婚の自由をすべての人に訴訟支援、同性婚仙台家事審判の支援などを行っており、これで培われた関係作りが今後の支援体制構築に活かせると考える。
(3)社会における認知度の向上力
相談会・セーフスペースの認知はSNSを利用した広報活動を継続し、一定の認知を得ている。みやぎにじいろパレード2024においてブースを出展し、セーフスペースでの活動の成果物を展示した。
(4)ステークホルダーとの関係構築力(相反する立場をとる利害関係者との関係性を良好に築いたり保持したりする力)
(2)と同様に、この点においても本事業での取り組みを展開できなかった。他の活動でのネットワークを活かしたい。
(5)持続力
セクシュアリティの課題に取り組む人員確保の難しさを感じた。相談活動を支えるには、大きなモチベーションと相談スキルが求められるが、他の本業を持った上での活動には限界がある。相談員の生活をある程度支えるだけの裏付けをもって、そのような人材を確保してゆく必要がある。
組織力を充実させ、団体としての責任能力を向上しておく必要を感じた。コンプライアンスを明文化し整備するとともに、より広範な専門知識を持った人と繋がり、活動に参画してもらえる体制構築が望まれる。
【Ⅱ】Ⅰの評価軸はいずれも、強化するには連携力が潜在的に重要であり、その一助として次の項目を考える。
(1)当事業が取り組む社会的課題の根底にある社会的要因/背景(根本課題)は何だと考えるか。
2024年12月に仙台市がパートナーシップ宣誓証明制度を開始した。政令指定都市では最後の導入であり、全国唯一空白県として残っていた宮城県にも導入自治体が所在し、やっと空白が埋まることとなった。2015年に渋谷区・世田谷区で導入された当初からこれに類する制度を仙台市でも導入するように政策提言し、2018年・19年には仙台市との市民協働事業~にじいろ協働事業を行い、2019年からは市議会会派へのロビイングを実施、その結果2021年から5年間の男女共同参画せんだいプラン2021にはパートナーシップ制度の導入の検討が盛り込まれたが、これがやっと実現したことになった。これだけ時間がかかったのは、性的マイノリティに関する社会の関心がまだまだ薄く、ごく一部のマイノリティの問題としての認識しかないことが原因であると推測される。
2023年にはLGBT理解増進法が制定されたにもかかわらず、未だ実施計画が策定されていない現状からも、こうした「ないがしろにされている」状況が見て取れる。
セクシュアリティ多様性の課題は、ジェンダー平等の基礎と位置づけられるものと言える。ジェンダー平等への取組みの精度を上げていくために不可欠な要素であると考えられるが、未だその認識は浸透していないと言わざるを得ない。こうした状況がシスヘテロ規範に縛られた家父長制の残滓が残り続け、繰り返しバックラッシュが起こっているひとつの要因であると言える。
こうした中、「LGBT」という言葉だけが広まり、マイノリティ個々人の状況は十分に認識されているとは言えない。また、障害や疾病を抱え孤立しがちなダブルマイノリティは取り残され、十分な支援が行きわたらない状況になっている。
(2)その根本課題の解決にどのように貢献できそうだと考えるか。
困難を抱える性的マイノリティは、社会資源の乏しい地方でより厳しい状況に置かれている。これらの人々のニーズを把握し、より効果的な支援体制を限られた資源の中で構築していく必要がある。反面で、コミュニティの小さい地方では他分野との連携を活かした実践が可能でもある。地域の課題を把握しながら、セクシュアリティの課題と困難を抱える人の課題が交差した問題に取り組みやすい。地方での活動の実践により、地方ならではの支援体制の構築に、本事業は貢献できると考える。
(3)他団体と連携したプロジェクトのアイディア、あるいは具体的な構想、あるいは希望などはあるか。
相談会・セーフスペースの事業はひと段落をつけ、その成果を地域で様々な課題に取り組む機関・団体に還元し、多分野が連携した支援体制の構築に役立てたい。また、全国のセクシュアリティに関する相談活動を行っている団体と連携し、セクシュアリティの課題に取り組む実践の効果をあげていきたい。
~宮城県地域では、みやぎにじいろパレードなどのイベント開催、交流会の開催、地域団体・教育機関・支援機関・団体等への講師派遣、相談支援活動など、セクシュアリティに関する重層的な活動が複数の団体によって展開されている。これまでの活動の経緯などから、これらの団体は互いに顔の見える関係にあり、様々な状況にある当事者のエンパワメントに貢献している。今後この連携をさらに深化させて、多様な当事者と共にある活動を進めていきたい~ ■